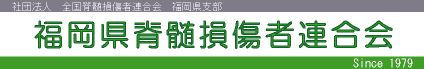
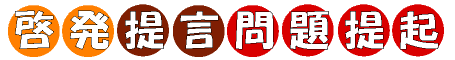
![]() 障害者の法と正義
障害者の法と正義
文化体育部長 久保 親志
今、わが国の法の支配が揺らいでいます。法の支配とは、「あらゆる国家機関が個人の自由と平等を保障する正義の法たる正しい法に拘束される」という原則です。
つまり、法の支配が適切に行われていないところには正義の実現はありえないし、国民の自由と平等は守られないことになるのです。そして、日本国憲法がこの法の支配」の原理を採用していることはいうまでもありません。
一国家にあって法と正義が守られているということは、国民(市民)が安心して生活を営む上での基本です。そのためには国を構成する三つの機関である立法・行政・司法が、各々の役割を国民(市民)のために正しく遂行していくことが必要なのです。
しかし、わが国の現状はどうでしょうか、まさに揺らぐ三権といっても過言でないスキャンダラスな内容の報道が毎日私たちの茶の間に飛び込んできます。
KSD事件での前参議院議員らの逮捕や外務省の外交機密費疑惑、そしてなんと前次席検事の捜査情報漏洩問題等々。
本当に私たち国民(市民)の常識をはるかに越えた内容の事件ばかりです。
いまは、おりしも1999年7月、国民(市民)にとって分かりやすく利用しやすい司法を目指して、鳴り物入りで発足した司法制度改革審議会の中間報告が昨年11月示され、その骨子である三つの柱を中心に、今年6月の最終報告に向けて積極的な審議の充実が叫ばれている最中です。
改革の三つの柱とは、「人的基盤の拡充」、「制度的基盤の整備」、そして「国民的基盤の確立」です。
ところが、国民(市民)にとってこの中間報告はもとより審議会に対する関心は低くく、審議会の存在を知っている人の数は僅かにすぎません。
これは、裁判官・検察官・弁護士といった一握りの法律の専門家による司法の独占が、国民の司法離れを招いた結果ではないでしょうか。
中坊公平元日弁連会長のいわれるように、「わが国の司法というのは本来果たすべき機能の二割しか果たしていない」という意味において「二割司法」であるといえます。後の八割は「泣き寝入り」、「政治決着」、「暴力」そして「行政指導」といった弱肉強食形の紛争解決で片づけられてきたのです。特に、障害者の場合は、我慢と諦めを強いられた「泣き寝入り形」の解決が最も多く、法と正義の実現には程遠いものであったのは、私の経験上確かです。
また、私たちの周囲を見ても、経済的・社会的に弱い立場の人たちが自由や権利を侵害され、いわれなき差別を受けている例はあとを絶ちません。そういう場合こそ、真の意味で司法を活かして用いる必要があるのではないでしょうか。
そのような弱い立場の人が、生来もっている生命・自由・平等が保障され、少しでも幸福になれる国こそ正義の法にかなった国だといえます。
そこで、21世紀の「この国のかたち」を変えるため、私たち障害者市民も自分が主権者であり統治の主体であるという意識をもって司法を検証し、能動的に司法に参加することが必要だと思います。裁判の傍聴もその一つです。車いすで積極的に裁判所に出かけ「裁判ウォッチング」をしてはどうでしょうか。
裁判は公開で、誰もが自由に傍聴できます。裁判所や法廷内の現場を見ておかしいと感じたことは、はっきりと声を上げて改善を求めていくべきです。残念ですが司法制度改革審議会には、障害者の声はあまり届いていないのが現状です。
障害者の法と正義の実現こそが、全ての国民(市民)にとって分かりやすく、利用しやすい司法になるのですから、是非「我ら自身の声」を届けましょう。
これこそ正に、バリアフリーの司法制度改革だといえるし、また障害者の権利の実現のため、リーガル・アドボカシー(法的権利擁護)運動を国民(市民)と共に推進する「車輪の一歩」ではないかと、私は考えます。
2001年3月
(広報誌「わだち」No.105より)
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ ![]() レクリエーション
レクリエーション
![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」