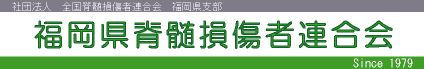
| 裁くのはあなたです! 〜模擬裁判員に選ばれて〜 文化体育部長 久保 親志 |
||
福岡地方裁判所で、2月23日(月)から25日(水)の3日間開かれた、裁判員模擬裁判で本番と同じ手続を経て「模擬裁判員」に選任されました。その後、他の模擬裁判員と共に、裁判長から、裁判員の職務について説明を受けた後、宣誓を行いました。いよいよ、職務を遂行するときが来たのです。 被告人が犯行を否認している「傷害致死被告事件」を想定した模擬裁判で、3人の現役裁判官と私たち6人の裁判員役の合計9人で301号法廷の壇上での審理や評議室での評議を重ねて評決を行い、裁判長による判決の言渡しまでの刑事裁判の全過程を体験しました。勿論、検察官と弁護士も現役でした。裁判員裁判の大筋の流れは、「冒頭手続」→「証拠調べ手続」→「弁論手続」→「評議」→「判決宣告」迄です。私の3日間の体験を記憶とメモに基づきコンパクトにまとめて記します。 冒頭手続(陳述) 被告人の確認(人定質問)が行われ、検察官が起訴状を朗読しました。続いて事件の具体的内容を説明する「冒頭陳述」が行われました。検察官側が立証しようとするのは、起訴状によると、「大工の被告人Aが居酒屋で一緒に酒を飲んでいた同僚男性Bと店を出た後、路上で泥酔した男性を殴る蹴るなどの暴行を加えて、腹部に致命傷を与えて死亡させたとする傷害致死罪(刑法第205条)」です。法廷の左右に掲げられた大型ディスプレイモニターと、法壇上の裁判員の手元の小型モニターに陳述要旨が映し出され、更に配布された紙ベースの陳述要旨、これを示しながら検察官と弁護人双方の陳述が行われました。 検察官の主張は、「被告人Aと被害者Bは仕事仲間で飲み友達である」「事件のあった時間に被害者Bと一緒にいたのは被告人Aだけ」「被害者Bは何者かに腹部を蹴られて死亡しており、着ていたTシャツにはサンダルの左足つま先部分の跡がついていた。跡は被告人Aのサンダルの形と矛盾しない」という。 これに対し、被告人は「酔っていて腹を蹴ったことや暴力行為などは記憶にない」と犯行を否認しました。弁護人も「被害者BのTシャツの腹部に残る足跡はサンダルと合わせると数ミリずれる。被告人Aのサンダルとは別の形のものかもしれない」と反論し無罪を主張しました。最後に、法壇上の私たち裁判員に向かい「刑事裁判の原則の『疑わしきは被告人の利益に』を忘れないで下さい!」と締めくくりました(刑事裁判では、検察官が証明責任を負いますが、ある事実の存否がはっきりしない場合には、被告人に対して有利に事実認定をしなければなりません)。 裁判の争点は、「本当に被告人Aが、被害者Bに致命傷(内臓破裂)を与えるほど腹を蹴るなどの暴行を行ったかどうか」です。有罪か?無罪か?有罪ならばその量刑は、どうなるのかを判断しなければなりません。結論が分かれる難しい事案だなと感じました。 証拠調べ手続 検察官側の「証人」が登場しました。1人目は、事件の当日2人が飲んでいた居酒屋の店員Cです。「2人が来店したのは午後6時ごろ、被告人Aは、大声を出すなど酩酊状態の被害者Bをなだめていた。被害者Bが店を出たのが午後7時45分。被告人Aがトイレに入った後、店を出たのが午後8時です」との証言でした。モニター画面で見る限り居酒屋の外は人どおりが多い道路です。ここに、被告人と被害者の「空白の15分間」が存在したのです。 2人目の証人は、被告人Aの部下であり被害者Bの友人Dです。事件当日の夜遅く、被告人はDに頻繁に携帯電話をかけていたという。「証拠書類」の通信記録からもその事実は明らかです。証言によれば、「Bちゃんが動かない、どうしようか」と焦った声で語ったとのこと。また、「居酒屋から出たらBちゃんが寝転がっていた。起こそうとしても起きないし、2、3回くらい蹴ったかも知れない?このことで死んだら大変だ、伏せておいて欲しい」と言っていたとも証言しました。 3人目の証人も2人の共通の友人Eです。大きな動作を交えながら、事件の2日後、仕事現場で「被告人Aが、『お尻を蹴ったかも知れない』と言っていた」と証言しました。私は、この「蹴ったかもしれない」の言葉に注目しました。 続いて被告人質問が行われ、「酔っていてよく覚えていませんが、起こそうとしましたが、顔を殴ったりお腹を蹴ったりはしていません」と被告人Aは答えました。犯行を示す、有力な物証がなく「状況証拠」のみでした。 弁論手続 法廷で、被害者Bさんの妻の調書を検察官が読み上げました。「被告人Aは絶対に許すことは出来ません。懲役の最高刑が20年なら、是非その刑にして下さい」と被害者家族の気持ちを代弁しました。検察官は、証拠を大型モニターに示しながら、「被告人の弁解は不合理である」と論告し、懲役8年を求刑しました。 一方弁護人は「空白の15分間に他の者が殴ったり、蹴ったりする可能性がある。また被告人が被害者の腹部を蹴りつける理由が見当たらない」と無罪を訴えました。これで、法廷での審理は終わりました。 後は、3人の職業裁判官と私たち6人の裁判員役の合計9人で非公開の評議室での最終評議です。 評議 本来は非公開ですが模擬裁判ですので、参考程度に触れてみます。 ラウンドテーブルに9人が着席しました。中央に裁判長が座り裁判員がそれぞれ裁判員1番から裁判員6番までが座りその間に他の2人の裁判官が分れて座ったのです。この並び方が裁判官3人一緒に座るより「評議」がし易いと思いました。ちなみに、私は裁判員3番で裁判長の右隣でした。 さて、評議が始まりました。検察官と弁護人の両者共どちらの足で何回踏みつけたかを尋ねていません。証拠から事実を認定することで、「着ていたTシャツに残った足跡が、被告人Aのサンダルと合致しているかどうか」が評議の論点です。裁判長も2人の裁判官も、問題点を整理して同じ論理過程をたどっていました。 裁判員の意見は、この「足跡の鑑定」で躊躇しました。証拠の判断は裁判員に任されるのです。「蹴った程度で内臓が破裂するだろうか。これは踏みつけたのではないのか」という裁判員。他の裁判員は、「踏みつけたなら、かかとの足跡が残るのではないか」という。「被告は右利きだが、踏みつけられた被害者のTシャツには左足つま先の跡が残っているのは不自然だ」という意見。「被害者が横を向いて倒れていれば、つま先で蹴ることができる」という反論。裁判員が「Tシャツに残った跡は被告の踏み方と関係する」と拘った議論が続きました。結局、足跡は似ているようだが、確定は出来ない。もし蹴っていたとしても致命傷を与えるものではないだろう」との結論に落ち着きました。 さらに、「空白の15分間に他の者が殴ったり、蹴ったりする可能性」についても、意見を出し合い、私は、「他の者の犯行の可能性は捨てきれない」と思いました。また、検察官の証明は、常識に従いどう考えても「合理的な疑問が」残りました。裁判員と裁判官が十分に議論を尽くしたころに、いよいよ評決です。 無罪8人、有罪1人の「評議の結果」がでました。この評議の結果に基づき裁判長が判決書の原稿を作成し、いよいよ法廷で判決が宣告されるのです。 判決宣告 法廷壇上に裁判長を中心に、右陪席、左陪席の裁判官が着席し、その横側に私たち6人の裁判員が着席しました。静まりかえった法廷に裁判長の声が響き渡りました。「主文。被告人は無罪」。判決宣告により裁判員の職務はこれで終了しました。 3日間に亘る「模擬裁判員裁判」が終了して、正直なところほっとしました。職業裁判官と一緒に、思想、性別、社会的身分、職業などの異なる私たち一般市民が「重大刑事裁判」につき議論し評決したことは、貴重な体験が出来たと思います。 それは、異なる経験や知識を持った人と議論をすることにより、自分の「思い込みや決めつけ」に気付かされたことです。これが、裁判員裁判の導入理由の一つかなと感じました。とにかく裁判員制度が始まる迄あとわずかです。そして、裁くのはあなたです! |
||
|
||
| 障害者権利条約に関する一考察 文化体育部長 久保 親志 |
|
| (その1) 2007年11月 | |
| 現状認識(はじめに) |
|
皆さんはすでに、新聞や「わだち」No.144で周知のごとく。高村外務大臣は9月28日午後、ニューヨークの国際連合(以下、国連。)本部で、障害者の固有の尊厳、個人の自律及び自立、差別撤廃とすべての分野において均等な社会参加の促進を求める、人権条約「障害者の権利に関する条約」(以下、障害者権利条約。)に署名しました。更に、政府から同条約の「仮訳文」も出されました。昨年12月13日、第61回国連総会で同条約が全会一致で採択され、本年3月に署名のために開放されて以来、すでに113カ国と欧州共同体(EC)が署名を終わり。必要な国内法の整備をして条約を批准している国はクロアチアやキューバなど5カ国(9月27日現在)。条約が発効する要件は、20カ国以上の批准(締約)が必要となりますが、現在はまだ20カ国に達しておらず、発効していない。 障害者を対象とした権利条約は初めてのことで、世界人口の1割、約6億5千万人(国連推計)とされる障害者の人権の拡大に大きく寄与されるとの期待が高まっています。繰返しますが、同条約は、批准国に対し、「個人の尊厳」を基礎として、交通、教育、雇用などの面で障害者の立場改善のための立法・行政措置を要求、障害者を差別する国内法を見直し、必要な法整備を義務付けています。 しかし、先の政権が「国内法の整備が整っていない」という大義名分をつけて署名しなかった経緯があり、政権が代わるとこうも変わるものか、不思議です。報道によれば、政府は外務省や法務省、警察庁など9省庁で構成する「障害者権利条約にかかわる対応推進チーム」をすでに発足させています。今後、同チームを中心に、関連する法律の改正などを論議し、早期の批准をめざす考えのようですが、まだまだ、課題が山積しています。それは、この「障害者権利条約」が、一般国民(市民)に理解されていない、政府の「仮訳文」にも誤訳がある、いや!当事者である障害者市民すら十分に理解されていない等々。 それは、全脊連・第31回九州ブロック会議福岡大会の記念講演「“国連・障害者の権利条約”とは」を、熱心に語られる講師東俊裕弁護士と会衆との間に温度差を感じたのは、私だけだったのでしょうか。以前、織田晋平事務局長が、障害者権利条約につき、「わだち」No.141で述べていた、「まず、法内容を読み解くことから始めてほしいと思います。同法を生かすも殺すも、一人ひとりの『理解と行動(権利行使)』に委ねられていることを、・・・」を思い出しました。正しく、その通りです。 そこで、障害者市民の立場で障害者権利条約の考察に着手した次第です。 |
|
| 文理解釈 |
|
始めに、基本論点を明らかにするために障害者権利条約の文言から見ていくことにします。条約を正しく解釈し、立法趣旨・目的に則って「国内法を変える必要性」を関係各省庁や国会議員に訴えるために、必要だからです。では、事典を用いて「国際連合」「条約」の文言それぞれを見てみます。 先ず、国際連合(United Nations)とは、「国際連合憲章の下に設立された国際機構である。世界の平和と経済・社会の発展のために協力することを目的とする。」略称は、国連、英語ではUN。(フリー百科事典『ウィキペディア・Wikipedia』より。)と、いうことです。 次に、一般的に解する条約とは、「国家間、または国家と国際機関との間で結ばれる文書による法的な合意。条約という名称のもの(狭義の条約)だけでなく、協約・憲章・取極・議定書・宣言・規程・規約などの名称のものも含む」(三省堂『大辞林 第三版』より)。更に、法的にみると「条約とは、国際法の主体間において、一定の権利義務を当事者間に生じさせるために、書面の形式により、かつ国際法の規律に従って締結される国際的合意である。」(有斐閣『法律学小事典』より。)と、いうことになります。 今回は、国連の障害者権利条約の「現状認識」に多く紙面を割きましたが、次回から少しずつ条約の中身について、考察したいと思います。(つづく) |
|
| (その2) 2008年1月 | |
今年は、「世界人権宣言」が1948年12月10日、第3回国際連合総会において採択されて60周年を迎える記念の年です。昨年は、「日本国憲法」施行60周年を迎え、政府をはじめ日本弁護士連合会や人権団体などで記念式典及び記念講演などが各地で実施されました。私も、日本国憲法の三原則、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」について多くの場で学ぶことができました。 今年も、「人権の世紀」といわれる21世紀に相応しく、世界人権宣言60周年記念の催し物が、世界各国で行われることでしょう。昨年、署名に伴い、政府の「仮訳」が公表された「国連・障害者権利条約」を学習し検証を重ね、いま世界の大きなうねりの中で、政府仮訳のすべての問題点を検討し、政府に修正を求めて行くことが大切です。続いて、政府の公定訳作成の場を設けることが必要となります。最終的には、条約を政府が翻訳した「公定訳」を見ながら条約の締結を承認するかどうかについて国会で議論することになります。 国会で承認を得ることになる政府の公定訳に、私たちの意見が取り入れられること。その議論と意思決定過程において、障害者団体及び障害者市民の参加を保障することを求めて行く運動が重要だと考えます。 世界人権宣言の第1条に、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」と、あります。 また第7条に、「すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。」と、もあるのです。 まさに、この理念にそって「障害者権利条約」を取り巻く現状を認識すると同時に、条文をしっかり読み解き考察を重ねて行くべきです。 さて、「文理解釈」の続きに入ります。前回、この解釈について何も説明していませんでしたので、説明します。文理解釈とは、「法律条文を構成している言葉を通常の意味に従ってそのままに理解すること」です。よって、「法律の適用を受ける一般国民が、その法律条文の意味内容を把握することが比較的容易であり、行動の指針を得やすい」という特徴があります。法律の解釈には、他に、「目的論的解釈」、「反対解釈」、「拡張解釈」、「縮小解釈」、「類推解釈」などがあります。実際に解釈を行う場合、先ず、文理解釈で解釈し、それでは妥当な解決ができないときに、解釈の対象となる法規範の目的に従った目的論的解釈を行います。そして、その目的論的解釈の道具として、他の解釈の方法があるものといえます。では、「権利」について見てみましょう。権利とは、「ある利益を主張し、これを享受することのできる資格。社会的・道徳的正当性に裏づけられ、法律によって一定の主体、特に人に賦与される資格」(三省堂『大辞林』 第三版より)です。さらに、「権利とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう」(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)ことになります。 事典を用いて、「国際連合」、「条約」、「権利」の三種類の文言それぞれを解釈してみました。続いて「障害者」です。障害者とは、「身体または精神に何らかの障害をもつ者」(三省堂『大辞林』第三版より)と、なります。これら四種の文言を合わせて、障害者の権利条約をさらに辞典で調べますと、次のようになります。 障害者の権利条約とは、「障害者への差別を撤廃して、健常者と同等の権利を保障する国際条約。2006年12月、国連総会で採択された。障害者権利条約。」(三省堂『デイリー 新語辞典』より)と、一般国民に解釈しやすいものとなると思います。 しかし、事典、辞典などを用いた解釈だけでは、実質的解釈に欠けますので、次回から、法的な思考力をも、加味して条約の文言を考察したいと思います。(つづく) |
|
| (その3) 2008年3月 | |
| 本条約の基的な考え方 | |
障害者に関する法律や制度は、恩恵と福祉そしてリハビリテーションの対象として考えることが多いのですが、「障害者権利条約」は人権を観点として創られました。 人権とは、人間が人間らしく生きるために生来持っている権利をいいます。今まで、人権は大別すると二つに分けられて来ました。 それは、自由権(個人の自由が国家権力の干渉・介入を受けることのない権利)と社会権(個人の生存、生活の維持・発展に必要な諸条件を確保するために、国家に積極的な配慮を求める権利の総称)です。自由権に関しては、政府は間をおかずにすぐに実施する義務がありますが、社会権に関しては順を追って徐々に目的を実施する義務しかないといわれて来ました。 また、権利の内容についても、前者は権利性が強いが、後者は弱いとされて来ました。 しかし、本条約では、自由権と社会権の二分論をまとめた形、いわゆる「包括モデル」になっています。障害のない人にあたりまえに保障されている権利を障害者にも平等に保障しているのです。逆にいえば、障害者に特別の権利を与えるものではなく、同じ人間なのに、障害があるゆえに、人権を考慮せず「実質的不平等」がもたらされている現状を解消するための条約です。 また、従来「医学モデル」の視点から、障害を個人のものとし、自己努力とリハビリテーションによって克服することで、保護の客体として発達して来た障害者福祉の枠組みを大きく転換し、「障害は個人ではなく社会にある」といった「社会モデル」の視点から捉えたのです。 つまり、私たちが、求め続けていた「保護の客体から権利の主体へ」の転換を基調にした法的拘束力をもつ条約によって規定されたものなのです。 さらに、障害のある世界の仲間たちが、私たち抜きに、私たちのことを決めないで!(Nothing about us, without us !)を、合言葉に働きかけを続けて障害当事者の視点から作られた条約であることも特徴的です。 |
|
| 理念と原則が凝縮、前文を読んでみよう | |
法的拘束力はありませんが、条約解釈の指針となる大切な条文です。 先ず、「前文」の (a)〜(c)項を読んで解釈してみましょう。この条約の締約国は、(a) 世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものとして、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び価値並びに平等のかつ奪い得ない権利を認める国際連合憲章において宣明された原則を想起し、(b) 国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての者はいかなる区別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、(c) すべての人権及び基本的自由の普遍性、不可分性、相互依存性及び相互関連性、並びに障害のある人に対してすべての人権及び基本的自由の差別のない完全な享有を保障する必要性を再確認し、・・・「川島聡・長瀬修 仮訳(2007年10月29日付)から引用」。 この箇所は、世界人類社会のすべての構成員(障害者を含む)の固有の尊厳、平等原則を定めています。 国連の「世界人権宣言」「国際人権規約」に基づき、すべての人間の固有の尊厳、平等、権利を保障すべきであることが、世界の自由、正義及び平和の基礎を成すものであり、世界はそれを宣言し明らかにして合意しました。 すべての人権、基本的自由は普遍的であり、不可分で相互に依存関連するものであることを認め、そのためにすべての障害者がこれらを差別なしに完全に享有することを保障しなければならないのです。 私たちは、今後この障害者権利条約を十分に理解すると共に、人権の視点から我が国の福祉のあり方を捉え、国の施策も組織もすべて「個人を守り、個人の人権を保障するための手段なのだ」ということをきちんと認識して、行動すべきです。 そして「個人の尊厳の確保」という目的の実現のため、障害者運動の手段(道具)として条約を活用して行くことが大切だと考えます。(つづく) 参考文献「東俊裕・監、 DPI日本会議・編『障害者の権利条約でこう変わる Q&A』解放出版社、松村明・編『大辞林 第二版』三省堂」。 |
|
| (その4) 2008年6月 | |
| 歴史的瞬間「障害者権利条約」が発効 | |
世界中すべての人に普遍的人権の実現をもたらす「障害者権利条約」が、2008年5月3日、法的効力を発生しました。既に4月3日、エクアドルが批准したことで、効力発生要件である計20カ国の批准を満たした為です。条約締結国は、差別をなくし、教育や雇用などあらゆる分野で障害のある人に障害のない人と同等の権利を保障する義務を負います。 国連によると、現在までに日本を含めて127カ国が署名し、これまでに25カ国が批准しています。アジアではインドやバングラデシュが批准しています。また、潘基文(パン・ギムン)国連事務総長は、「これは、すべての人のための完全にインクルーシブな社会の創造に向けて、すべての人の普遍的な人権の実現を追求している私たちにとって、歴史的瞬間です。」と発効を歓迎する声明を発表しています。私も同感です。何故ならば、「障害のある人」の権利を保障することは「障害のない人」の権利も保障することになるからです。 日本政府も昨年9月に署名し、現在は批准に向けて外務省や法務省、警察庁など9省庁で構成する「障害者権利条約にかかわる対応推進チーム」を発足させ準備作業を進めていることは前にも述べました。条約の批准は当然ですが、政府にいま求められているのは、ただ単に批准さえすれば良いとする態度ではなく、障害者の権利保障をうたった条約に違反するような法律や政令、条例などを早急に改正・修正することが重要な課題なのです。 一方、私たち障害者市民と障害者関係団体も、権利条約の「政府仮訳」のすべての問題点を検証し、政府に修正を求めて行くことが大切です。続いて、「政府公定訳」作成の場を設けることが必要となります。最終的には、政府が翻訳した「公定訳」と「正文」を見ながら条約の締結を承認するかどうかについて国会で議論することになります。国会で承認を得ることになる政府の公定訳に、私たちの意見が取り入れられることが大切です。権利条約をお飾りにしないためにも、その議論と意思決定過程において、障害者市民及び障害者関係団体の参加を保障する運動が必要だと考えます。 |
|
| 権利条約の目的について | |
それでは、「前文」に続き、第1条「目的」の条文を読んで解釈してみましょう。この条文は条約の制度趣旨と目的を基本的に示した文章です。 「この条約は、障害のあるすべての人によるすべての人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し及び確保すること、並びに障害のある人の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。 障害〔ディスアビリティ〕のある人には、長期の身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害〔インペアメント〕のある人を含む。これらの機能障害は、種々の障壁と相互に作用することにより、これらの機能障害のある人が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げることがある。」(川島聡・長瀬修 仮訳2007年10月29日付から引用) 21世紀は、「人権の世紀」と呼ばれています。正に、今世紀最初の人権条約である「障害者権利条約」の目的は、人権保障の国際的合意点を示しています。 前段は、すべての人に保障されるべき、普遍的な人権と基本的自由を、障害のある人に対して差別なく完全かつ平等に享有することを提起しています。すべての分野において、「障害にもとづく差別」を禁止し、固有の尊重を促進するために、締結国が適切な行動をとることが義務付けられています。 後段は、「障害」や「障害のある人」を、体のどこかに機能障害「インペアメント」があり、そのことと社会の障壁との相互作用によって、社会参加に制約を受ける人を障害者なのだという考え方、つまり障害は個人ではなく社会にあるとする「社会モデル」を明確に規定しています。わが国の「障害者基本法」などにおける、障害者の定義より広くなっていると思います。(つづく) 参考文献「東俊裕・監、 DPI日本会議・編『障害者の権利条約でこう変わる Q&A』解放出版社、編集代表・奥脇直也『国際条約集 2008年版』有斐閣」 |
|
| (その5) 2008年8月 | |
| 合理的配慮とは何か | |
| 障害者権利条約において、国際人権条約として初めての概念である、合理的配慮(reasonable accommodation)を、第2条「定義」から見てみることにします。 条文によれば、「『合理的配慮』とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。」(川島聡・長瀬修、仮訳2008年4月19日付)とある。 また、条約署名のため政府の出した同条文の「仮訳文」と比較して見ると、「『合理的配慮』とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」(政府仮訳2007年9月)とあり、前者の「仮訳文」(川島・長瀬訳)の方が的確で分かりやすい。 原文の、「リーズナブル」(reasonable)という言葉を辞書で引くと、最初に「合理的な」「分別のある」「 無理のない」と示されます。 次に、「アコモデーション」( accommodation)を引きますと「適応」「調節」「 融通」という意味が示されます。つまり、障害から派生する諸問題の解決を「障害者個人の自助努力に求めるのではなく」、「社会的環境を論理にかなった、適切な変更や調節をすることで解決すること」そしてそれは、あまりに大きすぎる負担がかからない限り、社会に対して当然求められる基本的人権の行使であると解釈されます。 本条約では、自由権と社会権の二分論をまとめた形、いわゆる「包括モデル」になっていることは前述しました。障害のない人にあたりまえに保障されている権利を障害者にも平等に保障しているのです。逆にいえば、障害者に特別の権利を与えるものではなく、同じ人間なのに、障害があるゆえに、人権を考慮せず「実質的不平等」がもたらされている現状を解消しなければなりません。 そのために導入された新しい概念の一つが「合理的配慮」というもので、本条約の大きなキーワードです。 |
|
| 具体例で考えてみよう | |
たとえば、出入り口に階段などがある会社に車いす常用者が就職しようと求職活動をした場合を想定してみましょう。人事担当者が、「うちの会社には残念ながらエレベータがありません。階段しかないので採用はお断りします。」ということがあったとします。階段しかないのが現状であっても、障害者の雇用に際してはスロープを設置するなど適切な変更で改善できることであれば、それは当然その配慮をするべきだという考え方が「合理的配慮」です。 ところが、階段しかない狭いテナントビルに入っている中小企業の場合で、新たにエレベータを設置するとなると、会社の経営が回らなくなるような多額の費用がかかる、あるいは物理的に、そもそも設置が難しいという状況であれば、「合理的配慮は無理」である、又は「合理的な範囲を越えている」ということになると思われます。ただし、資本金の額が3億円を越える会社もしくは300人以上の従業員を常時使用するような大企業が安易に、「階段しかないので、うちは障害者の方は雇用できません。」といい出した場合は、合理的配慮が行われていない、つまり、「合理的配慮義務違反」になり、条約では差別にあたります。合理的という言葉の中には、障害者にとって「合理的」というだけではなく、雇用主などにとっての「合理的判断」という面が含まれており、「合理的配慮」とは両者の間の「合理性」をめぐって適切に調整されるものであると考えます。 現在、厚生労働省職業安定局において「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」が公開で開催されており、6月27日で第3回を終えています。皆さんもホームページなどでご確認下さい。(つづく) 参考文献「東俊裕・監、DPI日本会議・編『障害者の権利条約でこう変わる Q&A』解放出版社、『NHK社会福祉セミナー(2008年7月〜9月号)』日本放送出版協会」。 |
| (その6) 2008年10月 | |
| 権利条約批准37か国へ | |
障害者権利条約を批准した国は、トルクメニスタン(2008年9月4日現在)を加え、37か国となりました。 国連のウェブサイトで、批准した国の名前を紹介しており、中国もオリンピック開催直前の8月1日に批准しています。 批准国の拡大は障害者の権利保障を国家として推進する決意の広がりとして注目されます。 我が日本の国会も権能を発揮し一日も早く批准すべきです。政府は、外務省(総合外交政策局人権人道課長)を主任とし、内閣府(政策統括官付参事官)を副主任として、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省で構成する「障害者権利条約にかかわる対応推進チーム」がすでに活動を開始しています。 今後、同チームを中心に、関連する法律の改正などを論議し、早期の批准をめざす考えのようです。 また、立法府としては、超党派的な協力体系として「国連障害者の権利条約推進議員連盟」が活動を開始しています。さらに、厚生労働省(職業安定局高齢・障害者雇用対策部)において「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」が公開で開催されており、条約批准に向けた取り組みが進んでいるなか、課題が山積しています(以下、条約と表記する)。 |
|
| 具体例で考えてみよう | |
先ず、条約の批准は当然ですが、政府にいま求められているのは、ただ単に批准さえすれば良いとする態度ではなく、障害者の権利保障をうたった条約に違反するような法律や政令、条例などを早急に分析、点検、整備を誠実に行なうことです。 それを監視することが障害当事者及び当事者団体の重要な課題であり責務です。 次に、障害のある私たちが障害の種別・団体をこえ連帯した条約実施過程に参加する運動を進めて行くことが必要です。 条約第4条3項によれば、「締約国は、この条約を実施するための法令及び政策を策定し及び実施するに当たり、並びに障害のある人と関連する問題についての他の意思決定過程において、障害のある人(障害のある子どもを含む。)を代表する団体を通じて、障害のある人と緊密に協議し、かつ、障害のある人を積極的に関与させる。」(川島聡=長瀬修仮訳2008年5月30日付より引用)、とあり、締約(批准)国への「一般的義務」が規定されています。 さらに、条約作成段階に障害のある世界の仲間たちが、「私たち抜きに、私たちのことを決めないで!」(Nothing about us, without us !)を、合言葉に働きかけを続けて障害当事者の視点で条約を創り上げてきたことを思い起こし、この根拠条文を「てこ」として積極的に条約実施過程に関わることが肝要だと考えます。 |
|
| インクルージョンとは何か | |
ここで、本条約の大切な原則の一つであるインクルージョン(inclusion)「包含」を第3条「一般原則条項」から見てみます。「社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン」が規定されていますが定義そのものは示されていません。しかし、反対語のイクスクルージョン(exclusion)「排除」と対比させてみると良く分かります。つまり、障害のある人を排除してきた社会が障害のある人を排除せずにそのまま受け入れ、包み込むという意味です。 障害のある私たちからすれば、私たちが変わるのではなく、社会の側が変わることを求めていることが分かります。「排除(イクスクルージョン)から包含(インクルージョン)へ」また「保護の客体から権利の主体へ」の変換。 そういった意味でもこの条約の大切な原則だといえるのです。「教育条項」第24条のキーワードである、「インクルージョン」と「インクルーシブ」も同じ原則であると思います。 インクルーシブ教育については次回に触れます。(つづく) 参考文献「東俊裕・監、DPI日本会議・編『障害者の権利条約でこう変わる Q&A』解放出版社、長瀬修・東俊裕・川島聡・編『障害者の権利条約と日本―概要と展望』生活書院、『NHK社会福祉セミナー(2008年7月〜9月号)』日本放送出版協会」。 |
| (その7) 2008年12月 | |
| インクルーシブ教育とは | |
インクルーシブ教育(inclusive education)とは、学校教育の現場、特に初等教育や中等教育段階において、障害のある子供が大半の時間を障害のない子供と普通学級で共に包括的な教育を受けることです。前回、インクルージョン(inclusion)の意味を、反対名詞のイクスクルージョン(exclusion)と対比させて、障害のある人を排除してきた社会が障害のある人を排除せずにそのまま含み込み受け入れるという意味だと解釈しました。続いて、条約は、障害のある人が生涯を通して自己の住む地域社会で分け隔てられることなく、教育を受けることができることをインクルーシブな教育制度として保障しています。それは、条文の文言を読むとき文理解釈することで分かると思います。 条文の第24条「教育」を見てみます。1項に、「締約国は、教育についての障害のある人の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしにかつ機会の平等を基礎として実現するため、あらゆる段階におけるインクルーシブな教育制度及び生涯学習であって、次のことを目的とするものを確保する。」(川島聡=長瀬修仮訳・2008年5月30日付)とあります。このように、「インクルーシブな教育制度」をはっきりと保障していることが読み取れます。 ところが、条約署名のため外務省の出した条文の「仮訳文」と比較して見ると。第24条1項は、「締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とするあらゆる段階における障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。」とあり、「インクルーシブ」の文言が、「包容」と訳されていることが何か釈然としません。この訳文は教育関係者を始めとし、多方面から政府官僚お得意の「永田町用語」ではないかと指摘されています。辞書で「包容」を調べると、「(1)包み込むこと。包み入れること。(2)心が大きく、他人や他人の意見を受け入れること。」(『大辞林 第3版』)とあります。障害のある子供の側は包み入れられるかもしれないと期待しますが、受け入れる学校側(校長)に寛大な気持ち(心が大きく)ないと、受け入れてはもらえないことになるのではないかと危惧の念が出てきます。昨今の教育現場、特に、普通学級では、障害のある子供を寛大な気持ちで受け入れる「ゆとり」がなくなっているように感じられます。 |
|
| 教育現場の状況は | |
| 2007年4月から、特別支援教育が「学校教育法」に位置づけられました。障害の種類や程度に応じ特別な場(盲学校、聾学校、養護学校)で教育するこれまでの特殊教育から、「LD(学習障害)、AD/HD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症なども含めた、障害のある子供の教育的ニーズに応じた特別支援教育へ移行することによって、すべての総合支援学校であらゆる障害に対応すること」が、本来の目的です。 しかし、特殊教育から特別支援教育へ名称を変更しただけで、教育現場では相変わらず障害を個人的レベル(医学モデル)のものと捉え、自己努力とリハビリテーションによって克服することにこだわっているようです。 また、特別支援教育と同時に進められてきた格差や競争を促す教育改革によって、障害のある子供が普通学級で学びにくい状況が生まれています。障害のある人が、障害があることによって差別されることのない共生社会(社会モデル)をつくるには、初等・中等教育という人生の入り口で、障害のない子供たちと、障害ある子供たちが「共に学び育つ」ことが不可欠です。 かたくなに「分離教育」を主張してきた学校側や、教育現場を「インクルーシブな教育」に変えるためには、一刻も速い条約の批准が必要です。 条約の批准に向け教育分野の法律や政令、条例などを改正・修正することが「焦眉の急」だと考えます。(つづく) 参考文献「東俊裕・監、DPI日本会議・編『障害者の権利条約でこう変わる Q&A』解放出版社、長瀬修・東俊裕・川島聡・編『障害者の権利条約と日本―概要と展望』生活書院、『NHK社会福祉セミナー(2008年7月〜9月号)』日本放送出版協会、松村明・編『大辞林』(第3版)三省堂」。 |
| (その8) 2009年1月 | |
| 批准国44カ国までの過程 | |
| 2008年12月15日現在、スウェーデンが選択議定書と共に批准したことにより、「障害者権利条約」の批准国は44カ国(選択議定書を共に批准した国は26カ国)になりました。この発表を受けて採択からの経過を、再確認して見ましょう。 障害者権利条約が2006年12月13日の第61回国連総会において全会一致で採択され活動の舞台はいよいよ国連の場から日本国内へと移って来たのです。2007年3月30日には署名が開放され、日本政府は2007年9月28日に115番目の署名国となりました。これによって条約の制度趣旨と目的を尊重しなければならない「国際法上の義務」が日本政府に生じたのです。 2008年4月3日、エクアドルが批准したことで、効力発生要件である合計20カ国の批准を満たして、1カ月後の5月3日に同条約が発効しました。 批准国は、条約の実施を義務付けられることになり、差別をなくし、教育や雇用など、あらゆる分野で障害のある人に障害のない人と同等の権利を保障する義務を負います。 権利条約の国際的な実施のための「障害者権利委員会」も設置されました。条約採択までの過程に世界の多くの障害のある人や障害者団体・関係者団体が参加し、障害者運動の成果が随所に盛り込まれています。本条約をどのように行使するのか、法解釈論と立法論、そして政策論にまで及ぶ条約実施過程において、私たちの「法的思考力」が問われる時が来たといえます。 |
|
| 権利条約の淵源を問う | |
| 21世紀は、「人権の世紀」と呼ばれています。昨年は、「世界人権宣言」が1948年12月10日、第3回国際連合総会において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、採択されて60周年を迎えた節目の年でした。今世紀最初の人権条約である「障害者権利条約」が発効した年と重なるとは、眼に見えない何か大きな力を感じます。世界人権宣言の第7条には、「すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。」とあります。正に、障害者権利条約の淵源だといえるでしょう。 この、世界人権宣言と国際人権規約に基づき、すべての人間の固有の尊厳、平等、権利を保障すべきであることが、世界の自由、正義及び平和の基礎を成すものであり、世界はそれを明らかに宣言し本条約に合意したのです。 |
|
| 条約の目的と基本法見直し | |
| 条約第1条の「目的」は、人権保障の国際的合意点を示しているといえます。 前段では、すべての人に保障されるべき、普遍的な人権と基本的自由を、障害のある人に対して差別なく完全かつ平等に享有することを提起しています(非差別・平等)。すべての分野において、「障害にもとづく差別」を禁止し、固有の尊重を促進するために、批准国が適切な行動をとることが義務付けられています。 後段では、「障害」や「障害のある人」を、体のどこかに機能障害「インペアメント」があり、そのことと社会の障壁との相互作用によって、社会参加に制約を受ける人を障害のある人なのだという考え方、つまり障害は個人ではなく社会にあるとする社会モデルを明確に規定しています。 わが国の障害者関係の各種実定法の基本的な根拠になっている「障害者基本法」における、障害の定義より広くなっています。 その、障害者基本法も本年2009年6月に見直しを控えており、権利条約に基づく国内法整備が本格的な段階を迎えています。条約との関連で、具体的権利性(裁判規範性)を伴う実体法としての「障害者差別禁止法」の制定や「障害の定義」などの見直しが検討されているところです。 (つづく) 参考文献「東俊裕・監、 DPI日本会議・編『障害者の権利条約でこう変わる Q&A』解放出版社、長瀬修・東俊裕・川島聡・編『障害者の権利条約と日本―概要と展望』生活書院、編集代表・奥脇直也『国際条約集 2008年版』有斐閣」。 |