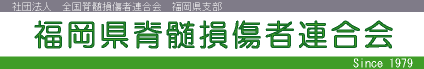

![]() 研修会
研修会
![]() 日時 2002年7月26日(金) 13時〜17時迄
日時 2002年7月26日(金) 13時〜17時迄
場所 春日市 クローバープラザ
内容 第1回文章講座
講師 B大学文学部人間関係学科 A教授
内容 出前講座の進め方
講師 福岡県脊髄損傷者連合会 事務局長 大里 恵
内容 第1回問題提起・話し方について
講師 福岡県脊髄損傷者連合会 顧問 織田 晋平
主催 社団法人・全国脊髄損傷者連合会
九州ブロック連絡協議会
 7月26日(金)午後1時より春日市のクロバープラザにて、社団法人・全脊連九州ブロック連絡協議会の文章の書き方・話し方(講演)・出前講座の進め方について研修会がありました。
7月26日(金)午後1時より春日市のクロバープラザにて、社団法人・全脊連九州ブロック連絡協議会の文章の書き方・話し方(講演)・出前講座の進め方について研修会がありました。
私は予てからこういった内容の研修会があったら是非参加したいと思っていましたので、同じ支部の早原さんと一緒に張り切って出かけました。
まず最初に文章講座で、文章を書くとは・書き方の技術的注意点・文章の構成・その他の留意点を、別府大学文学部人間関係学科のA先生に教えていただきました。
文章を書くとは、問題を自ら引き受けること、問題そのものが何であるかを解明し、深めることが大切で、いたずらに回答を求めたり、知ったかぶりをしない。文章を書く時は、あまり気負わず、事実を淡々と分かりやすく書く、文章を書く習慣を身に付ける、など簡単なようですが、実際にはなかなか難しい内容でした。技術的な事では原稿用紙で書く時やワープロ・パソコンを使う時の決まり事など、昔々学校で習ったのにすっかり忘れてしまった事から全く知らなかった禁則処理というものまで、詳しく説明していただきました。
文章講座全体の資料として、私達が毎日目にしている新聞の社説を参考に、分かりやすい文章とはどういうものなのかを皆で考えました。A先生のお話はとても楽しく、時には辛口なコメントもあって時間の経つのも忘れて聞き入りました。
次に大里事務局長が出前講座の進め方(大里流講演の進め方)についてお話をされました。大里事務局長は私達筑豊支部の支部長でもありますので、何回か出前講座にご一緒したことがあります。最近は出前講座の中で、手作りの紙芝居(私たちにもできること)をされていて、絵、内容もさることながら、大里事務局長の紙芝居をされる時の語り口に惹きつけられ、子どもたちも紙芝居を始めると真剣な顔で観ています。もちろん私もその紙芝居の大ファンです。各支部、各個人それぞれが趣向をこらすなどして、魅力ある出前講座を展開して行きたいと思いました。
最後に織田顧問が話し方についての講義をしてくださいました。私にとって織田顧問の文章は、大変難しく、お話も同じように難しいのだろうなと思い込んでいたのですが、全く違っていました。長年の活動経験に基づく豊富な知識で、話す(講演)時の心構え・常識的なこと・技術的なことをひとつひとつ丁寧にを教えていただきました。もう一つ問題提起で、「障害者の福祉ってなんだろう」ということを話していただきましたが、こちらはちょっと難しく、時間も足らなかったので、当日の資料と後日いただいた資料で、私なりに考えています。機会があったらこのことをもっと時間をかけて皆で勉強できたらと思います。
私がこの研修会に参加しようと思ったのは、地域の中で福祉活動をしていくうちに、自分自身の考えをもっと分かりやすく表現したいと思ったからです。
私は、人に教えるという事を専門にしてきたわけではないのに、車イス利用者というだけで、これといった知識も技術も経験も無く子どもたちに教えることは(教えるという表現は適切ではないかも知れませんが)とても難しく、限界があるように感じていました。専門家でなければ出来ないと言うわけではありませんが、福祉活動・出前講座などをする以上、ある程度の基本的なことは知識として持っておきたいと考えたからです。
私達一人一人が地域で福祉活動をする際に、自信を持って出来るようになるためには定期的に会員同士で学びあったり、情報を交換したりすることで、力をつけていけるのではないかと思います。そういった意味で、今回の研修会は、私にとって大変意義のあるものでした。
遠方から研修会の講師として来ていただきましたA先生をはじめ、福脊連の役員の皆様に、学ぶという楽しさを思い起こさせていただき、心からお礼を申し上げます。
ありがとうがざいました。(下川 厚子)
(広報誌「わだち」No.114より)
![]() 研修会
研修会
![]() 日時 2003年3月28日(金) 13時〜17時迄
日時 2003年3月28日(金) 13時〜17時迄
場所 春日市 クローバープラザ
内容 第2回文章講座
講師 B大学文学部人間関係学科 A教授
内容 第2回問題提起・話し方について
講師 福岡県脊髄損傷者連合会 顧問 織田 晋平
主催 社団法人・全国脊髄損傷者連合会
九州ブロック連絡協議会
3月28日(金)午後1時より春日市のクローバープラザにて、B大学のA教授を講師に第2回目の文章講座の研修会がありました。
 私は、前回受講された下川さんや早原さん達から「とてもいい講義だったよ」との話を聞き、今回は是非、私も「苦手な文章が上手く書けるようになれたらいいなぁ」と思い研修に参加させてもらうことにしました。藤田さんと一緒に直方社協の移動送迎支援事業のリフトカーで、クローバープラザへ、以前仕事で来た事もあり、なんだか懐かしい思い出と福脊連に入会して日も浅く何も分からない私ですが、皆さんとお会い出来るのを楽しみに来ました。
私は、前回受講された下川さんや早原さん達から「とてもいい講義だったよ」との話を聞き、今回は是非、私も「苦手な文章が上手く書けるようになれたらいいなぁ」と思い研修に参加させてもらうことにしました。藤田さんと一緒に直方社協の移動送迎支援事業のリフトカーで、クローバープラザへ、以前仕事で来た事もあり、なんだか懐かしい思い出と福脊連に入会して日も浅く何も分からない私ですが、皆さんとお会い出来るのを楽しみに来ました。
最初に、A先生の講義で「文は人なり」とは、文章を書いた人の性格や教養、その時の気分が表れ、文は短く簡潔に、修飾語、接続詞はできるだけ使わず、事実を淡々と書き、段落ごとに文章をまとめ、「である」調「です、ます」調を混入せず、主語、述語は正確に、名文をまねたり「文章を書くとは」発見や驚き、疑問や感動を記録し、人に伝えることが大切であると教えていただきました。
 先生は、ユーモアを交えながら、とても分かり易く説明をして下さり、私は驚きと感嘆で、先生の話に魅了されていました。一言では、簡単に見える文章も実に奥が深く難しいものだと実感し、新たな気持ちにさせて頂き、良い勉強となりました。
先生は、ユーモアを交えながら、とても分かり易く説明をして下さり、私は驚きと感嘆で、先生の話に魅了されていました。一言では、簡単に見える文章も実に奥が深く難しいものだと実感し、新たな気持ちにさせて頂き、良い勉強となりました。
次に、織田理事の書かれた資料を添削事例に使い技術的なことや注意点など教わりました。私は「わだち」を通じて織田さんの報告書を読み、長年の経験と幅広い知識を生かした会報誌は内容も充実し素晴しいものだと感銘しています。
最後に、良い文章とは、自分にしか書けないことを、誰が読んでも分かるようにかく。悪い文章とは、誰でも書けることを、自分にしか分からないように書く。この言葉が、活字嫌いの私に重くのしかかる中で、今、感想文を書いています。これを機に、あるがままの自分を表現出来るようになれたらと思っています。障害者福祉についても、これから研修会や仲間同士の交流を通じて共に学び視野を広げて行きたいです。
福脊連の役員のみなさまのお陰でA先生の有意義な講義を楽しく学ぶ事ができ、厚くお礼申し上げます。
ありがとうございました。(東房 晶子)
(広報誌「わだち」No.118より)
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」