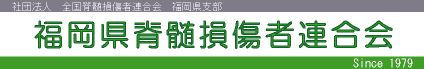
![]() 在宅勤務障害者の権利保障を望む
在宅勤務障害者の権利保障を望む
文化体育部長 久保 親志
私たち障害者の雇用や就労を取り巻く現状は、最近の景気後退に伴い、大変厳しいものがあります。総務省が8月28日に発表した7月の労働調査(速報)によると完全失業率は前月を0.1ポイント上回って5.0%となり過去最悪となりました。完全失業者数は330万人を数えます。更に追い討ちをかけるように、業績の苦しい大手電機メーカーが軒並みに合理化の名のもとに、大規模な人員削減を打ち出しています。
正に”聖域なき構造改革”の嵐が吹き荒ぶ真っ只中にあって、障害者の一般就労の根幹が揺らいでいます。そこで、今回は障害者の在宅就労(勤務)の現状と課題を検証してみました。
近年、IT(情報通信技術)の発展や産業構造の転換により正社員にこだわらずパートや派遣労働など、就労形態が多様化しています。そのような社会の潮流の中で、企業、障害者ともに、在宅勤務や業務委託・請負等に対する関心が強まってきているようです。
特に、移動や交通アクセスに制約を受ける車いす利用者にとって、仕事の範囲と機会を拡大する可能性を有するものとして、在宅勤務方式の評価は高まっています。
在宅勤務とは「労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ自己の住所又は居所において勤務すること」をいいます。(在宅勤務障害者雇用管理マニュアル:日本勤務障害者雇用促進協会より)
最近は、先ほども述べましたようにITの発展により、自宅に情報通信機器を導入して仕事をする形態が増加しています。しかし在宅勤務をめぐる紛争も増加していることも事実です。具体的には、パソコン技術を活用し、文書入力やプログラム作成等の業務委託契約を結び仕事を完成させたが、代金支払いが遅れたり、値切られたりするケースです。
これは、取引上の優越的地位を濫用した不公正な取引行為や違反、業務委託契約の不履行等に当たります。分かりやすく言えば、弱い立場の在宅勤労障害者の労働力や技術力の買い叩きや契約違反です。このような行為は、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法で禁止されています。
また、一部の不心得な事業主のために在宅勤務方式の芽が摘まれることは、個人、企業、社会のそれぞれの損失だと思います。
そこで、厚生労働省は障害者の在宅勤務等をめぐる様々なトラブルを未然に防ぐための、法や制度の整備を急ぐべきです。更に、福祉と労働の連携を図り、働く障害者の生活権と労働権を保障すると共に、劣悪な障害者の職場環境と労働条件を改善する筋道を立てて欲しいと切望します。
”障害者を納税者に”これが私の願いです。
(広報誌「わだち」No.108より)
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」