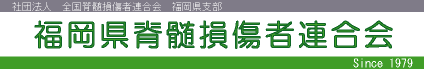

![]() 役員紹介
役員紹介 ![]() 平成15年(2003年)度事業報告
平成15年(2003年)度事業報告 ![]() 会則
会則 ![]() 入会のご案内
入会のご案内
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 当会結成から22年間の歩み
当会結成から22年間の歩み
![]() 全国脊髄損傷者連合会の40年・九州ブロック25年の活動の総括
全国脊髄損傷者連合会の40年・九州ブロック25年の活動の総括
![]()
![]()
当会は、労働災害、交通事故、スポーツ事故、または疾病等で障害をもつ県内の居住者で組織されている団体です。
会員の殆どが車いす利用者でありますので、1979年4月の結成以来、当事者団体として障害者自身の地域における自立生活と社会参加をめざして、
1、福祉の充実を図るために関係機関への働きかけ・福祉施策の提言。
それは、生活全般に係る医療、介護、教育、雇用、住環境、交通機関等の条件
整備について取り組んでいます。
2、とりわけ、行動(移動)の保障という、住環境、交通機関の整備にかかる「福
祉のまちづくり条例」化について促進し、福岡県、福岡市については、本年4
月より条例は実施されているところです。
3、会の主な活動は、
(1)相談事業・・・日常生活全般、諸福祉制度、住宅、雇用、介護、法的問題
等々についてピアサポート致します。
(2)情報の提供・・福祉に関する情報全般
会員には全国「脊損二ュース」毎月発行
当会の広報紙「わ だ ち」年6回発行
Oインターネット・ホームページによる情報の収拾と情報提供
O研修会、セミナー等の開催
(3)出前福祉講座の推進・・・小中高学校・公民館へ出向いて、車いす体験講
座、福祉、障害者問題についての講話を進めて
います。
(4)グループホーム建設・・・介護体制を前提としたホーム建設に取りくみま
す。ただ、住むだけではなく地域のコミニティ
化(活動場)図ることも検討しています。
(5)会員の会費は月600円です。無収入の方には減免制度があります。
(6)わだちの講読会員制度もあります。当会の活動支援、及び福祉活動へ
の参加という意味です。会費は年間3,000円です。
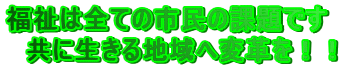
![]() 基 調 報 告
基 調 報 告
(社)全国脊髄損傷者連合会 理事(九州ブロック担当) 織田 晋平
行政改革・社会福祉基礎構造改革、それは、「三位一体の改革(骨太方針2003年)」といわれている。その内容とは、これまで、地方財源である、国庫補助負担金の義務教育費国庫負担金の全額廃止、児童保護費負担金(市町村分)の全額廃止となり、代わりに税金移譲(所得税等)・地方交付税等を組み替えて、具体的にどうように地方財源が確立するのかであるが、あるシミュレーションによると、「東京都のみが地方交付税の不交付団体だから交付税削減の影響を受けずに財源移譲による歳入増の恩恵を受けることになり、人口規模の小さい県ほど減少額が大きな傾向になるという。・・中略・・・地方財政の大幅な圧縮は、自治体の行政改革を急速に促進する。2004年度予算において各自治体は基金の取り崩しなどでかろうじて乗り切れたとしても、翌年度には基金が底をつき、予算が組めない自治体が続出するであろう。その結果、住民サービスの低下が不可避となるであろう。とくに、地方交付税の激変が一般行政サービスに及ぼす影響は予想を遥かに超える可能性がある。・・中略・・・一般財源化を契機として民営化の動きが加速する可能性が高い。しかし、住民合意のない公共サービスの民営化は、サービス水準の低下としてしか住民の目には映らないであろう。さらに、このような住民サービスの低下が不均等に進めば、地域格差が拡大することになる。」(世界4月号・「三位一体の改革」の実相を問う・平岡和久・森啓之著より抜粋)
これら事象は、推測ではなくすでに始まっている。ひとつは、支援費制度を介護保険へ統合する問題である。これらは財源上の問題として、各自治体や障害者団体に脅迫的(真理)姿勢で迫っていることは周知のとおりである。介護保険へ統合し20歳からの保険料徴収は、福祉財源の確保という戦略的なプログラムであり、「自己決定=選択と契約(権利性)」という謳い文句も実は「保険制度」という「保険料を条件とする給付」であり「負担なき受益を排除する」という排除原理をもっていることに注意しなければならい。つまり、社会保障という原理を排除するものである。現に、年金・医療・介護等において低所得者が必要とする「事案」から脱落する事態が生じている。
各社会福祉制度が「保険方式」を前提とし、その行く末は、「市場原理主義(競争と効率性=利潤追求)にさらされ、「公共の福祉」は、近い将来、商品としてのサービスとなる要素を孕んで加速していると思える。
政府の「総合規制改革会議」は、「社会システム全体の変革」の重要性を強調し、「規制改革・規制緩和=民営化」に基軸を置き、2001年から議論を進めている。ところが、本年から同会議は、「規制改革・民営開放推進会議」と、名称を変えて前改革会議を引き継ぎ、その課題を進めるだろう。こうした規制改革の流れに、どのように抗して、あるべき「社会保障」を求めるのか我々の課題である。
いまひとつは、どういう時代に生きているかという「生の所在」の認識である。ここに紹介するのは、イタリアの高校生に「今の豊かな生活は石油に依存している。もし今の生活を保ちたかったら、石油を確保するために戦争も止むを得ない」という意見があるけれども君はどう思う。との、質問にイタリアのマリオ15歳の高校生の考えは『もし本当に平和を望むっていうなら、僕たちが今の水準で生活していることや、他の人たちは病気に苦しみながら貧しい中で暮らしているのに、僕たちは日に3度の食事をしていて何でも持っているなんてことは考えられない。石油なしに僕たちの生活レベルは保っていけないことは事実だと思う。だから少しずつ落としていかなけりゃならないし、そうしないといつでもテロみたいなことが起こって、それに西側は戦争で応えるなんてことになってしまう。貧しい国を助けるためには、僕たちの豊かさのレベルさげなきゃ。皆が同じ生活水準にならなくちゃ平和はやってこない』
『私達は資源を際限なく搾り取っています。必要不可欠なものだけを使うことを学ぶ必要があります。私達は誰も経済的に不便で苦しい生活を知らないけれど、生活スタイルを変えていくことは私達の義務だとおもいます。(ジューリア16歳)』・『テロリズムは何か人の心の中にあるものでしょ。戦争でテロリズムと闘うなんてできないわ。戦争では人間を変えられないし、恐怖を与えることはできても、考え方を変えることができません。テロリズムは人間のメンタリティを少しずつ変えていく中で根絶するもので、このことを、他人についていくのではなく自分のアタマで考え、自分で分かっていって初めてできることだと思います。(マルゲリータ16歳)』(世界3月号・平和運動の中で自らを育むイタリアの若者達より抜粋)
イタリアの高校生が自由に「自分の考えを闘わす環境」があり、たとえ異論・反論を闘わしても、議論が終われば「一緒に遊び、日常のように反戦デモに参加する」という。これを読んで、自分も含めて、日本の若者や大人について考えてみた。「我々はどういう時代に生きているのか。」そして、「どのように生きているのか。」・「何を考えて生きているのか。」と、会員の皆さんにも、これらについて考えてみる機会をもつことを提起し、基調報告とします。
(平成16年福脊連総会・議案書より)
![]() 基 調 報 告
基 調 報 告
(社)全国脊髄損傷者連合会理事・九州ブロック連絡協議会会長 織田 晋平
はじめに
世界一の軍事力、新型大量破壊兵器を駆使し、イラク制圧すための米国の「おろかな戦争」が始まった。すでに、子供をはじめとする民衆への犠牲が報じられている。我々は、イラクから遠く離れていて戦争との緊迫感がない。戦況を現場から伝えるニュースを、日常の出来事のように、またはドラマを見るように、食事をしながら「戦争」を見ている。その自分(存在)に問う、人として何もしないでいいのか?ふがいなさ、もどかしさ、いやおうなしに戦争(国の対応で)に荷担している自分がいる。否、反戦を掲げ、私は非国民として主張と行動をしていこう。
イラク国民に及ぼす多くの犠牲と国土破壊も苦痛であるが、ブッシュの戦争の理由が、そもそもの大問題です。米主導の一極主義の考えと、それを成し遂げるための軍事力・暴力的に制圧するとい考え方とその方法(戦争行為)を「正義=善」とするところです。
イラクへの戦争が、世界的に何を及ぼすのか?我々に何をもたらすのか?その多大な影響は述べるまでもないでしょう。
福祉の行方
医療保険、年金制度、介護保険や四月から始まった支援費制度も国の財政破綻した上に乗っかっています。従って、制度上も再編が不可欠です。しかし、その改革は政治上の混迷と経済の立てなしが進まない中、先行きは益々不透明です。明らかなのは、財政破綻の「つけ」を福祉施策の中で、国民から吸い上げる「自己負担増=税金」の政策は強化されていくでしょう。
イラクへの戦争は、戦費、戦後復興への支援費等の負担が避けられません。戦争は、経済負担のみではなく、世界の政治・経済へ膨大影響を及ぼし、かってない政治、経済危機に向かうのでないかと危惧されます。これらは、我々の生活にも多大な影響を及ぼし、真っ先に生活そのものを後退させる、政策に突き進むでしょう。
従って、これからの会の活動は、会員ひとり一人が如何に自分の生活を確立していくのかで、それは、社会保障(補償)である、法律、福祉制度やサービスを適切に「使う=行使」ことで、生活基盤を整えることです。その権利行使するための「社会的生活力」を身につけることが、重要で、現実に差し迫る課題となることを提起し、基調報告とします。
(平成15年福脊連総会・議案書より)
![]() 基 調 報 告
基 調 報 告
(社)全脊連理事・九脊連会長 織田 晋平
昨年の基調報告で、現在進行中の「社会福祉基礎構造改革」に対してどのように対処していくべきなのか。それらに対処するには、一人一人の「自己責任」問われてくること。従って、如何に個々の会員の「生活力」を高めていくのか。そして、会としての「組織的」力とは何か。その基盤をどのように整備すべきなのかについて問題提起をしています。
また、5月の九州ブロック熊本大会においては、全脊連の40年の総括について提起しました。要約しますと、全脊連の結成1959年(昭和34年)〜1974年(昭和49年)までの「労働者災害補償保険法(以下労災と言う)の制定にかかる、被災者サイドからの補償要求と1965年代(昭和40年)からは生活圏拡大要求活動に推移し、この時期が第一期の運動です。1975年(昭和50年)〜2000年までが第二期の運動です。75年代は、自動車社会という時代にのり、改造自動車の普及が移動を可能にし、当会の活動も全国の各県に支部が結成され、各ブロック大会が開催されて行き、運動も全国的な展開となります。国の福祉政策が大きく進展する時代でもあります。
80年代になりますと「国際障害者年」の提起もあり、「障害」の位置付け(捉え方)や「障害」者当事者の市民的な権利としての社会への完全参加と平等の考え方が提起され、それまでの慈善や弱者救済という「考え方」を根本から問い直す機会となります。また、国際的な交流の機会も増加し、国内の障害者運動に大きな影響をもたらし、特に、90年のADA法(差別禁止法)は衝撃を与えます。国内においては、障害者基本法の改正、ハートビル法の制定、介護保険法、交通バリアフリー法制定と続き現在、社会福祉の基礎構造改革が進められているところです。が、これらが、福祉サービスの拡大に繋がるかどうかは分かりませんし、これからの課題です。一昨年から欠格条項の見直し、道路交通法の改正、昨年の11月には日弁連大会で「障害者差別禁止法制定」に向けたセミナーが開催され、各団体による「制定化」の動きが始まっています。この2000年までが第二期の運動と考えます。
第三期は2001年からですが、その障害者運動の軸足は、「社会的役割」を明確にし、具体的な活動を行うことです。そこで「社会的な役割」とは何かと言うことですが、端的にいいますと「与えられるから側・依存する姿勢」から脱却し、制度や立法、地方自治、福祉行政や事業等における役割を担う当事者して(共生する)主権者としての立場を確率することです。これが、市民としての『生活力』と考えます。以上が九州ブロック熊本大会での提起です。さらに、これかの運動を思考するにあたり、押さえておくべきことは
昨年、世界保険機構(WHO)提起している「障害」に関する国際分類の改定版を昨年11月に発行し、その翻訳本も近く出版されますが、その改訂版の中で注目すべきところは、「障害とハンディキャップという二つの用語の使いい方は近代障害史の視点から見られるべきである。1970年代には当時の用語法に対する強い反発が障害を持つ人の組織の代表と障害分野の専門職からあった。障害とハンデキャップは不明確で、混乱をもたらす形でしばしば使われ、政策形成と政治行動に不充分な役割しか果さなかった。用語は社会環境の不完全さと欠陥を無視した医学的・診断的手法を反映していた。」「1980年にWHOが、一層正確である同時に相対主義的アプローチを提案する損傷、障害、ハンディキャップ国際分類(ICIDH)を制定した。この分類は損傷、障害、ハンディキャップの明確な区別を行っている。ICIDHはリハビリテーション、教育、統計、政策、立法、人口学、社会学、経済学、分化人類学、などの分野で幅広く利用されている。国際分類にはそのハンディキャップの定義においてあまりに医学的で個人中心であり、社会の状況や期待と個人の能力との相互作用を適切に明らかにしていないという一部の利用者からの批判がある。こういった懸念や国際分類発表以来12年間に利用者から表明されてきた。他の懸念はきたる国際分類の改定で取り上げられる。」
追加加筆された部分・『2001年に採択した機能、障害、健康、の国際分類では、機能、と障害は個人的要素と(物理的、社会的、意識的、態度的など)環境的要素によって起きるという理解を示している。機能と障害は身体的、個人的、社会的レベルで分類されている。ICFは特定の個人の単純または、複雑な行動の遂行能力を分類する事に用いることができる。―中略― 個人の現在の環境における活動状況を分類するのに用いる事ができる。活動を容易にしている環境要因と妨げになっている要因を確認し、活動の成果を向上させるために適切な修正また処置を講ずることができる。』さらに、18節の追加は『ハンディキャップという言葉には、軽蔑的な、否定的な、屈辱的な意味が含まれるることがあり、細心の注意を払って使用すべきである。』と注意を促しています。
これらの考え方を基本にして、各国(30カ国)の「差別禁止法」の制定に裏打ちされてきていると言えます。国際的な「障害の考え方・捉え方」となっていることを前提にし、我々の立脚点との確認の上に、これからの活動の軸足と戦略を射程しければならないと考えます。その意味での「社会的な役割」を具体的にしなければならないということです。言換えれば、障害がある人、無い人も関係なく、同じく市民生活者としての等しく機会と社会的保障がなされる「社会の建設」について、提案、実践していくことが我々に与えられている課題と考えます。なぜなら、我々は、「障害」の有無の両方の生活体験を有する唯一の市民だからです。これらの「客観的」立場を生かさずして何をなすべき「人」かです。 以上を基調報告とします。
(平成14年福脊連総会・議案書より)