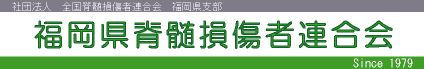
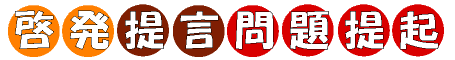
![]() 支援費支給制度
支援費支給制度
副会長・事務局長 大里 恵
これまで行政責任で行ってきた障害者福祉サービス(措置制度)が、2003年4月より支援費支給制度(契約制度)に変わります。つまり介護保険と同じように、行政が障害者福祉サービスにおける責任を放棄して、民間の事業者に託すということです。万が一トラブルなど発生しても、行政は一切タッチせず、利用者(障害者)と事業者の間で解決していかなければなりません。それが、支援費支給制度、契約制度の一つの問題点といえるでしょう。また、マスコミ等の扱いも介護保険のような扱いはせず、未だに制度化されることを知らない障害者もか少なくないはずです。そのことは、社会が障害者を軽視している証拠だと思わざるをえません。
ところで、ここからは支援費支給制度が導入にいたるまでの経緯と、今後私達障害者がどのように対応すればいいのかということを解説していきたいと思います。
第1章/導入にいたるまでの経緯
現在日本が抱えている財政赤字は600兆円とも700兆円ともいわれています。それはバブル以降の戦後最悪ともいわれる経済状況を読み切れず、相変わらず他国へ多額の援助を行い続け、狸しか通らない所に高速道路を引くといったような計画性のないお金の使い方をし続けた結果だといえるでしょう。その責任は政府与党とそのような政治を放任しきてた私達国民にあるといえます。
一方でその対策として、基礎構造改革(行財政改革)が着々と断行され、福祉分野においては社会福祉の基礎構造改革という形で、規制緩和を旗頭に、はじめに児童の分野で、次に高齢者の分野で介護保険が導入され、そして、今度は障害者の支援費支給制度(契約制度)が導入されることとなりました。
第2章/支援費支給制度導入により国が考える効果
まず、利用者と事業者は対等であるとしていますが、それは介護保険で実証済みであり、高齢者の中にはそれを実践している人もごく一部におられるようですが、大半の高齢者は事業者のいいなりであることは明白だといえます。
また、利用者が事業者を選択できるとありますが、先に述べた理由からもその可能性はわずかであり、障害者の場合、高齢者より参入する事業者が少く、選択できるといううたい文句は絵に描いた餅でしかないといえます。
第3章/未発表内容を含めた課題
1.現段階においては介護保険のような認定分けが何段階あるかは未発表となっていますが、今年の夏頃に発表されると思われます。(タイムスケジュール表参照)
2.利用者負担が増えることが将来的にあるかもしれません。そのことは、すでに介護保険においてもそのような動きがあるともいわれていますし、国や県市町村の財政状況を考えても遅かれ早かれ予測できることだといえます。
3.必要なサービスのみ提供される。このことはよい部分、悪い部分両方あるといえます。措置制度では障害程度に応じて、本人の能力はあまり考えられず一括してお金が支払われていました。しかし、支援費支給制度では、本当に必要なサービスのみを提供することになり、例えば1級の障害者でも、自分でトイレができる人、できない人という風に細かくチェックされ、その能力に応じて支援費が支払われます。そのことにより軽い人は極わずかな支援費しか支払われず、その一方で今まで重度の人は市町村の状況に応じたサービスしか受けられませんでしたが、サービスを提供できる事業者さえいれば今まで受けられなかったサービスも受けられることが可能となります。
4.家族の介護能力でサービス量が左右される。介護保険にはないシステムが採用される恐れがあります。在宅障害者の家庭における家族の介護能力を差し引いて、残りの足りない部分のみが支援費の対象とする恐れがあります。ある意味においてはそれが自立する切っ掛けにもなるかも知れませんが・・・。
5.一定水準は国が定め、上乗せは市町村独自で決める。ある程度のサービスレベルは国が定め、プラスαのサービスについては市町村が独自で予算を組みサービスを行う。介護保険の横だしのような感じだと思われますが、介護保険よりさらに市町村の裁量が大きいといえる制度です。そのことにより、地域格差の問題が新たな形で出てくる恐れがあります。支援費支給制度は広域サービスを基本とし、そのことによりサービスレベルの向上と地域格差をなくすことも目的の一つとなっているはずなのに、矛盾は否めません。
6.市町村障害者計画の中身によってサービス内容が変わることもある。前文と関連して、自分達が住んでいる市町村障害者計画の中身が充実していないと、支援費支給制度が導入されてもサービスが不十分ということが起こることが考えられます。
7.逓減制導入。在宅は1年ごとの見直し、施設は3年ごとの見直しが行われ、特に入所施設は立前上通過施設が原則であり、できるだけ施設を出て地域で暮らすことが理想となっています。つまり、3年経つと地域に送り出すということが前提となり、支援費も低くなるかもしれません。医療制度と同じように、ある程度を過ぎると、支援費の額が減るということも懸念されます。
8.苦情解決策が不十分。前段で取り上げた様々な問題点により、トラブルも多数発生することが予測されます。しかし、すでに行政は責任を放棄しているわけですから、苦情処理については一切タッチしません。今回の制度ではその苦情解決のシステムが全く確立されていません。
その他にも様々な問題を抱えた支援費支給制度ですが、タイムスケジュール表にあるように2003年4月に向けて、すでに予定上ではかなり動き出しているはずですが、末端の市町村の動きがあまり感じられないのがさらなる不安を募らせているといえます。
第4章/支援費支給制度によるサービス提供の流れ
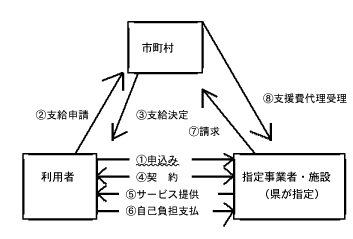
第5章 タイムスケジュール表
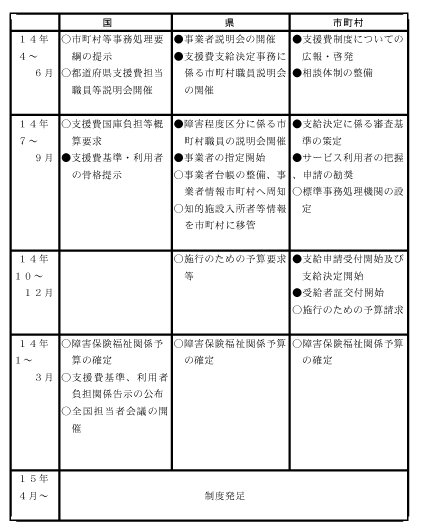
※●は重要
第6章 重要ポイント
※支援費支給制度になると、サービスを行う事業体が地域にいなければ支援費は発生しません。つまりサービスは受けられないのです。事実、県内の介護保険指定事業のうち支援費支給指定事業者に参入するのは約3分1程度(2002年2月現在調査)だそうです。また、現在障害者のホームヘルプサービスを行政から委託されている社会福祉協議会も、支援費支給制度になると、介護保険と同じ独立採算性となるので、事業から撤退するという所もあると聞いています。
※今後は、障害者支援センターを核として、地域において福祉サービス提供事業者の発掘や事業体の開発を死にものぐるいで行わないと、サービスが受けられない恐れがあるかも知れません。
※今回の制度で一点だけ救われるのは、今まで特定事業体の独占だった福祉サービスが小さな事業体でもサービスが可能となるところです。今後は当事者に寄り添った、よりきめ細かなサービスが提供できる小さな事業体の活躍が期待されます。
(広報誌「わだち」No.112より)
![]() 支援費支給制度(2)
支援費支給制度(2)
副会長・事務局長 大里 恵
この文章を書いている9月3日現在での、わかっている情報、行政の責任範囲でやらなければならないこと。更には、こうなるであろうから注意するようにという推測を書いてみたいと思います。
1.総論について
支援費制度は介護保険と同じようなうたい文句で、自己決定、自己選択を尊重し、事業者との対等な関係などと素晴らしい言葉が羅列してありますが、このことはすでに介護保険で実証済みです。同じ手口にだまされる障害者はいないと思います。
また、支援費制度になれば、サービス内容・量等が黙っていても充実すると思っている当事者や関係者がいるとすれば、それは間違っているといえます。そのことは、後で述べたいと思います。
2.申請からサービスを受けるまでの流れ
(1)申請
※利用したいサービス内容を申請書に書き込み、市町村に申請を行います。(10月頃から受け付け開始。ただし、町村によってまちまちである)
(2)申請の審査
※申請内容に関する審査が行われ、過去の利用状況などを見て、支給量など決定されます。
(3)受給者証の交付
※支援の種類・支給期間・支給量が明記されます。
(4)事業者と契約
※公的機関が発行するパンフレット等から、あるいは自分が知っている事業者と直接契約します。
(5)サービス開始
※事業者との契約の後、施設サービス(入所・通所)や、在宅サービス(身体介護・家事介護・外出介護)のサービスを受けることができます。
※サービス開始(15年4月1日からの予定)
3.申請が始まるまでに行政責任としてやるべきこと(当事者からの提言)
(1)行政の担当職員が、支援費制度を十分に理解する努力をすること。
(2)支援費制度を障害者や、その家族に周知してもらうための説明会や広報活動を徹底して行うこと。(県・市町村)
(3)利用者から申請(10月頃受付予定)があった場合、支援費制度の趣旨を十分に理解し、利用者の意向や生活環境などの聞き取りを経て、その内容を勘案し、支援費の支給量を決定するという支援費制度の趣旨を遵守すること。
(4)申請書に過去の利用状況を明記するようになっているが、今まで、在宅介護や外出介護を受けていないから。という理由で、安易に支援費の量をゼロとしないこと。利用者の意向を十分配慮すること。
4.現在までわかっていること
(1)今まで、ホームヘルパーを利用した際、同居家族がいる場合、家族の収入によって、利用料の負担が発生していました。しかし、支援費制度では、20歳以上の独身の障害者については、本人の収入(年金等は収入になりません)に応じて、負担が発生することになります。高収入の障害者以外は実質的に、利用料の負担金はゼロ円となり、サービスが利用しやすくなります。ただし、配偶者と子供が働いている場合は収入の対象者とみなされます。
(2)支援費の量の上限は設定されません。障害の状況に応じてサービス内容と支給量が決定されます。(県担当係長の回答)
※これにより、各市町村の担当者が勝手に、支給量を決定することはできないことになっています。また、不服のある場合は市町村に異議申し立てができます。
(3)通所・入所施設サービスの申請は16年3月31日までに、申請すればいいことになっています。
(4)通所施設サービスと、在宅サービスは併用できます。
(5)知的障害者は手帳がなくても申請可能です。
5.注意点
(1)自己申請制ですので、黙っていたらサービスを受けることはできません。自ら申請し、受給者証を発行してもらい、事業者と契約し、その後サービスを受けるという段取りになります。
(2)審査の際、過去の利用状況を重要視して、支援費の量を増さない担当者がいるはずですので、注意してください。
6.最後に
支援費制度の趣旨をよく理解していない市町村では、在宅障害者の生活状況は無視して、過去の実績、つまり、過去にホームヘルパーや外出介護(ガイドヘルパー)を使ったことがあるか。使ったとすればどれだけの時間か。などで支援費の量を決定するおそれがあります。
なぜ、そのような対応をするのかといえば、各市町村の財政は厳しい状況であり、利用者の意向に添って、今まで以上にサービス量を増やしていたら、財政を悪化させるからです。既に、そのような対応を考えている市町村がいくつかあるようです。そんな対応を考えている時点で、支援費制度の理念は、全く無意味となります。
今まで、必要なサービスを受けたくても、使い勝手が悪くて使えなかったり、制度(ガイドヘルパー制度)そのものがなかったりしました。そのような行政の怠慢はしらんぷりして、安易に利用状況だけを重要視するようであれば、支援費制度になっても、現状と何にも変わらないことになります。
支援費制度を使い勝手の良いものにするには、まず、私達障害当事者が支援費制度のことを学習し十分に理解することが大切です。そして、一番のポイントとなる申請と審査の際に、障害者が生きる上で最も大切な介護保障について、相手を納得させることができるかどうかだと思います。つまり、支援費制度の趣旨ともいえる、利用者の意向や生活環境などの聞き取りを経て、その内容を勘案し、支援費の支給量決定にあたる。となっていることを的確に担当者に伝えられるかどうか。また、過去の利用状況や制度がないことを理由に、支援費の種類や量を勝手に決められないようにできるかどうかだと思います。
以上のことを踏まえ、支援費制度になってもやはり黙っていたら、何も変わらないということです。つまり、支援費制度になっても、やはり自分のことは自分で道を切り開いていくしかないということです。その意味で、冒頭の半分正しく、半分間違っているということをいいたかったのです。「わだち」が発行される頃には、既に、申請の受付が始まっている市町村もあるかも知れませんので、行政の担当者と頑張って交渉してみてください。
(広報誌「わだち」No.114より)
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」