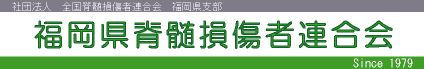
![]() 車イス使用者トイレ設計提案
車イス使用者トイレ設計提案
(現在時で再考)について
1.最低、各階に男女別に設置すること。
できれば、上記の他、一般トイレ男女のトイレの一番奥を多少広めにして使えるようにしておくこと。
(高速道路のSP・PAで採用をはじめた)
2.汚物洗い器の設置(病院等で使われている物より小さめでいい)。
3.汚物捨て器の設置、小さなゴミ入れではなく、足元に邪魔にならないように固定式で、捨て口が回転(足ふみではなく)するものがよい。
4.折たたみ式のベッドの設置。
5.便座に座ったままで手洗器(小)が必要。
6.洗面器の鏡の設置。ただし、鏡の設置は便座正面には設置しないこと。
7.介助が必要な人の場合には、介助者の待合の場が必要である。便座との間の仕切りが必要。
(介助者は用をたしているところにつっ立ている状況)
8.トイレのドアと便座の位置は直線にしないこと。開けた場合丸見えにならないようにすること。ドアの前は仕切りとなる壁などが必要。
9.管理面での衛生管理が重要(床の汚れ。濡れている場合が多々ある)。
10.手荷物をおく棚やフックの設置(できれば洗面器の横に・女性に不可欠)。
以上の設置は必須条件である。
また、現状の新たな問題として考慮すべきことは、1973年(㍼48年)「福祉のまちづくり推進運動」以降、障害者トイレ(車イス使用者の)設置の働きかけをへて増加したが、90年代以降は、「ノーマライゼイション・ユニバーサルデザイン」等の言葉の一人歩きで、そのトイレは「多目的化(誰でも使うという美辞麗句の基)」され変質をきたしているところである。これは、絶対数が少ない(男女兼用が多数である・一箇所)という実態であることと、需要(使い手の幅を拡大解釈)だけを煽った傾向に奔った経緯を再度検証すべきであること。幼児の授乳・オムツ交換・幼児のトイレ使用・高齢者の使用・オストメイト使用者・その他などの使用者の増加、これら需要者に対する対応(内容)は急務である。現状は、当会の車イス使用者が使用できない場合が増加している実態がある。従って、
1.上記提案事項の1項の提案を前提に施行を再考すること。
2.自己導尿者やオストメイト者らの増加があるので「専用性(これしか使えない)」が不可欠な要素があることの理解と周知化。
3.授乳・オムツ交換台・幼児、子供用トイレ等を別に設置すること。
できれば、一般トイレの中に親子トイレの設置を。
4.トイレの設置は、すべての市民への生活権の保障(行使)であることを、建築設計士から設主への啓発を促す(これは、単なる「対策」という、観点ではないことを理解してもらうこと)。
5.トイレに対するイメージ、発想の転換
①健康管理・維持の場所
②ひと休の場所
③不可欠の要素
2002年12月6日 九脊連・織田 晋平
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」