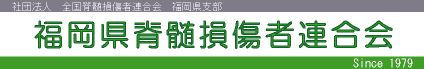
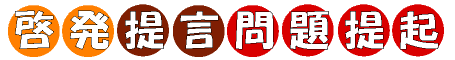
![]() 自動車事故対策センターの
自動車事故対策センターの
介護認定問題の対応について
九州ブロック理事 織田 晋平
○はじめに
昨年より、自動車事故対策センターの介護料支給制度が、給付対象者の範囲が改善され、会では新制度の内容を吟味し、問題点を明確にし、該当者への案内をしてきたところです。同時に、連合会本部に対して、介護認定に関する改善を求める交渉を事故対策センター中央本部(東京)と早急に進めるよう提起しました。本部は数回の交渉をし、国会でも審議されるよう働きかけ、その経緯は脊損ニュース(細野理事)で報告されている通りです。若干の改善はありますが、まだ不充分です。本制度の改善から一年を経過し、申請者の介護認定に関する問題が全国的に出てきていますので、先般の三重総会で配布した「申請における対応について」を議論の素材として提起します。
一、診断書の記述上の問題点
1.日常生活動作の「食事・排泄・体移動・衣服着脱・整体動作」などのチェック項目の問題点。
重度後遺障害診断書(脊髄損傷者用)
| ① 日 常 生 活 動 作 |
食事 | □全介助を要する □自助用具使用により可能 □自立 □その他( ) |
| 排泄 | □全介助を要する □手伝ってもらえれば可能 □自立 □その他( ) |
|
| 体移動 (ベッドから車イスへの移動) |
□全介助を要する □手伝ってもらえれば可能 □自立 □その他( ) |
|
| 衣服着脱 | □全介助を要する □手伝ってもらえれば可能 □自立 □その他( ) |
|
| 整容動作 (歯磨き 洗顔 洗髪など) |
□全介助を要する □手伝ってもらえれば可能 □自立 □その他( ) |
(1)①食事の「全介助を要する」とは、ひと箸ひと箸(あるいはスプーンで)食べさせる介助を、「全介助」との観方を差しているのであろう。が、②の「自助用具使用により可能」の場合は、自助具付けて食べている間は介助なしの、自力よるとの解釈(随時との解釈)であろう。しかし、自助用具を装着・脱着の介助が前後にあることと。すべての食材が「自助具」よって食べられるわけではないこと。例えば、コップや湯のみをもって飲むことはできないなどを考慮すれば、「全介助を要すると自助具使用により可能」の間には、介護者の介助時間と拘束力において、差異はなく、常時介護との認定(範囲)をすべきである。
強いていえば、自力で可能だという判断は、装具着脱においても介助を必要せず、自分で装具を着脱できる場合と考える。つまり、指先に多少握力がり、補助具を付けることによって、よりつかむ力(動作力)が加えられる場合などが考えられる。
※食に関して共通することは、食材の調達(買い物)・調理・配膳・賄い・あと片付けなどは全介護(介助)を要する。しかし、日常生活動作のチェック表にはこれらの項目がないので、別添付文書で主張しておくべきです。
(2)排泄の項については、排尿の処置について脊髄損傷の場合、失禁状態にある者は収尿器の装着脱と衛生面の処置などの介助が必要である。また、装着した収尿器の脱落、破損などで、尿水害(漏れて)に合い、身体の洗浄、消毒、着替えなど、突発的に起こる介助も少なくないのである。
80年代以降の受傷者の多くは「自己導尿」で排尿処置を行っている。この行為は「医療行為の範囲」となっているが、頸損者の場合は指が利かないので殆ど自力ではできないので、家族の介助によって行っている。前後の消毒処置が不可欠であり、日常的に頻繁に行うことが必要である。
排便処置についてはより複雑である。便を促す薬用の使用(下剤)、浣腸液の使用、摘便(脊損者は便秘がちになりやすい)などであるが、どれか一つの処置方法でやっていることではなく、併用も少なくない。また、排便は日時を決め定期的な排便となるが、失敗も多く、汚れた衣類の洗濯、身体の洗浄・消毒などの介助が頻繁に起こるのである。特に脊損の特性として「直腸障害」があるので、「下痢」を起こすことが多く、下痢状態に陥ると介助はその分頻度を増すので大変である。
排尿、排便処置は、すべての脊髄損傷者の「介護要件」でもある。
③体移動の項も、短にベッド上から車いすへの移動のチェックのみである。「寝返り・起き上がり」、が、できるかどうかのチェックがない。
④整容動作の項は、歯磨き、洗顔、洗髪などと在るが、清拭(身体を拭く)などのチェックがない。身体の清拭は「褥瘡」の予防としても不可欠である。(入浴回数が、少ない人ほど清拭は欠かせない。)
※以上の点なども注意して、介護の内容(実態)を主張して下さい。
二、事故センター案内文書の8項の※印にところに・・・・
「下記の症状を満たしている方は最重度と見とめます。」とあり・・・・
【脊髄損傷者の場合】
イ.自力移動が不可能である。
ロ.自力摂食が不可能である。
ハ.屎尿失禁状態にある。
ニ.人口介添呼吸が必要な状態である。
との記述があるが、診断書にはイ~ニの生活動作状態を記載する欄がない。
(1)特に、自力移動については「屋内・屋外」についての移動にかかる介助実態のチェックも欠落している。同じく入浴の介助や調理(後かたづけを含む)なども同様である。(従って、別に、日常の「介護実態」を記載し添付すべきである。(自賠責障害等級が証明できない自損事故の人の場合は特に注意する)
(2)従って、一の項で介護状態を説明したとおり、特に頸髄損傷者の場合は、上記のイロハに該当し、常時介護(最重度)のと認定すべきである。
以上のように、「介護実態」を明確に把握するには、医学的な機能障害・能力障害のみに重点を置いた認定をすべきではなく、「当たり前の生活」をするために、具体的な生活支援、社会参加活動などにおける、介助(介護)がどのように必要かという「視点」での「チェック表」の作成を再検討すべきである。ついては、WHOの「国際生活機能分類(ICF)」を基準にして、再検討を求める。
(3)本件の介護料給付は、労災補償保険法の「介護補償給付の支給基準」に準ずるとある。従って、障害等級認定については、労働省労働基準局補償課長の事務連絡・平成9年3月10日付、「介護(補償)給付に係る要介護障害程度区分の判定等にあたって留意事項について」において、『脊髄損傷とは、神経系統(中枢神経・末梢神経・自立神経)の損傷障害であるので、両下肢・四肢の機能に係る障害(部分)のみでの「障害認定」をすべきではないと、障害等級の見なおし』を通知していること注目して、再認識を求める。つまり、脊髄損傷とは中枢神経などの第一次損傷があり、その結果、四肢・下肢麻痺などの体幹機能不全・直腸障害・排尿排便機能障害・性能障害・痙性障害・痛恨障害などなどの第2次障害が生じる特有の損傷である。これらの障害が総体的に、如何に、「生活活動・社会活動参加行動」、などに関する際、「行動の阻害要因」を引き起こすのかである。その分析過程に不可欠な人的な支援要素(介護度)が明らかになる。
労働基準局の障害等級見直しは、機能障害の一部分を観(診)て認定していた監督署があったので、それらを上記観点から正したものである。その労災障害級一級の3号は、自賠責保険障害等級、一級の3号の認定(障害の内容)に準ずるものである。と、解釈する。
以上のような項目を検討、吟味した上で、あるいは申請に先立ち「相談会」を開き相互の意見交換(議論)の上、申請を進めることが、ケアマネジメント・セルフケアマネジメントであり、申請者(会員)の立場を強化(エンパワーメント)するものである。つまり、これらの総称としてのピア・サポート体制(相談)が会活動として機能していない。会員個々にも問題意識が希薄であるとの実態を露呈している。結果、常時であるべき状態の会員が「随時と認定」されているのである。常に、会員は制度の改革者としての視点を持つことが、会活動の基本である。
以上述べたことは、各種制度サービスを利用する、「介護保障(補償)」に関する共通する事案であり、個々個人が明確に自分の介護内容を主張(提言)する「説明能力」が求められるということです。従って、自分の介護内容・時間及び日常的な、「介護プログラム」を自分で作成し、それらを基に、自分に該当(法制度的に)する制度サービスを適切に利用するということですが、それは、サービス提供者との合意形成が前提です。または、理解を促す交渉力が問われると言うことです。(セルフケアマネジメント)
三.以上の問題点を参考に・・・・
本部・支部の取組みの提案
1)事故センターとの意見交換、介護認定の内容についての見解書の提出等。
2)申請者への『事前研修』の推進。サポートの強化。
3)認定者の申請書(データとして)のコピーの収集・分析。
4)認定の不服申立ての検討・研究(随時から常時への変更など)。
5)現時点(介護内容の基準が拡充されるまで)では、頸損者の申請を重点的に進めることの確認。
(広報誌「わだち」No.114より)
![]()
![]() 自動車事故対策センター御中
自動車事故対策センター御中
―申請書提出時に別紙で添付することー
事例文・・・日常生活動作の項の補足として「介護実態」
せきそん 花子(頸損)の介護について
【食事の項】
朝 ご飯を炊く(一日分)。味噌汁を作る。漬物や惣菜等の準備をする。お茶を用意する。
以上の物を食器に入れ、大きめの盆に並べ、ベッドのサイドテーブルにセッティングして自助具を装着させる。食後の後片付けなど、全てにおいて、介助が必要です。
昼 私(夫)は、会社から12時10分頃帰宅し、昨日の残り物や朝の残り物を 朝と同様にセッティングし、自助具を装着させて食べる。
注)朝と昼は、食事後の起立性低血圧(併発疾病)が重症の為、ベッド上での食事になるので全介助が必要です。
夜 午後から座位で体調を整え、夕食は食卓につき、朝食・昼食と同様のセッティングをして、自助具を装着させて食べる。食べるといっても、肉・魚・大きめの野菜等は、自分で細かくする事が出来ず、常に誰かの介助が必要です。
注)食事に関して共通することは、食材の調達(買い物)調理 配膳 後片付けなど 全面的な介助が必要です。自助具により可能な部分はほんの一部、特に汁物やお茶を飲むなど介助が必要で、食事に関しては、全面介助を要します。
【排泄の項】
膀胱・直腸機能障害の後遺障害の為、生活を困難にする最大の難題です。現在 排尿は一日四回(朝6時・昼12時・夕6時・夜11時)です。尿道にカテーテルを通して、全て夫の介助導尿です。しかし、導尿から導尿の間にはどうしても失禁があるので、オムツを使用しなければなりません。よって朝・昼・夕のオムツ交換の介助も必要です。
女性の介助導尿は、体の構造上手法が大変(技術)で、ベッドに仰向けに寝かせ、ズボン・下着を下ろし、足を開脚し、消毒し、カテーテルを尿道―膀胱に挿入し、排尿を促し、排尿後足を戻し、オムツ・下着・ズボンをはかせる。尿を捨て、カテーテルを洗浄し、消毒で終了。(消毒等、充分気を付けていても、いつも、常に、尿路感染症・膀胱炎におびやかされています。)
排便は、週二回、朝下剤を服用し、夜排便するようにリズムをとっています。しかし、感覚が全くない為、排便時は座薬使用、随時 摘便していますが、数時間後、軟便が出たり、翌日、失便したり、その都度仕事を中断し、帰宅して、オムツ交換や衣類交換やシーツ交換しないと、悪臭や,褥瘡(じょくそう)の危険にさらされます。
注)この排泄に関しては、時と場所を選ばない為、障害者本人、介護者共、身体的・精神的苦労・苦痛は、筆舌に尽くしがたいものです。
【体移動の項】
ベッドに仰向けの状態からは、寝返り・起き上がり等 一切出来ませんので、電動ベッドにて、ベッドと共に起き上がります。しばらく座位の体勢で体調を整え(食後は 起立性低血圧の為2時間位要する。)ベッドと車いすのすき間を埋めるボードをセットし、ずりながら後ろから引っ張ってもらい、車椅子に移動します。又、ベッド上では寝返り等できない為、枕3個を使い、体位を固定して就寝するので、ほとんど夜中に1度は体位を交換する介助が、欠かせません。
注)起立性低血圧とは、脊髄損傷に起因する併発疾病で、交感神経の麻痺のため急な座位したりすると、血液が麻痺域に移動し、急速に低血圧状態に陥ることがある。時には脳環境が貧血を起こし、立ちくらみ・貧血・失神したりするので、時間を掛けて座位をすることとなる。このような疾病によりベッド上での健康管理と維持・車いすへの移乗・移動にしても、常に介助が必要です。
【整容動作の項】
指がほとんど動かない為、洗顔・洗髪・入浴・洋服の脱着等全てにおいて介助が必要です。入浴については、天井走行リフターを設置して、行っていますが、体力的・時間的に見て週3回が限度です。しかし、常に清潔にしておかないと、褥瘡(じょくそう)の危険がある為、清拭の介助も欠かせません。
以上の他に、突発的な事柄が多様にわたって起こり、その都度いろんな介護が必要です。時として、仕事を中断したりする為、収入も減らされる現状です。それでも私一人では限度がある為、本人の姉、義妹、近所の友人数人とネットを張り、常に誰かがかけつけられる体勢をとっています。
また、私事(夫)ではありますが、10年余りの介護の蓄積もあり、腰痛が悪化し、平成13年1月に腰の手術をし、10ケ月休業を余儀なくされました。入院期間中は妻も共に入院しました。しかし、手術しても腰痛は治まらず、体力的に不安をかかえています。
今後、自宅介護者の負担が少しでも軽減できるよう介護料の認定変更(認定変更による差額で、ヘルパー雇用の確保ができるよう)をお願いします。
なお、自宅介護の為の 玄関・トイレ・浴室・寝室等の自宅改造及び増築の状況や、前述の介護実態を、機会があれば、実際目に触れていただきたくお願いいたします。
2003年*月*日
せき損 太郎 記 印
※ 併発疾病(褥瘡・熱発の頻度・膀胱炎・腎盂炎等)に係る介護増・集尿器(袋)装着による排尿処理における介護内容等も該当者は、詳細に説明を書くようにして下さい。
〈文責/織田 晋平〉
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」