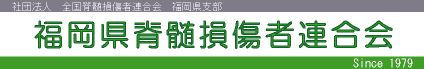
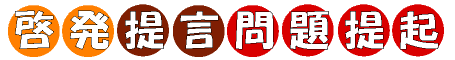
![]() 社会保障制度の新展開
社会保障制度の新展開
-健康保険(共済各種・社会・国民)
・年金(共済各種・厚生・国民)
・介護保険等の社会保障制度の空洞化-
会長 織田 晋平
-はじめに-
昨今、厚生年金・国民年金の保険料の負担が重く加入しなくなっていると言う。自営業者の三人に一人が保険料を支払っていないと言う。無年金者の問題が問われる中、無年金者が増加している現実がある。
企業が厚生年金に加入しなければ、従業員は給付水準の低い国民年金に移ることになる。一方、もらえるかどうか分からない国民年金の保険料を支払っても「!!意味ないじゃーん!!」との考えが、若い世代に拡がっている。(フリーターや大学生の存在)
介護保険についても、国はドイツの介護保険制度の原因や年齢を問わずすべての要介護者を対象にする包括的なものをモデルとしたが、出来上がった制度は高齢者介護に限定され、いわゆる障害者は対象外となっている。四月から開始されたが、この制度の矛盾と商業主義に委ねられた「市場主義・請負主義」の福祉は何をもたらすのか、その流れ抗した当事者と市民レベルでの改革活動が問われていると言える。
-年金制度の問題点-
わが国の厚生年金は、一九四二年に労働者年金制度が発足し、二年後に厚生年金に改組されている。この制度の発端は戦費調達のためとも言われている。また、年金受給や健康保険や福利厚生(企業独自の年金、住宅・余暇制度)においても企業の大小で差が付いてしまう制度をとっている。年金も現役時の所得に反映されるので、老後の所得も格差を生む制度となっている。
現在の厚生年金は、厚生省がモデルとして示しているのは「昨年時点で七十歳の男性が八〇歳まで生きたとして、生涯に支払う保険料は約千三〇〇万円(本人負担は七〇〇万円・事業主負担六〇〇万円)に対して受け取る年金総額は六千八〇〇万円になる。
同じように昨年五十歳の団塊世代の場合は、保険料が三千八〇〇万円(本人二千万円・事業主千八〇〇万円)に対して、年金総額は五千七〇〇万円になる。それが三十歳となると、保険料が六千百万円(本人三千百万円・事業主三千万円)に対して、年金額は五千万円にとどまる。」と言う。それより若い世代の給付はさらに少なくなり、かろうじて本人負担の保険料の総額を上回るだけだと言う。(年金不信に繋がっている原因といえる)
現在の年金の積立金は、これまでに約束している給付を実施するためには、四百五十兆円不足すると言われている。しかし、政府の年金改革は、保険料負担を抑えるために、将来の給付を削減する事が中心になっている。
-これまでの動き-
国は、高度経済成長を背景に福祉元年と唱えた一九七三年の法改正では、各種共済年金・厚生年金・国民年金における給付水準の官民格差の是正が求められていたが、①現役労働者の老齢年金額を平均賃金の六〇%程度(厚生年金は月額五万円に引き上げられた)に設定し、②報酬比例部分の査定の際に基礎となる過去の低い所得水準に一定の倍率を掛ける再評価率制度の導入、③物価の上昇率に合わせた年金スライド制を設けたが、各種年金制度の構造的な格差は是正するまでには至ってない。
一九八五年、国民年金財政の破綻、救済するための公的年金制抜本改革が迫られていた。年金改革の大儀名文は、従来の三種八制度となっているものを「1.「基礎年金」を共通部分を統合一元化して、年金財政の破綻を回避して安定かを計り、2.給付の抑制と負担の拡大により世代間の公平か計り、3.女性の年金権と障害者給付の充実を目指すものである」として基礎年金導入をした。よって、国民年金財政の危機は回避され、八六年四月からの「基礎年金」は実施され障害者の所得保障が確立されたと言えるが、年金制度間の矛盾と制度上の狭間で無年金者の存在が大きな問題となっていくが、未だ無年金者の所得保障の確立は、その糸口さえ見い出せないでいる。
その後、八九年、九〇年、九四年と共済年金・厚生年金・国民年金の改革を進めてきたが、いずれも場当たり的で、財源上のつじつま合わせで抜本的改革に至らず今日に至っている。超高齢化と小子化による現役保険料の負担者減と受給者増の逆転現象を目の前えにして、政府も官僚も政治家も国民が納得する具体的改革について提起しえていない。
介護保険制度についても同様な事が言える。すでに制度上の問題が多岐にわたっているが、これらの抜本改革の実戦が求められている。
先進国の社会保障は「弱者救済」ではない。すべての国民が安心して暮らせるための共同事業であるとしている。医療・年金・介護・児童手当(子育てを含む)・教育等の社会保障構造を横断的視点に立って再構築(国民的合意形成)することが問われて(機会でもある)いる。そして、我々はその渦中にいる当事者であることを決して忘れてはならない。
(広報誌「わだち」No.101より)
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」