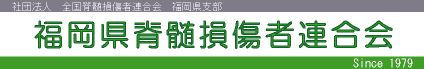
![]() "ほ・ん・ろ・う"される「障害」者福祉の現状
"ほ・ん・ろ・う"される「障害」者福祉の現状
―濁流に飲み込まれるのか―
全脊連 本部理事 織田 晋平
一昨年一月、厚生労働省が支援費制度の利用量(時間)に関して、「上限を設定」することを知り、各障害者団体が協働して厚生労働省へ「上限の撤回を求めて、連日抗議行動と交渉を行ったことは、皆さんもご承知でしょう。この、一連の交渉において障害者団体は、厚生労働省と「上限は設けない」との約束を「取り付けた」と、胸をなでおろしたのです。
ところが、4月の支援費制度が始まると、「125時間の上限の厳守」を貫く市町村(申請窓口)が続出しています。一部の全身障害者のみ、上限は適用されず、400時間から720時間(1日24時間介護)の要介護認定がなされている事例もあり、各地域間の「認定の格差」が大きく生じているところです。その格差は、各サービス内容・量(時間)の認定・ケアマネジメントの違いで、生活支援・介護サービスに格差が生じ、必要とするサービスを受けられずに、利用者の生活低下につながり問題となっています。
介護保険は、家族のみで抱えるのではなく、介護の社会化(社会保障制度)がその制度の目的でした。支援費制度は、生活支援・介護サービスの自己選択と契約(利用者主体の権利)制度として、地域において、家族や他者に依存することなく「社会保障としての支援費制度を行使する権利」があることで、「自立した生活と人生の形成」が、できると小躍りし、「支援費制度」が始まることに期待していたのです。
しかし、前述のように多くの問題が出ています。これらの問題は、支援費制度の「窓口」である市町村の対応のあり方に問題があります。
第1点目には、障害者の生活実態や障害の特性に関する理解とその周知度です。(市町村ごとにバラバラ)
第2点目には、要介護認定の視点の欠如です。支援の内容は、家庭内生活支援と社会参加の支援という二つのニーズがあります。なお、社会参加という範囲は、医療や教育を受ける場合に必要な支援、また、就労するための事前の職業訓練・就労後の支援、そして、一般の社会・文化活動やスポーツや娯楽等の自己実現するための「支援」と考えますが、これらの多くは、「利用制限」がなされています。今後の課題です。
いまひとつは、介護内容の「医療行為の範囲」となされている、痰吸入・摘便や自己導尿、褥瘡の治療等、「医療行為」といわれている部分です。「看護師の職域」とされている分ですが、これは、家族がやる分には黙認されていますが(自己責任ということでしょ)、ホームヘルパーはやれないことになっているのです。資格者の看護師でなければなりません。
これらは、また、訪問看護や入浴サービスの利用は、「高額」になるために、他の介護支援サービスを削る人も少なくなく、生活の低下になる現実があります。(自己負担能力の限界)
このように多くの問題が露呈する中、今日、介護保険制度に支援費制度を統合する(吸収する)との新たな問題が政治的な現実的課題になっており、日々、各障害者団体や当連合会の本部理事は、厚生労働省や関係国会議員と折衝し、支援費制度の改悪阻止に取り組んでいるところです。
これらの経緯を紐解くと、介護保険導入から支援費制度の開始、そして今日の両制度の統合は、一方では、介護保険料徴収(40歳から)と統合時には20歳からという、二段階方式での保険徴収に対する国民の反感を最小限にする戦略でしょう。2回に分けて、次第に「やもを得ない」との認識を喚起する戦略でしょう。はじめに「保険料徴収の枠組み形成」ありきだったのです。また、「介護保険制度でサービスの枠組みを確立する」ことで、支援費制度のサービスの拡充を制限する狙いもあります。それは、高齢者の介護の内容と障害者支援内容の違いがあることで、あたかも対立軸があるかのように議論を提起し、高齢化による介護内容との規定を作り、一方では、障害者に対する介護サービスを介護保険制度におけるサービスを援用する運用を図り、一段と利用者には複雑で難解なものと変容させているというのが現況なのです。
つまり、「支援費制度」と「介護保険制度」の関係、「支援費制度」と「労災の介護補償給付と労災ホームヘルプサービス」との関係、「介護保険制度」と「労災の介護補償給付及びホームヘルプサービス」の関係等の制度間の区別と調整は、要介護認定・ケアマネジメント等の現場で、その運用が周知されていない中、混乱や調整不備が生じているところです。従って、利用者は、必要とする「介護サービス」を利用できない実態があります。(船員保険法・消防法・国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法等も同じ)
以上の個別の法制度について「公費負担優先給付」としながらも、介護保険制度のサービスの援用、活用を図るという「意図」は、介護支援策の「介護保険制度への道」だと危惧します。
その意味では、始まったばかりの「支援費制度」を「介護保険制度」に統合吸収する提起は、そうそうに「撤回・凍結」して、5年間位を試行期間として、その実践的な経過の中で、よりよい「支援費制度」の確立を図ることを求めていくことが当事者としての課題と考えます。
必要なこととは、支援費制度を「介護保険に統合するのではなく」、今後、実践的に試行錯誤し確立した、支援費制度のサービス内容を「介護保険の制度」として改革すべきであり、障害者・高齢者との区別するのではなく、生活・介護支援が必要とするすべての国民が、必要とする介護サービスを選択し契約し、自立した生活を作れる社会保障としての生活支援・介護サービスを利用できる制度とすることが、本来のあり方と考えます。
「それは、理想です」といわれるでしょうが、この間、論議の軸足を高齢者・障害者の違いがあると「区別」し、高齢者介護は、「人生の終末期に対する家庭内生活介護が中心」なのだと、傲慢にまで、障害者の立場を強調したことを反省し、高齢者の方々もさまざまで、買い物や・音楽や演劇、如何に生き生きと生活を保障するのかであります。このように、介護保険制度サービス対象者の方々の「社会参加をする機会」を無視した「発言」となっていたことを真に反省ししつ、再考する次第であります。
2004年3月11日(木)
(『わだち』No.123より)
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」