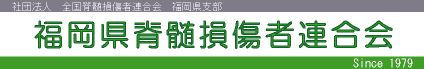 �@�@�@
�@�@�@
| �S���J�����S�q���Z���^�[��P�T�� | |
| �����^�Q�O�O�S�N�V���Q�S���`�Q�T�� ���^�z�e�����K������ �@����N�� �@�u���ꂩ��̘J�����S�q�������ƈ��S�Z���^�[�̖����v �@�u�J�Еی��̖��c�����߂��鏔���v �@�u��Ў҂̗��ꂩ��̒�N�i�J�Еی��̖��_�j�v �@�S�����S�Z���^�[����́A�S������Z���^�[�W�҂U�O���A�������P�Q���E��ҘA�P�V���E���̑��P�O�����̖�P�O�O���̎Q���ŊJ�Â���܂����B �@�Z���^�[�W�҂́A�����ЊQ�E�J�ЁE�E�ƕa�E�ߘJ������E��̈��S�q�����ɌW��\������i�ٔ����܂ށj�̃T�|�[�g�����Ă���i�d���j���ƂŁA��t�E�ٌ�m�E�Љ�ی��J���m�̕��X���ꏏ�Ɏd�������Ă��܂��B �@�܂��A�����J���ȂƐ����A�J���@�E�J�Ж@�Ȃǂɂ��āA���A��N���s���Ă��܂��B �@����͐D�c��B�u���b�N��̒�N���u��Ў҂̗��ꂩ��̒�N�v�����Љ�܂��B |
|
| ��Ў҂̗��ꂩ��̒�N �i�Ёj�S�ҘA�@��B�u���b�N�A�����c��@��@�D�c�@�W�� |
|
| �@�Љ�ɂ�������܂����D�c�ł��B�����S�����S�Z���^�[�̑�����ŊJ�Â��邱�Ƃ����肢�����̂́A���ĘJ���^���̐��̋��_�ƌ���ꂽ�����ɘJ�����S�Ɋւ���T�|�[�g�Z���^�[���Ȃ��͔̂��ɂ��������ƁA�Q�W�N�Ԏv�������Ă�������ł��B��B�ɂ͒Y�B�ЊQ�ɂ�邶��x�̐l�A�b�n���ł̐l���������܂������A���a�Q�O�N�`�R�O�N��͒Y�B���̂Őґ��ɂȂ�l������Ȃɑ��������̂��ƁA���͋�B�J�Еa�@�ɓ��@�������Ɓi���a�T�P�N���j�m��܂����B�܂��A��B�ɂ́A�k��B�̐V���S�͂��ߏd���w�H�ƒn�т�����������܂��̂ł̘J�Ў��̂�����܂��B�����̘J�Ў��̂ɑ���J���ґ��́u���ӎ��v���A����ɊɂȂ��Ă��������Ƃ��������Ă�������ł��B�މ@��i���a�T�R�N�j�ґ��A�����g�D���A�������͂��߂��̂�����Ȏv������ł��B �P�D�ґ��Ƃ͂ǂ�ȑ����� �@����܂ł̐ґ��A����̊�����ʂ��Ċ����Ă��邱�Ƙb�������Ǝv���܂����A�͂��߂ɁA�ґ��Ƃ͂ǂ̂悤�ȑ����Ȃ̂��A���a�Ȃ̂��B�b���������Ǝv���܂��B �@�Ґ������Ƃ͂ǂ�ȑ����Ȃ̂��A��Q�Ȃ̂��A�m���Ă�����͂ǂ̂��炢���܂����B��������Ă݂Ă��������܂����B�قƂ�ǂ��Ȃ��݂����ł��ˁB���͎��Ă���Q�X�N�ڂł����A�����P�O�N��y�̐l�������͏o�Ȃ��Ă��܂����A�ȒP�ɐҐ������ɂ��Ă��b���܂��ƁB�Ґ��Ƃ́A�����x���Ă����̕�������ł����܂��B�����牺�����łł��B���傤���`�̗��������肪���łP�Q�Ԃƍ��łP�Ԃ�����A���ł͐卜�܂ł���܂��B�ҒłƂ����͈̂�{�̍��ł͂Ȃ��A��ЂƂd�Ȃ��Ă��āA�d�Ȃ����ԂɒŊԔ������āA���ꂪ���邪�䂦�ɐl�ԂƂ����̂́A�O�ɋ���A���ɔ������肷�邱�Ƃ��ł���킯�ł��B�ŊԔ�����ƁA���ɂƂ������ƂŁA�F��������m����Ă���Ƃ���ł��B �@���̐Ғł̒��ɐҐ��Ƃ��������_�o�Ƃ����̂��ʂ��Ă��܂��āA���̒����_�o�͔]�ƂȂ����Ă��܂��B�]�͊ȒP�Ɍ����R���s���[�^�[�̂悤�Ȃ��̂Łi���͂����ƍ��x�ł��j�A�����ȏ����������Ă���̂ł����A�Ƃ��ɉ^���_�o�������ǂ�_�o��A�S���A�t���A�̑����̂����ȑ���⌌���E�����_�o�������䂷��_�o�Ȃǂ��A���̒����_�o�i�`���H�j��ʂ��ĐM�����s�����藈���肵�Ă���킯�ł��B���̐��͂ǂ��������̂��ƌ����ƁA�P���Ɍ����Ε������̓d�b�����S���W�߂Ă������̑��ɂ����݂����Ȃ��̂��Ґ��ł��B�Ђ���Ƃ�����A����ȏォ������܂���B������F���A���ɉ������𗎂Ƃ��āA���邢�͉����ɏR�T���āA�u�ɂ��v�Ƃ����ߖ�������Ƃ����̂́A�ł����u�Ԃɑ��̐G�o�_�o�i�Ɋo�j���璆���_�o��ʂ��Ĕ]�ɏ�s���āA������������āu���������[�v�ƁA�������t���o�Ă���B����́A���ɕC�G���鑁���ŁA��ɒ����_�o�ŐM�����������Ă���̂ł��B �@����������̓I�Ɍ����ƁA�F����̓g�C���ɍs���ꍇ�A����͔A�ӂ������čs���킯�ł��ˁB�g�C���ɗ����ď������ł���ƁA�����ō�����o���܂��Ȃ�Ă��Ƃ͈ӎ����Ȃ��͂��ł��B�N���́A�������l�ł��������S�O�Occ�A�傫���l���ƂU�O�O�`�X�O�Occ���~�A���܂��B���܂�����g�C���ɍs�������Ƃ����M�����A�N������]�ɔ�������킯�ł��B�g�C���ɍs���ė����ď������ł���ƁA�A�����܂��Ėc���ł����N���́A����͂��傤�ljʕ��̃������̖Ԃ̖ڂ݂����ɁA�N���̎���ɐ_�o������߂��炳��Ă��āA�������ł���Ɠ����ɁA�i�����ł͈ӎ����Ă��Ȃ����ǁj���R�ɁA�Ԗڂ̐_�o���N�������k�����铭�������A�����Ɏ����J�����킯�ł��B������r�A���ł���Ƃ����d�g�݂ɂȂ��Ă���̂ł��B����͑S���A�]�ƒ����_�o���o�R���N���ň�u�ɍ쓮���Ă���킯�ł��B�i�ґ��҂͐M��������܂���̂ŁA���̔r���@�\�������܂���j �@�ґ��Ƃ́A�O�����邢�͕a�C�Œ����_�o�i�Ґ��j���ؒf���ꂽ��Ԃ������̂ł��B���̐ؒf�����ɂȂ������̂��S���ؒf�����l�A�����ؒf�����l�A�ꕔ�ؒf�����l�A�������ʂł��Ǐ�͈Ⴄ�킯�ł��ˁB�����ł��������܂���ƁA����������������Ȃ��Ȃ�d�x�̎l����ჂƂȂ�܂��B�����ڂł́A��������č����Ă���ƁA�����Ȃ���Ԃł��肤�邱�Ƃ��炢�͂������肾�Ǝv���̂ł����A���ۂɂ͓��������������āA������Q�A�r����Q�i�召�@�\��Q�j���N�����E�t᱉��ɂ�����Ղ��A���B�@�\��Q��������܂��A�l�ɂ���Ă͒ɂ݁A���ɂ�����A�s���j�Q�v���ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�ґ��ɓ��L�ȁA���ɂ�����Ղ���Q�ƂȂ�u�������a�i�ґ����N���Ƃ��鎾�a�j�v�Ƃ����̂��A�J���Ȃ��F�߂Ă�����̂ł��Q�T���a����܂��B�������A���̔��e�ł͑���Ȃ����ɂ������ƍl�����鎾�a����̂ł����A�J�ДF�肳��Ȃ����a������킯�ł��B�ґ�����w�I�E�����w�I�Ɋς�Ə�L�̋@�\��Q�ƂȂ�܂��B �@���܈�l���Ē����������́A�ԃC�X�g�p�҂́A��Q�҂̑�\�݂����Ɍ����܂����A��ʓI�ȁu��Q�̔F���v�́A���̌����Ă��镔���́u�`�v�݂̂����Ĕ��f����Ă���Ƃ����܂��B�����ŁA�����Ă���g�̂̑����E�@�\�`�Ԃ��݂āA�u��Q�v�҂ƌ��ĂƂ�A�����ƈႤ�Ƃ�����ʂ��s���Ă���B���ӎ��I�ɂ������Ȃ��Ă���킯�ł��B���邢�͓���I�ɂ݂Ă��邩�ł��B�����ł̋�ʂ��u���ʁv�ɂȂ����Ă��邱�Ƃ����N���Ăق������̂ł��B�܂��A�ڂɌ����Ă��Ȃ��u��Q�i���a�j�v�̕���������Ƃ������Ƃ�m���Ăق����̂ł��B �@�ґ��҂Ƃ́A�ǂ̂悤�ɂ��Đ�����̂��A�ł����B�����A�n���S�ŗ���ꂽ��������������Ǝv���܂����A�������@���̏��a�T�P�N���A�����s�̒n���S�͌��݂���Ă��āA���̒n���S�H���Őґ��ɂȂ����l���ЂƂ���@���Ă��܂����B�n���S��ʂ�Ƃ��Ɂi���̍H���͂P�O�N���炢�������Ă��܂��j�A���̍H���ŘJ���҂����l����ŁA�ґ������l���܂�āA�ґ��ȊO�̘J�Ў��͉̂����������̂��ǂ����ȂǑz�����܂����ˁB�����͂��܂ł��}���V�����u�[���ŁA���w�̃r���������Ă��܂��B�����������w���݂̒��ŘJ�Ў��̂��F�����Ƃ����ƁA�����������Ƃ͂Ȃ��ł��ˁB��ʓI�ɊF���A��ʐ����̂Ȃ��ł��낢��Ȍ����ɓ���Ƃ��ɁA��x�����ł���������l���Ăق������Ƃł��B�����ł��A�E��Łu���S�v�ɂ��čl���邱�Ƃ��L�߂������̂ł��B�ґ��ɂȂ�l�͔N�ԂT�C�O�O�O�l�قǂƂ����Ă����āA�ŋ߂́A��ʎ��̂�X�|�[�c�Őґ��ɂȂ�l���������Ă��܂��B �Q�D�u��Ўҁv�Ƃ������� �@�u��Ў҂̗��ꂩ��̒�N�v�Ƃ������̃��W�����ƁA�u���ۏ�Q���ޏ��łƍ��ې����@�\���ށv�Ƃ����̂������Ƃ��Ă��z�肵�Ă���܂��B �@�ŏ��Ɂu�J�Еی��Ґ��Ɩ��_�v�ɂ��Ăł����A���S�Z���^�[���7����10�`13�łɁA�J�Еی��̓K�p�A���S�ЊQ�̔������ƁA���t��ޕʂ̎Ґ��̐��ڂ��Љ��Ă��܂��B2002�N�x���̔N���Ґ��̍��v�́A219,720�l�ƂȂ��Ă��܂��B22�łɂ�2002�N�x���̓s���{���ʂ̓����f�[�^���Љ��Ă��܂��B�������̋��Z���錧�̑Ώێ҂ɂ��čl���Ă������������̂ł��B ���݁A���a�E��Q�N���E�⑰�N���̎��Ă���l�i��Q�Q���l�j�̒��ł́A����x�Ɛґ��̐l�����Ȃ�̔䗦���߂Ă��邱�Ƃ����킩��ɂȂ�Ǝv���܂��B�J�ЂŖS���Ȃ����ꍇ�ɂ͎��̂��B���ɂ����ł��̂ŁA���Ƃ̏ꍇ�Ȃǂ́A�Ƒ��Ɉ⑰�N�������Ƃ���Ȃ�x������킯�ł����A���[�̑������ȂǂɂȂ�ƁA���̂��N������������Ёi�g�p�ҁj�������Ă��܂��ꍇ������܂��B��������Ǝ葱�����G�ɂȂ�ȒP�ɂ����Ȃ��Ȃ�܂��B���ǂ��̉���̂Ȃ��ł��A������������ǂ������ŁA�J�Еی����K�p����Ȃ������������܂��B �@�������������I�Ȗ�肪�N�����Ă���킯�ł����A�����́A���ۂɘJ�Еی��̊Y���҂ł����X�̒��ŁA�@���I��̖���葱����̖��ɂ��Ē�N�������Ǝv���܂��B �@�^�C�g���ɂ́u��Ў҂̗��ꂩ��̒�N�v�Ə�����Ă��܂����A�l�̕�����́u�����҂̗��ꂩ��v�Ə����Ă����̂ł��B���A�u��Ў҂̗���v�Ƃ������t�ɁA���Ɉ�a���������Ă��܂����A�Ȃ����Ƃ����ƁA�u��Ё����Q�v�Ƃ����v�l�����Ă��܂��܂��B���邢�́A��Ƃɑ��ĐӔC�Njy�𔗂�܂��B��Ђ������瑹�Q�����𐿋�����悢�̂��Ƃ��܂��ƁA���Q�����Ƃ́A�����I�ɂ͋��Ɋ��Z���邾���Ȃ̂ł��i���Z������e�����j�B�����g���ٔ������܂������A�ŏI�I�ȋ��z�����߂�Ƃ��ɁA���ǎ����̖�Ⴢ����́A�Ⴆ�A������{������ɂ�����ɂ��邩�Ƃ����b�ɂ����Ȃ�Ȃ��킯�ł���B�܂��A������̊�Ƃ������Ă��鎑�{�Ƃ������A�x���\�͂ɉ����Ă����A���Q�����͎Z�o�ł��Ȃ��Ƃ�������������܂��i�{���I���Q�������łȂ��j�B�ٔ��̂Ȃ��Ŏ������Ǝ�Ɍ����܂����B�u���̑�����{������Ŕ��邩�B��疜�~�Ŕ���Ƃ����̂Ȃ�A��������疃Ⴡi�I���Ɠ�����ԂɂȂ��Ċ��Z����Ƃ̈Ӗ��j�����Ă���ƁB����ł������v�Ƃ����ɒ[�Șb���������Ƃ�����܂��B��͂�A���������b�ɂ����Ȃ�Ȃ����A�ٔ��ł͖{���ɐ����̌����Ƃ��Ắu���Q���r���v��₤���Ƃ��ł��܂���ł������A��肫��Ȃ��v���ł����B �@������Q�����𐿋����錠�������邵�A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���������̌o�ϓI�Ȃ��Ƃ�����킯�ł��B�����ЂƂ́A�����CO�����i�O��Y�B�̒Y�o�����j�̒��ł������Ă��܂������A�ӔC�Nj��┅�����������ŕ������i�߂��Ă����̂��Ƃ������Ƃł��iCO���ʗ��@�̐���̈Ӗ�����Ƃ���ł��B�����@�ŁA����x�E�ґ��҂���Ў��̕��ϒ����̂U�O���x�ƕ⏞���t����b���鋋�t����A�Q�O���Ƃ̓��ʔN���̋��t�n�݂���t������A��Ў��̋��^�̕���80�����N���v�Z�̊� �b�ɂȂ�܂��j�B �@������́A�J�Ў��̂ŏ�Q�i���ǁj�������āA�������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���̐��������Ă�����ŁA�ǂꂾ���̎s���I�Ȑ������ۏႳ��Ă��邩�Ƃ������Ƃł��B�����̐����̒��ł����ʼn����ł��Ȃ��������N���܂��B�ґ��҂̒��ɂ́A�މ@��A�Ƃ��������o�Ȃ��l�����܂��B�܂��A���N��Ɏ��E�҂����܂��B���̂悤�ɁA��Q�������ƂŁA���̌������Ƃ߂��Ȃ��l�����܂��B����������Q�������N�������ƂƁA�����̂��܂��܂ȎЉ�I�ȁu��ǁ��j�Q�v���i�O���E���ʁj�v�̌����𑨂��Ԃ��Ăق����̂ł��B����́A�X�̐��_�I�Ȗ��Ƃ��āu�Еt�����Ȃ��v���ƂȂ̂ł��B���̖���b���Β����Ȃ�܂��̂ŁA���̂ւ�ł�߂Ƃ��܂��B �R�D���ۏ�i�⏞�j�̖��_ �@���ɉ��̖��ł����A�Ⴆ�A�J���ҍЊQ�⏞�ی��@�ɂ́u���⏞���t�v�Ƃ����̂��A�����W�N�ɓ��@��P�X���̓�ɑg�ݓ�����܂����B����܂ł͘J���������Ƃ̉��b�I�Ȑ��x�Ƃ��āA��싋�t�i�蓖�j�Ƃ����̂��������̂ł��B�J�Ђ̉��⏞���t�Ƃ����̂́A�펞���Ɛ������Ƃ�����̋敪��������A���s�͉Ƒ��̏ꍇ56,950�~�A�F�l�A�m�l���邢�̓w���p�[�̎��i�������Ă���l�Ȃǂ́A���l���̏ꍇ��104,950�~�Ƃ����̂��A���s�̉��⏞���t�Ƃ��čs���Ă��܂��B �@�u ���J���v�Ƃ������Ƃōl����ƁA�N���������Ă����̓��e�i���E�ʁ����ԁj���ς��킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�Ƒ�����삷��Ɖ��⏞���t�����z�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͂�����ƕ��ɗ����܂���B�F����͂ǂ��l���܂����B�Ƒ������甼���ʼn䖝����Ƃ����̂��A�J�Ў��̂ɋN�����ē������J�����K�v�ɂȂ��Ă���̂ł���A�������z�ŕ⏞���ׂ����Ǝv���܂��B �@�����ЂƂA�ŋ߁A�����N������ی����x�̖�肪�傫������Ă��āA���ی����x�ɏ�Q�Ҏx�����x������Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂��B��Q�҂̎x�����x�Ƃ����̂́A��Q�҂̉^���ŁA�i�܂��n��I�ɂł�����ǁj�A24���Ԃ̉��ۏᐧ�x�������Ƃ��Ă�����Q�҂���������킯�ł��B������x�[�X�Ɏx�����x�Ƃ����̂́A�u�����҂̎��ȑI���Ǝ��Ȍ��茠�𗝔O��搂��v�V�����x����x��n�݂��Ĉ�N�ł��B������A�ˑR�ɉ��ی��ɓ�������Ƃ����̂ł��B ����͑傫�Ȗ��Ȃ̂ł��B�ׂ������e�͎��ԊW�ŏȂ��܂����A�����A�Ⴆ��A����24���Ԃ̉��x�����K�v�ȑS�g��Q�҂ł���ꍇ�ɁA�x����̏ꍇ��24���Ԃ��ۏ������������l�����܂��B����24���Ԃ̃w���p�[�̉��J�������z�ɂ���ƁA�ō���200���~�ʂ�������炵���B�J�Ђł́A�����v��샌�x���̐l�ł͂�͂�24���ԕK�v�Ȃ̂�����ǁA�Ƒ�����삷��ꍇ�A�T���]�~�������炦�Ă��Ȃ��Ƃ����������N���Ă���킯�ł��B���l�ɉ��𗊂�ł��P�O���]�~�������t����Ȃ��A�c��͎��ȕ��S�ł��B �@�x����ł���ȑO�͂ǂ����������ƌ����ƁA�����ł͂Ȃ��A��ʂ̏�Q�҂̉��ۏ�̓[���ɓ������������A�n��I�Ɋ��������āA���1���ԂƂ��Q���ԂŁA�T�ɂP�`�R��Ƃ����z�[���w���v���h�����x�ł������̂ł��B �@���ɂ����ۏᐧ�x������܂��B���W�����Ɂu�J�Ђ̉��ۏዋ�t���_�ɂ��āv�Ƃ������ƂŁA�P������P�O���܂ŏ����Ă��܂��B���낢��ȉ�싋�t���x�̒��ɂ́A�����x���ł������茻�����t�ł������肵�܂��B���{�ʼn��ۏ�̎n�܂�́A�J�Еی��ƌ�����Ў҂Ɛ����ی�@�̑��l��쐧�x�i�s�����̕����{��j�̂R����{�Ƃ���A�������z�ʼn����т̓��e�ɂȂ��Ă��܂����B �@�����ӕی��ɂ������엿�̕]���z�i����j �A�����Ԏ��̑�Z���^�[�����t�����엿���t�z �B���ی����x�ɂ������싋�t�i�w���p�[�̉���V�j �C�u�x����x�v�ɂ�����V���t�z�i�w���p�[�̉���V�j �D������Ў҂ւ̉�싋�t�z �E�����ی�@�ɂ����鑼�l��쐧�x�̋��t�z �F�e����{�݂ɂ�������]���҂̋��t�i�����j �G������̑��Q�����ɂ������엿�̕]���i����j �H�J���ҍЊQ�⏞�ی� �I���̑��A���ƁE�n���������ЊQ�⏞�@�i���E�����ρE�D���ی��@���j �@��ʂ̏�Q�҂̐l�����ɂ͉��ۏ�͊F���������A���̓����́A�J�Ђ͉��蓖�Ă����炦�Ă����Ȃƌ���ꂽ���オ���������Ă��܂������A�x����ł�����A���x�͘J�Ђ̕����Ⴍ�Ȃ����̂ł��B���܁A�x��������ی��ɓ�������Ƃ����̂́A�����Ȃ肷�����x������ǂ�����ė}�����邩�Ƃ������Ƃ��A�����J���Ȃ̐헪���Ɩl�͎v���Ă��܂��B�ȑO�A�J�Ђ͂����Ȃƌ����Ă����̂��A�t�ɒႢ�킯�ł�����A�����Ȃ����x���������������ޗ��Ƃ��āA�J�Ђ̉��⏞���t�͐����Ă���i��p�j�̂ł��B �@�J�Ђ̐l�͒��ɂ́A���l���ق��āi���ҁj���A10���~�ł͂P�������Ԃ��������݂Ă��炦�Ȃ��A������A����Ȃ����͘J�Ђ̐l���x������g�����Ƃ����P���Ȑl����������̂ł����A�����������Ƃ����邱�Ƃɂ���āA�J�Ђ̉��⏞���t�������グ�Ă����Ƃ����u���ӎ��v�������ŏ����Ă��܂����Ƃɂ��Ȃ�܂��B���x�́A���x�Ԃ̑��݊W�������Ď�舵������邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�������ł���Ȃ���`�Ƃa�̐��x�̂Ȃ��ʼn��J���̕]���̈Ⴂ������܂��B����́A�ЂƂ́A���J���ɑ���]���������Ɠ��{�ɂ͂Ȃ������̂ł��B���a�Q�O�`30�N��܂łɂ́A�Y�z�̘J�Ў��̂Őґ������̂������������ݏo���ꂽ�̂ł����A�����ŁA�ґ��̐g�̉��̉������邽�߂Ɂu�t���Y�����x�v�Ƃ������̂�������̂ł��B�Ɛ��w����h�������t���Y�����A365���Ζ�����킯�ł��B���[�e�[�V�������R�l�őg��ŁA3���Ɉ�܂�ŁA���̕t���Y���������݂̂Ă����l���݂�B���������A��1�ɑ��āA�l�݂����Ɏ�̓����ґ��Q�A�̍��v�R�l���݂�̂��t���Y������̎d���i���j�������̂ł��B �@�t���Y������͂������������ł��B�����J���Ƃ��ẮA���̂悤�ȘJ���`�Ԃ͘J����@�Ɉᔽ���Ă��܂��̂ŁA�ł�����A�t���Y������̎d���́A�J����@������E�ƈ���@��������O����J���҂Ƃ��Ĉ����Ă����̂ł��B�Љ�ی��E�����N���E�ٗp�ی����������������Ȃ��̂ł��B���ꂪ�A1980�N��ɂȂ��āA��Q�Ґ錾�A���ەw�l�N�A�j���ٗp�ϓ��@���Љ�I�E���ۓI�ɐl���ۏႪ���m������āA���{�A�����J���Ȃ́A���������J���҂���u���Ă���Ƃ������Ƃ͍��ۓI�Ȗ��ɂȂ�Ƃ������ƂɂȂ��āA����3�N���炢����A�t�Y�w���z�[���w���p�[�̌��C�������āA�����ƐE�Ɛl�Ƃ��Ĉʒu�Â���Ƃ����헪���Ƃ�͂��߂��킯�ł��B���̂Ƃ��ɁA���J�����ǂ��]�����邩�Ƃ������ƂŁA���J���Ȃ͍l��������������܂��B �@�����Ȃ́A�e�s�����Ńz�[���w���p�[��{�����āA�z�[���w���p�[�h�����Ƃ����Ă����킯�ł��B���̌����ȂƘJ���Ȃ��l����A�z�[���w���p�[�̐g�̏�Q�҂̉��J���ɑ���]�����A����Ă���̂ł��B�Ⴆ�A�a�@�ʼn�������l�A�{�݂ʼn�������l�A����ʼn�������l�B�a�@�ŊŌ�m������ꍇ�ɂ́u�Ō�v�Ƃ������t���g���Ă��܂������A���Ƃ����d�����e�͓��������ǁu�����]���v�͈Ⴂ�܂��B���܂��A�J���ȁE�����Ȃ����J���҂̉��J���𐳋K�ɕ]�����Ă��܂���B�O�Ɋe��̐��x�Љ�܂������A���x�Ԃ̐������͑S���Ȃ��̂ł��A���t�i�����j�ɍ��������Ă��܂��B �@���ی����x�́A���́A�Ƒ��E�g���ł݂邱�ƂɌ��E�i�Ƒ�����������j������Ƃ����F������u���̎Љ�i�����ۏ�j�v����Ƃ����A���J���҂��V�����E�ƕ��삾�Ƃ������ƂŁA���Ȃ菗���̐l�����C���āA�z�[���w���p�[�̎��i������āA�d�����n�߂Ă��܂��B���ꂪ���c���Ŋ�Ƃ̎Q�������͐��������킯�ł�����A���낢��Ȋ�Ƃ����͂��߂Ă��܂��B�������A��������ۂɌo�c�����Ă����ƁA�w���p�[�������Ɉ����g�����Ƃ������ƂłȂ��ƁA���v���グ���Ȃ��B����ŁA�w���p�[������p�[�g�����Ă��܂��āA�Ј��͐��l���������Ȃ��B�����݂Ŏd���������Ă��܂��āA�`������a�����֍s���A�ړ����鎞�Ԃ͎����Ƃ��Čv�Z����Ȃ��Ƃ������܂��B�����Ɋr�ׂāu�����v�͈������g���̕ۏ͂Ȃ��̂Œ��������Ȃ��X���ɂ���܂��B����ł́A���̎��������܂��B �@�w���p�[����̉��J���������ƕ]�����Ă��Ȃ��Ƃ���ɁA�����鑤�ɂƂ��Ă��{���ɕK�v�ȉ��x�������Ȃ��B�x���g�R���x�A���݂ɕ����݂̎d�������A������l�ƒ���l�̊ԂɁA�l�ԂƐl�Ԃ̌��������Ȃ�đS���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�Ⴆ�A���ʘV�l�z�[�������āA����Ƃ��͂��낢��Â����t�������܂����A���ۖ{�l�������Ȃ���Ԃ������Ƃ���ƁA�����A���������ނ�ς��Ȃ��Ƃ�������邻���ł��B�i���ꂪ�Љ�ł��j �@���ہA�v����ԂɂȂ����l�����̐����̎x���E���ۏ�i�⏞�j���x�́A�v����Ԃ������N�������������O�Ƃ��鐧�x�E��|�ɉ������e��̉��ۏ�i�⏞�j���x������܂��B���̒��̂ЂƂɘJ�Ђ̉��⏞���t�Ƃ������x������킯�ł����A���Ɉ������ς����āA���̉��⏞���t�̓���́A�u�p�[�g�̎���640�~�ʂŌv�Z���āA5���~�A10���~�Ƃ����z�ɂ����v�ƁA�����̘J����b������œ��ق��Ă��܂��B�P�O�N�o���Ă��ς��Ȃ��̂ł��B �@���݂̉��ی����x�E�x����x�ł́A�p�[�g�̎����v�Z�ł͂���܂���B���ی����x�̒��̃z�[���w���p�[�̉Ǝ��x����1���Ԗ�1.500�~�A�g�̉��Ŗ�2,500�~�ʂł��B�J���ЊQ�̉��⏞���t�́A�ƒ���ł̐����݂̂�ΏۂƂ��Ă��܂��̂ŁA���̈Ӗ��ł��������]���ɂȂ��Ă��܂���B��Q�҂ɂȂ�ΊO�o���邱�Ƃ��Ȃ��ƁA��ʓI�ɂ͂������܂����ǁA����Ȃ��Ƃ͂���܂���B�Ⴂ�l�A�Ⴆ��20��Őґ��ɂȂ�����A�����A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ�����A�Ƃ̒��ňꐶ���߂����̂��H�ہA�����ł͂���܂���B ��w�݊w���ł���A���w���A���Ƃ�����A�E����Ƃ����v�����𗧂Ă�̂��A���Ăł͓�����O�̂��Ƃł��B�������ꂩ�痈�Ă������́A�ŗ��㎈�Ƃ���Ⴢ��Ă����Ԃł����A�ނƓ������x���̐N���J�i�_�ɂ��܂��āA�ނ͑�w�ɕ��w���āA�J�E���Z���[�̎��i������āA���ݓd���ԃC�X�g�p���Ȃ���ʋ��āA�a�@�ŃJ�E���Z���[�̎d�������Ă��܂��i�ʊw�E���Ȃǂ̎x������j�B�������x���̓��{�l�́A���������v���������Ă��Ȃ��B���w���A�E�Ȃǖڎw���Ȃ����A�ǂ��Ő������邩�Ƃ������Ƃ����܂܂Ȃ�܂���B�Ƒ������āA������x���̐�������ꍇ�͂����ł��傤���A�������Ƒ��̕��S�͌v��m��܂���B���Ă̂悤�ɁA�ЂƂ�œƗ����ĐE�Ɛl�ɂȂ��āA������������������Ƃ������Ƃ͓��{�ł͂ł��܂���B��قnj����܂�������̏㗢�N�́A����̐ґ��A�̎d�������Ă��܂��A�ނ��ґ��҂̃T�|�[�g�����Ă��܂����{�����e�B�A�ł��B�@�Ȃ������Ȃ̂��ł���܂��B�@����Љ�����������p���Ă��d�x�̏�Q������ƏA�E�͓���A���ɖ�肪���肷����Ƃ����̂�����ł��B �S�D����F��ƏǏ�Œ�Ƃ������_ �@�����ЂƂ́A�J�Ђɂ�����A�u����F��v�Ɓu�Ǐ�Œ�v�Ƃ������ł��B �@����F��Ƃ͉����Ƃ����ƁA���ؒf����B���̏���������B����ȏ㎡�Â̌��ʂ��Ȃ��ꍇ�ɁA����F�肷��Ƃ������Ƃł��B�����ЂƂ́u�Ǐ�Œ�v�Ƃ������t���o�Ă���̂ł����A�Ǐ�Œ�Ǝ���F��Ƃ́A�ǂ��Ⴄ�̂��Ƃ������Ƃł��B �Ǐ�Œ�Ƃ����̂��A���́A�l�͂��܂������Ǝv���̂ł����A�Ⴆ�A�����̎�����133�ŁA�u�ӌ��E�v�]�̓��e�v�̂Ƃ���ɁA�u�y�x���N���@�\�s�S��11���ōŒ�ł͂Ȃ����v�A�uQOL�d���̗��ꂩ��O���ɌW�錇���ɂ������A���֓�����ʂ̋��Ɋi�Â���ׂ��ł���v�Ƃ��A�u���ȓ��A�̒��x�ɂ��F����݂��Ăق����v�Ƃ��A�Ō�ɂ́u�l�H���͊��҂̔F����݂��Ăق����v�ƁB������Ǐ�͌Œ肵�āA�l�H���͂�����ΐ������ł���̂ŁA�u����v�����A�u�ǏŒ�v�����̂��Ƃ������f�ŁA��Q�N���ɐ�ւ�����̂ł��B �@�ґ��̏ꍇ�A��قǕ������a�̘b�����܂������A�唼�����ȓ��A�����Ă��܂��B���ȓ��A�Ƃ����̂́A�A���Ɏ����ŃS���ǂ����āA3���Ԃ������炢�ɔA��r�o����킯�ł��B�S���ǂ��o�����ꂷ��ۂɔA���������A�ۂɊ��������N�������N�����₷���̂ł��B�N�������i�ނƁA�t᱉����������N�����₷���̂ł��B�܂��A�̏ꍇ�ɂ́A�̉��������ł��Ȃ��̂ŁA�ď�Ȃǂɂ͂ǂ�ǂ�̓��ɔM���������Ă��܂��̂ł��B���ʂ̐l�͔M���Ȃ�Ɗ��������đ̉���������Ƃ����@�\���쓮����̂ł����A���������@�\���Ȃ��Ȃ��Ă���킯�ł�����A�ǂ�ǂ�M��������B����ő̗͂����Ղ��āA�Ⴄ�a�C�ɂ�����₷���Ȃ�킯�ł��B�ґ��� ��ԑ����̂́A��ጂł��ˁB����13�����Q�����Ă��܂����A�����ȏオ��ጂ������Ă��܂��B���������ґ��̂V�O���̐l�������Ă��܂��B������ጂ��܂��Ȏ҂ł���܂��āA��ʓI�Ɍ����Ώ�����Ȃ̂ł����A�_�o����Ⴢ��Ă���Ƃ��낪�����𑱂���ƌ������~�܂���ጂɂȂ��āA������ƉΏ��̏�ԂɂȂ�܂��B���ꂪ�ł���ƁA�����������N����܂���B����Ȃ��̂ł��ꂪ�G�ۂ�{�B����A�{�B��݂����ɂȂ�̂ł��B���̗{�B��̋ۂ͕\�ʂ����ł͂Ȃ������ɂ��Z�����܂��B�ŋ߂́A�R����������������g���Ă���W�ŁA�R�������ɒ�R����̂��ۂ�MRSA�A���W�I�l���ۓ��̂��낢��ȋہE�E�C���X�Ɋ������������܂��B ���ꂪ�\�ʏ����ጂ̏�Ԃł�������̂ł����A�����ɐ[�������ē����⍜�̂ǂ����ɋۂ��]�ڂ��āA�����Ɏ�ᇂ�����A�r��ؒf���āA�ꖽ���Ƃ�Ƃ߂�l������̂ł��B��ጂ��i�ނƔs���ǂɂȂ��ĖS���Ȃ邱�Ƃ�����܂��B �@�ґ��́A����������A1�N���ʂ��āA�u�Ǐ�Œ�v���Ă��邩��Ƃ��āA���a�⏞�N�������Q�⏞�N���ɐ�ւ��鐧�x�ɂȂ��Ă���̂ł��B�������A�ґ��́A���䂵���Ƃ͌�����������ꐶ�a�@�Ɖ�����Ȃ��̂ł��B�u�Ǐ�Œ�v���Ă���Ƃ����̂��k�قł��B ��Q�⏞�N���ɐ�ւ���Ƃ������Ƃ́A�ЂƂ͗×{�⏞���t��ł���Ƃ������Ƃł��B�������A��Q�⏞�N���ɂȂ��Ă��A�ʏ�A��ጂ̎��Â��N��������������A�J�e�[�e�������������A�ۂ��E��������������A�r�֗p�̉��܂⟯���t���A�ʏ�̎��ÁA���i�̎x���́A�A�t�^�[�P�A�ł��܂��Ƃ������܂����Ȃ̂ł��B �@�Ƃ��낪�A��Q�N���҂��A���@���Â����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��ɁA�Ĕ��F����Ȃ��ƘJ�Еی����g���Ȃ��킯�ł��B�e�s���{���ɘJ�ДN�����k���Ƃ����̂�����܂����A�E���i�ē��V�����j�́A�u�Ĕ��F������ē��@���ĘJ�Еی����g���Ɖ��⏞���t���o�Ȃ��Ȃ�Ƃ��A�葱����₱������������������ۂł��������ȒP���Ƃ��A��Ô�͂�����Ȃ��̂�����v�Ɗ��U������킯�ł��B �������a�ɂȂ��Ă���ǂɜ��A�i�Ґ��̍����y�݂����ɁA���������E��Ⴢ͏�ɏオ��̂ł��j�A�J���Ȃ��F�߂Ă��镹�����a�ł���ɂ�������炸�A�������N�ی��Ŏ��Â��������ȒP�ł��Ɗ��߂��ē��E�������܂��B���ꂾ������Ȃ��B��ጎ��Â��t᱉����N�����Ă������ł��B �@����͂ǂ�����肩�Ƃ����ƁA�ґ��ɋN�����镹�����a�̎��Â����Ȃ���A�������N�ی��Ŏ��Â��Ă���ƁA�J�Ђ̃J���e�ɕa�����c��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�܂�A���̐l���S���Ȃ����Ƃ��ɁA�a�����c���Ă��Ȃ�����A���̐l�́A�u���C�������v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�ґ��Ƃ����Ɩ��ɋN�����鎾�a�ŖS���Ȃ����ƌ����Ă��A���Â��o�߂͓͂��Ă��Ȃ��̂ŁA�u�������āA�Ɩ���ƊW����Ƃ����ł����v�ƁA���ꉽ�������Ȃ��̂ł��B ��Q�⏞�N���ɂȂ��Ă���l�́A�u���Ȃ��͈�U�u�����v���A�Ǐ�Œ肵���킯������A�Ĕ��F�肩��w�I�Ȏ��S�����Ƃ���u�Ɩ���ɋN�����鎾�a�̏؋��v���o���Ȃ���A�J�Ј⑰�N���������邱�Ƃ͂ł��܂���v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���킯�ł��B���a�N���Ə�Q�N���Ƃ́A��������⿂��i�藎�Ƃ��j�ɂȂ��Ă���̂ł��B �@��Q�N�������Ă���l�ŁA�Ⴆ���̐l�͎��Ɏ�p�ŗA�������Ă��āA������C�^�̉��Ɋ������Ă����B����ʼn��N�����Ă���̉��Ŋ̑��������ŖS���Ȃ����Ƃ��A���̕a�C�̌o�߂���������̂ł����B�������A���Q�N���҂́A�u����v���Ă���̂ł�����A���������Ƃ����؋����o���Ă���Ƃ����킯�ł��B���̏؋����o���Ȃ�����A�⑰�N���͂��炦�Ȃ��̂ł��B �@�����ԁA�J�ДN���Ő��������āA���݂���70���炢�ɂȂ��Ă��āA������͒U�߂��S���Ȃ����Ƃ���A�o�ϓI�ɉ����Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��܂��B ���������ӂ��ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�������͂��܁A�����̕a�����Ǘ����A�������a�ɌW��a�C�ɂ��Ă͍Ĕ��F������Ď��Â���Ƃ������Ƃ������߂Ă��܂��B�������A���������̗���ɗ����Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ������������ӎ��́u�Ƒ��v�ɋN����Ȃ��悤�ł��B�T�^�Ⴊ�A�ŋߑ������Ă���O�H�}�K�̃g���b�N�̎��̂ł����A���ׂ�����ƌ����đ��葱���āA���サ�Ď��̂��N�����Ă��܂���ˁB���ׂ����邱�Ƃ��킩���Ă��Ȃ���A������g���Ă���Ƃ����D�_�s�f���Ƃ������B��ʁA����ƐV���ɐ��Q�������āA�e���r�����Ă�����A����l�����������Ă��܂����B�u��l���V����ǂ݂Ȃ��痬���ꂽ�B����܂łɉ��̔������Ȃ����̂ł���v�Ƃ����B�������o����Ȃ��ƁA�V����ǂ݂Ȃ��痬�����܂ŁA�����l���Ȃ��̂��Ƃ����ɂȂ��Ă���ł��ˁB�߂������ȁB �����Ŏ������ǂ���邩�Ƃ����ϓ_���Ȃ��B���ׂĂɂ����āu�����H����H�v�Ɉˑ����Ă��܂��ˁB����͂����̉^���̒��ɂ�����܂��B�^���𗦐悵�Ă���Ă���l�Ɉˑ����Ă��܂��Ƃ��A���ꂩ�Ɉˑ����Ă��܂��B����������肪���ܐ��̒��ɂ͖������Ă���Ƃ������������܂��B������A�u�@����x�v�������Ă��A������ǂ����p���A�s�g���Ă������Ƃ������ӎ����Ȃ��B������ǂ��L�߂邩�Ƃ������Ƃ��Ǝv���̂ł��B���x�̑I����43���̐l�����[�ɍs���Ȃ������Ƃ������Ƃ́A���낢��Ȍ������������Ă��܂����A��{�I�ɂ͂��܂̑̐���e�F�����킯�ł��B�܂�A���܁A�Љ���ۏ�̊�{�\���i��ÁE���E�N���E����E�Z���j���j�]���A���ꂩ��̎Љ���ۏ�̑������u�s��o�ώ�`���v���Ă��܂��Ƃ������v�̕����ɗ���Ă���킯�ł��B�����̏�ɖ��S�ł���킯�ł��B����́A���������̎؋����q���⑷�Ɍ����肳����Ƃ������ӔC�Șb�ł�����킯�ł��B �@��Ђ��ďd�x�̏�Q���������U�߂��A20�N��30�N���ꐶ�������ĉ�삵�āA�S���Ȃ����ꍇ�ɂ́A���݂̂Ƃ���A�⑰�N�����s�x���ɂȂ����Ƒ��ɑ��āA�u�����Ƒ����҉�����v�Ƃ������Ƃŋ��A100���~���x������܂��B����100���~�Ƃ����̂́A�⑰�N���x���Y���҂����炤�����̊z�Ƃقړ������z�ł��B�����キ�炢�o���܂��傤�Ƃ����b�ł��B����́A�Ɩ���̈��ʊW���Ȃ��A�S���Ȃ����ꍇ�ł��������Ƒ��ɑ���⏞�����߂钷���^���̒��Ő��x�����ꂽ���̂ł��B�����A�J���ґ��͑ΈĂƂ��ďo�����̂�300���~�ł������A�g�p�ґ��i�o�c�A�j��300���~�͑������邩��Ƃ�����100���~�ɂȂ��Ă�����̂ł��B �@�⑰�N����\�����Ċē��ŋp�����ꂽ�ꍇ�A�ŏ��ɋƖ��O�ł���Ƃ����ӌ�����������҂́A�����ŁA���O���o���Ȃ��ł����̂ł��B�⑰�̓J���e�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA�؋����������낦�邱�Ƃ��ł����ɁA��w�I�Ɏ��a�̌o�܂��ᖡ�ł��܂���B�ĐR��������\�����Ă��Ƒ����a�����L�^���Ă��Ȃ�����A�s�[���ɏI���܂��B�ĐR���ł��p�����ꂽ��A�����̘J���ی��R����ɍāX�R�����������܂��B�����R����ŋp������Ă͂��߂āA�����ٔ����ł��邱�ƂɂȂ�܂��B����ł������������l����10�N������B�Z���l�ł��S�`�U�N�ʂ�����܂��B�⑰�N���𐿋�����l�͍���҂���������A5�`6�N�ŖS���Ȃ��Ă��܂��ꍇ������܂��B���̓r���ł�����߂Ă��܂��ꍇ������܂��B�i�_�ؒ�o������Ȃ�j �@�����炢�܂̘J�Еی����x���A��Ђ����l�ɂ����ƕ⏞���鐧�x�ɂȂ��Ă��邩�Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��A�J���Ȃ̐R���@�ւ̓y�U��ōs���̂ł�����͂��߂��珟���ڂ͂���܂���B���̂��Ƃ�����̉ۑ�Ƃ��āA�����ƌ����ȑ�O�ҋ@�ւ�݂��Ă��悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă����˂Ǝv���܂��B �@�S���̐ґ��A����Ƃ����̂͊e�s���{���Ɏx��������܂��̂ŁA�S�����S�Z���^�[�̊e�n�̃Z���^�[�Ɛґ��̌��x���Ƃ�����͘A�g���Ƃ��Ă������������̂ł��B�A����̎x���Ƃ����Ă��@����x�ɂȂ���ł��Ȃ����A�����������C������𗬂��d�˂Ă��������āA���������ґ��A����̉���̖��ӎ������コ���邽�߂ɁA�����͂����肢���Ă��������Ǝv���܂��B �@���Ԃ��Ȃ��Ȃ�܂����B �@�{���́A�u��Q�v�Ƃ͉����A�������E�l�����ɂ��Ă��������b���������̂ł����A���Ԃ�����܂���B�����Ƃ��Ă��z�肵���u���ۏ�Q���ޏ��łƍ��ې����@�\���ށv�Ƃ����̂́A����͍��A�̐��E�ی��@�ւ̒��ŁA�V������Q�̑������E�l�����݂����Ȃ��̂���N����Ă���̂��A���n�r���e�[�V�����̈�t��������������̂ł��A���Жڂ�ʂ��Ă������������̂ł��B �@���̃��W�����̓ɁA�u��Q�v�҂͗��j�I�ɂ́A�ǂ�ȑ��݂ł������̂��v�Ƃ������Ƃ��܂߂āA�ꉞ�N�㏇�ɏ�Q�҂̂�����Ă���݂����Ȃ��̂��A�������Ă���܂��̂ŁA���̃����̒�����A������x���j�I�ȈӖ������N���Ă��������āA�ł���Βn��̏�Q�҂̐l�����ƈӌ�����������@������Ѝ���Ăق����Ǝv���Ă��܂��B �@�u��Q�v�҂̖��Ƃ́A�{���A�u��Q�v�����l�X�̎s��������������ɉ������݁A�{���̎Љ���̖{������i�o�ρE�����E�����j���O���Ă������Ƃ����ł���܂��B�܂�A����͎s���Љ���ɂ����āu��ʂ��E���ʁv�ݏo���Ă���̂́A��Q�������Ȃ��l�X�̕����ł���A���l�ςɗ��ł�����Ă���̂ł�����A���P���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́u��Q�v�����҂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̂悤�Șb�������������̂ł����A �{���͂���1���Ԉʂ�\�肵�Ă����̂ł����A���̋@��ɑ����A�c�O�łȂ�܂��I��肽���Ǝv���܂��B |
|
| ���W���� | |
�u��Q�v�҂͗��j�I�ɂ́A�ǂ�ȑ��݂ł������̂��B �@���j�I�Ɋς�ƁE�E�E �@�X�p���^�i�I���O��`�����I�j�ɂ����ẮA�V�����V���������āA�s������^���邩�ǂ��������肵�A�^�����Ȃ��ꍇ�i�g�̂ɖ�肪����j�͒J�Ɉ�������B �@�����[�}����A���܂ꂽ�Ԃ�V�V���A�g�̂��ςĕs�����Ώ�����m�ɂȂ�Ȃ��Ƃ��Đ�ɗ������B �@�Î��L�ɂ́A�C�U�i�M�m�~�R�g�E�C�U�i�~�m�~�R�g�̊Ԃɐ��܂ꂽ�u�g�q�v�͎O�ɂȂ��Ă������Ȃ������̂ň��̑D�ɏ悹�ė������B�Ƃ̋L�ڂ�����B �C�D�ޗǎ���̑m���s��i���傤���j�́u�e�̈��ʂ͎q�ɕv�u�O���̈����v������A�M�҂Ɂu��Q�v�����Ɏ̂Ă�悤�Ɏw������B ���D�M�������̍Ő����A��������A�O��V�c���a�C�Ŏ����E�m���V�c�̑�l�c�q�̐l�N�e���i���˂₷�j���o��Q�������A�Ӑl�̕ی쐭����Ƃ�B �n�D���q����E�E�E�������������ł́A�⑰�̖��Ό��Z�i�����������傤�E�Ӑl�j�������̍��ɂ���A�Ӑl�ɑ���{������܂��B���i�@�t�\�Ìy�O���� �j�D�]�ˎ���̎��q���ɂ́A3000�l��266�������炩�̏�Q�������̂��ݐЂ��Ă����ƋL�^������B���������肵�Ă������� �����̎��㎞��ɂ����āA�w�u��Q�v�҂̎��Ԃ͎j���A�����A���w�̓��ɂ����Ĕے肳�ꂽ��A���h�i���҂Ƃ����Ȃ܂ꂽ�肵���j�A�ז��҈�������Ă���B�x�i�ȏ�́A�t���̒��̏�Q�҂����E�㓡�N�F�����j ���Љ�ɗ]�͂��o�Ă���ƁA���P�̑ΏۂƂ��Ă̏����E��ʂ̎Љ�l������������B�����Љ�̈���Ƃ��Ă̈����ł͂Ȃ������B �@�@1874�N�i����7�N�j�@�~�n�{�� �@�A1879�N�i����11�N�j�ӈ���@�J�݁i���E�ł�1785�N�j �@�B1881�N�i�����P�R�N�j�����P�Ӊ@�J �@�@�����ېV�]���V�����@�E���@�E�i�@���x�E���琧�x�i�l���E�Љ�I�Ȏ�ҋ~�ρj���w���x��݂���B����ނɋ�ʂ����B �@�@�n���҂��Q�҂̋~�ςɋ�S�����Ƃ����B���A�w�Z�́A�u�q�포�w�������w�E�������w�n�l���w�E���w���m�c�t�A���w�E�Ȃ�A���̑��A�p�l�w�Z����ׂ��v�Ƃ���B �@�x����������E�E�E�����Ƃ��č��ւ̕�d �@�J���͂Ƃ��Ă̕]���i���N�ȓ��́j �@���V��\�^����\���W�I�̑��E�E�E�q���ɓ����̂�{���B �@�x���������x�ŏ�Q�҂́A�����Ԃ��E���Ƃ����鎞��B �@�����E�吳�E���a�����̂��܂� �@��O�E���̕�������̍����y�сu��Q�v�̔����Ɨv���ƌo�܁i�T���j �@�o�Y���ɂ�����g���u���E�c�����̎��a�E���a�E�푈�ɂ����镉���ҁB���a10�N�A���{�����q������E��5��w�p�w��͒f��@�̐���𑣐i���܂��B���a15�N�u�����D���@�v����B23�N�ɂ́u�D���ی�@�v�ɕς��܂��B���̑����́u�D����̌��n����s�ǂȎq���̏o����h�~����v�Ƃ���Ă��܂��B �i�P�j���̕����Ƃ������ƂŁA�d���w�H�Ɖ���簐i���܂��B���̌��ʁA�J���ЊQ�E���Q�E��Q�̑呝���i�Y�B���̑����j�ґ��ґ����B �@���ۓI�{��̌o�܂��܂߂� �@���̓����N��1948�N�ɍ��A�́u�l���Ɋւ��鐢�E�錾�v���܂��B �@49�N�i���a24�j�N�g�̏�Q�ҕ����@�����肳��܂��B���A�@�̐��i�߂����āA�u�ی�v�ɂ��邩�B�u�X���v�ɂ���̂��B�u�ی�v�Ƃ���̂��c�_�ɂȂ�A���̌��ʁA�X���@����{�Ƃ��A���̍X���ɂ����ĕK�v�Ȍ��x�ɂ����āu�ی�v���邱�ƂɂȂ�܂��B���̖@�́A�u�����������[���鑕��Ȃǂ���t���A�E�ƌP�����ŐE�Ƃɂ����Ƃ��O��ƂȂ��Ă��܂��B�v���̌�A����ɂ킽���������܂��B �@���E���́E�E�u�X���v�Ȃ̂��ł���B�����́u��Q�v�҂̑������ł���B �@50�N�E��11�A�Љ�o�ϗ�����Łu�g�̏�Q�҂̎Љ�n�r���e�[�V�����v�̌��c�B�T�R�N���E��Q�ҊW�c�̋��c��i�b�v�nIH�j�����B�T�T�N�u��Q�҂̐E�ƃ��n�r���e�[�V�����Ɋւ��銩���B �@60�N�u���_����ҕ����@�v���z�B�f���}�[�N59�N�@����A�o���N�E�~�P���Z���̏������m�[�}���C�[�[�V�����̗��O�������傤�ƂȂ����B60�N��1��p�������s�b�N�i���[�}�j�B62�N�T���h�}�C�h��Еɂ���ܔ̔��֎~�B64�N�A�����J�u�������@�v�̐���B�i�A�����J�̏�Q�҂́A�������^���ɐG������āu���������^���iIL�^���j�v���͂��߂��B68�`70�N��E�����܂ł͑�ʎ{�݊u������ł������B�j �i�Q�j��O���E1965�N��i���a40�N�j�E�G�l���M�[�v����̗�������E���ݘJ���ҁi�ґ����������ݏo�����j�E��ʐ푈�i��ʌ��Q�E�������j�B �@68�N�����������́E���_����҂̈�ʓI�y�ѓ��ʂ̌����Ɋւ���錾�i�G���T�����錾�j�B69�N���ۃV���{���}�[�N�y�у��n�r���e�[�V����10�N�i70�`80�N�j�̑��B71�N��26�A����u�m�I��Q�҂̌����錾�v�B�u�m�I��Q�҂̌����錾�v�B74�N���A��Q�Ґ��������Ɖ�c�E�o���A�t���[�f�U�C���i���z�ɏ�ǂ̂Ȃ��v�j�����܂Ƃ߂�B �i�R�j��l���E1975�N��E�����ԎЉ�ɂ���ʍЊQ�������A�ґ��҂���������i�ʋЊQ�j�E�X�|�[�c���́E��a�E�S�̕a�C�i���������ǁ����_����ǁj�E�J���ЊQ�E�V�ЁB 75�N��30�A����u��Q�҂̌����錾�v�B�A�����J�u�S��Q�Ҏ�����@�v�E�h�C�c�u��Q�ҎЉ�ی��@�v�E�t�����X�u��Q�Ҋ�{�@�v����B �@���A�́u���ەw�l�N�v76�N�u���ۏ�Q�ҔN�i81�N�j�v���c�B ���Љ�̕ω������Y��i�i�d�H�ƁE�Ȋw�H�Ɖ��j�E����̕ω��������p���̕ω��A�H�E�H�i�E�_�Ɛ��Y�E�_��Ȃǂ̉Ȋw�����̐��Y�E���j����Q���ɂ��A�u��Q�v�҂̐��Y�ł���A�푈�ɂ��u��Q�v�҂̍Đ��Y�ł���B����́A�l�דI�Ȃ��Ƃł���Ƃ������Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�l�Ԃ́A���܂�Ă���u���a�V���v�܂ł̉ߒ���H��Ȃ��琶���Ă������̂ł���ƌ����Ă��܂��B�a�ƘV�̊ԂɁu��V�i��Q�j�v�������Ă����ׂ��Ƃ��l���܂��B |
![]() �@�����̏Љ��@
�@�����̏Љ��@![]() �@�[���E�E����N�@
�@�[���E�E����N�@![]() �@�J�Ёi�J���ЊQ�j�W
�@�J�Ёi�J���ЊQ�j�W
![]() �@�o�O�����u���@
�@�o�O�����u���@![]() �@�Ԃ����_���X�@
�@�Ԃ����_���X�@![]() �@�o���A�t���[�ނ�N���u
�@�o���A�t���[�ނ�N���u
![]() �@���N���G�[�V�����@
�@���N���G�[�V�����@![]() �@�L�u�킾���v�@�@
�@�L�u�킾���v�@�@