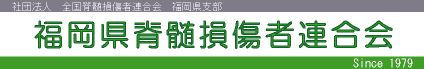 �@�@�@
�@�@�@
| �o���A�t���[�̕ϑJ�Ɋւ����l�@ �|���j���Ƃ����ā| �k��B�x���@�㓡 ���d1) |
|
| �P�j���{���z�w��E���{�����̂܂��Â���w�����F���B�v���z�m�������@���쏗�w�@��w���u�t |
|
| ��2006�N2��20���u�������l�ɂ₳�����܂��Â���u����v���������z�w���ێ�Â̏��^ | |
�@���݁A�n�[�g�r���@�A��ʃo���A�t���[�@�Ȃǂ̖@�������i�݁A1973�N����7�s�s���������f���s�s�錾�����������̂܂����v���o���Ɗu���̊�������B2001�N�v�g�n����ł̍��ۏ�Q����ICIDH�i1980�N��`�j�̉��肪�������肳��A���ۏ�Q���މ�����ICF�Ƃ��ď��F���ꂽ�B���␢�E�́A�l�̑�������Ƃ��A�����ʂł����j�o�[�T���f�U�C���ւƈڍs���悤�Ƃ��Ă���B���̏̒��ŁA�o���A�t���[���烆�j�o�[�T���f�U�C���ւ̗��j�����B |
|
| �L�[���[�h�F�P�l�f�B�哝�́E�S�[���h�X�~�X�E�o���A�t���[�E���j�o�[�T���f�U�C���EICIDH����ICF�ցE�{�s�� |
|
| �P�D�o���A�t���[�̋N�� | |
�@1950�N�㏉�ߖk��������ꂽ�m�[�}���C�[�[�V�����̔g�ɂ̂�1961�N1��21���A�����J���O��35��哝��J�EF�P�l�f�B�͏A�C�����̗����A���N�푈�̏��w�R�l�ɑ��Ă̐���Ƃ��ăo���A�t���[�@�āi�č����z��@ASA�j�𐧒肷��B �@����ASA����ɂ��āA�C�M���X��1963�N���l�̖@�K�𐧒肷��B���̖@�̐���Ɋւ�����S�[���h�X�~�X���͂��̔N�ɁuDesigning for the Disabled�v���o�ł��Ă���B �@���̖{�����{�̃o���A�t���[�̂��������ƂȂ�̂ł���B(1974�N2�Ł@�|��B1981�N���{���z�w��̏��قŗ���) |
|
| �Q�D���{�ɂ����� | |
�@64�N���n�r���e�[�V�����w��ݗ����������I�����s�b�N�̌�̃p�������s�b�N�ł͑傫�ȃV���b�N�����B�O���I��̎ԃC�X�Ɠ��{�I��̂���Ƃ��S�R�Ⴄ�̂��B�܂�ŃX�|�[�c�J�[�ƌy�g���b�N�̂悤�ɁB �@70�N�S�[���h�E�X�~�X���O�f�̒������킪���̃��n�r���e�[�V�����̃��b�J�ł����B�J�Еa�@�̓����̉@���V�����a�搶�ɂ���Ĉꕔ�|��A���{�Ƀo���A�t���[�����߂ďЉ���B �@�{�l�̓w�͂ƁA��ÃX�^�b�t�̔M�ӂɂ���ă��n�r���e�[�V�����P�������Ă��A�Љ�A�ǂ��납�ƒ땜�A�����܂܂Ȃ�Ȃ�������A�����̉��P���}���ł���ƁA���z�E�փA�v���[�`���ꂽ�̂ł���B �@���̍��́A��w�̌������Ȃǂł̌����̎���ŁA���X�ɂ��̐��ʂ͕��ɂȂ��ďЉ��Ă����̂ł��邪�A�܂��o���A�t���[�Ƃ������t�͈�ʎЉ�ɂ͒m���ĂȂ������B �@�����̕Ƃ���72�N���{���̕s���R������́A�u��Q�҂̐������̌����T�A�ԃC�X�g�p�҂̐������v�s����B �@73�N�������N�Ƃ�ꂽ���Ƃ͎��m�̒ʂ�ł���B���̔N�k��B�s���܂ސ���7�s�s���u�������f���s�s�v�錾������B���̍�����u����Љ�v�Ƃ������t�����Ƃ̒��ŗp����ꂽ�B�Z��s�s�������c�͂��̔N�Ɍ��c�Z��̐ݔ���������Ҕz���Ƃ���ƂƂ��ɁA����ɂ���đ��z�ƂȂ�H����Ɋւ��Ă͕⏕�̑ΏۂƂ��铙�A�o���A�t���[�̑Ώۂ��g�̏�Q�҂��獂��҂ւƍL���钛�������邱�Ƃ��ł���B �@74�N���c�s�͑S���ɐ�삯�āu�����s�s������v���쐬����B �@75�N�s���g��Z���^�[�ɏZ��������k�������J�݂�����匚�z�w�Ȃ̖쑺���搶���S�����ꂽ�B �@���̍����猚�ݏȂ̐g�̏�Q�҂̗��p���l�������v������A�S�����z����́u���q�w�ɂ�����g��ݔ��̌����v���e�Ȓ��̃o���A�t���[�Ɋւ���ϑ��������|�[�g�����w����n�߁A���ɏo�Ă���悤�ɂȂ�A�o���A�t���[�̍l�������������̒������ʎs���̐����ւƊ��p����n�߂�B �@�F�{�ɂ͎ԃC�X�g�p�Ҍ����̃n�E�X���[�J�[�ɂ�郂�f���Z����Ă�ꂽ�B �@�e�n�������͕̂����s�s��ڎw���A�����x�̌��������܂߂āu�����s�s��������v���쐬���A���s���n��81�N�̍��ۏ�Q�ҔN�ɖk��B�s�����s�������_�ł�40���s�s�����s����܂łɂȂ��Ă����B �@80�N���{���z�w��ɂ����āA�n���f�B�L���b�v���ʈψ���݂�����Ƌ��ɁA���w��ɂ��u���z�v�����W���v�̒P�ʋ�Ԃ̍��ɎԃC�X���g��W�̎������W������A���s�����B(�����̍��Ɏ{�H�����e�B) �@81�N���z�w��̓S�[���h�X�~�X���������u���Ƃ̂��߂̃o���A�t���[�Z�~�i�[�v���J�Â���B �@82�N�ʎY�Ȃ̈ϑ��������{���̕s���R������́A����ҁA�g�̏�Q�҃P�A�V�X�e���̊J���ɂ��ĕ����o�B����҂��g�̏�Q�҂ɉ����Ĉ�ʌ��z�̒��Ɉʒu�Â�����悤�ɂȂ����̂͂��̍�����ł���B �@86�N�����Ȃƌ��ݏȂ̘A�g�ɂ��ł��o���ꂽ�u�n�捂��ҏZ��v��(�Z�݂悢�X�Â���)���i���Ɓv���n�݂����B �@89�N(�������N) �����Ȃ͑呠�ȋy�ю����Ȃ̍��ӂ̉��Ɂu����ҕی��������i�\���N�헪(�S�[���h�v����)�v���쐬����B �@���̍���薯�Ԋ�Ƃɂ��u�ƂÂ���u���v�̒��ɁA�ԃC�X�g�p�҂⍂��҂ɑ���Z��Ƃ��Ēi���̂Ȃ����ʁA�����˂�萠���A�o���A�t���[�̍l�������������悤�ɂȂ��Ă���B �@�����h�C�c�����90�N�A�č��ł`�c�`�@(�č���Q�Җ@)�����肳�ꂽ�N�A�u����҂̏Z����z���k�}�j���A���v���S���Љ�����c���S���̎Љ�����c��ɔz�z���ꂽ�B�������Z����Z���ɂ́u����Ή��Z��t�H�[���}�j���A���v���쐬�B���N�A����ґΉ��\���H�������Z�����x�𐧒肷��B �@94�N�S�[���h�v�������ԔN�������̔N�n�[�g�r���@�����肳���B ��95�N��B���̃n�[�g�r���@�K�p�����e���[���f���I�[�v�������B���N�A�o�k�@�����肳��A�č��ł́A�������C�X�炪���j�o�[�T���f�U�C�������B �@96�N�Z����Z���ɂ́A�Z���̑Ώۂɍ���ґΉ��\���H���i�o���A�t���[�j��t��������B���̎�������A�}�j���A����K�C�h���C���̐������i�݁A�S�̂̒�グ���v��ꂽ���A���̌㐔�N�A���肪�}�j���A������Ɋׂ��ė��p�ҕs�݂ɂȂ��Ă���Ƃ����w�E���o���B�����ɁA�z�藘�p�ґw���L�����đ��l�ȃj�[�Y���o�Ă������Ƃŏ]���̂悤�Ȓ�ǂ���̍����̌��E���M�킹���B�������Ȃ���A�o���A�t���[�Ƃ������t�͎s�����������B �@98�N���ی������ɂނ��āA�P�A�}�l�W���[�̐V�݁B �@2000�N���ی������̔N�A��ʃo���A�t���[�@�����肳���B����ɁA�u�Z��̕i���m�ۂ̑��i���Ɋւ���@���v���{�s����A����Ɋ�Â��u�Z��\�\���v�����x�������B �@04�N��Q�Ҋ�{�@����������A���ʋ֎~�������lj����ꂽ�B �@������05�̍�N��Q�Ҏ����x���@����������A���ی����������ꂽ�B �@���N�́A��ʃo���A�t���[�@�ƃn�[�g�r���@�̌��s2�@�������u����ҁE��Q�҂̈ړ��~�������i�@�āi���́j�v�Ȃ�V�@�Ă��A�����Ȃ͔N���{�s��ڎw���Ă���B |
|
| �R�DICIDH����ICF�� | |
�@01�N�{�����e�B�A���۔N�̔N�AWHO���u���ۏ�Q���މ����Łv������BICF�̊T�O�ɂ����ẮA�����Ƃ���𗘗p����l�X�����ڂ�������Ă��镔���͑�Q���̔w�i���q�ɊY������B �@�����Ɖ���鑤�Ƃ́A�����q�ɂȂ�A�����ė��p���鑤�̐l�X�͌l���q�ɕ��ނ����Ƃ��Ă���B �@ICF�̊T�O��\�P�Ɏ����B �@���̕\���Ӗ����邱�Ƃ́A�Љ�o���A�t���[�ɂȂ邱�Ƃɂ���ď�Q�҂��Q�����Ă��邩�A��Q�҂��Љ�ɏo�ăo���A���w�E���A�o���A�t���[�Љ�ł���̂��A�����ċv�����g�Љ�悩�����҂��悩�h�́A�Â����̐V�����������@�̂Ă�����ƂȂ�̂ł���B ��1�j�����ŁAICF�̌l���q�ł̕��ނƂ��Ă͊܂܂�Ă��Ȃ����A���̈��q�̊֗^�́A���܂��܂ȉ���̌��ʂɂ��e��������B |
|
| �S�D�{�s�Ⴉ��w�ԃo���A�t���[ | |
�@���r��Q�҂����Ȃ̏�Q�������I�Ɏ�e�ł��邩�ۂ��́A�Љ�A�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��B �@��Q��e�̊T�O�́A�g�̓I�A�Љ�I�A�S���I��3�̑��ʂɓK�p�����Ƃ����B�g�̓I�ɂ͖{�l����Q�̐����₻�̌����A�����ǁA�\��ɂ��Ă悭�m�邱�Ƃł���A�Љ�I�ɂ͎��Ȃ̐E�Ƃ�Z����Ƒ����̑��Ɋւ��Č����I�ł��邱�Ƃ��Ӗ����A�S���I�ɂ͎��Ȃ̏�Q�Ɋւ��ĂЂǂ���I�ȏǏ�������Ȃ����Ƃ��Ӗ�����Ƃ����B �@���̒i�K��4�̉ߒ�������Ƃ���Ă���B(�X���C�h�Q��) �@��Â̐i���ɂ����@���Ԃ��ȑO�Ɣ�ׂ��Ȃ�Z�k����A���҂̎Љ�I�A�S���I���ʂ��ǂ����Ȃ��̂�����ł���B �@�Z������Ɋւ��Ă��A�����҂̈ӌ����ɂ��{�l�ɂƂ��ĉ����ǂ��ĉ��������̂������f�ł��Ȃ��̂��ʏ�ł���B���̂��߂ɂ��A�ʏ�̐v �^�������X�g�ɁA�t�����ׂ��^�������X�g������B(�X���C�h�Q��) �@�����҂��ł��邱�ƂƂł��Ȃ����Ƃ������o�����̂ŁA�ł��Ȃ����ƂɊւ��Č��z�I��Ă����݂邽�߂̃��X�g�̈��ł���A��Q�i�s��̃t�H���[�Ǝ��̃N���C�A���g�ւ̎����Ƃ��ĎQ�l�ɂ��Ă���B �@�`���ɏq�ׂ��悤�ɍ�����30�N�O�Ɣ�ׂ�Ɗu���̊�������B �@�����̏�Q�҂����p�ł��錚���������Ă������Ƃ́A�{���Ɋ�����B������A��Q�ҁA����҂݂̂Ȃ炸�A�I�X�g���C�g��q�ǂ��ւ̔z���ȂǁA���i�K���炳��ɔ�A������l�X�ɂ₳�����g���₷�����̂��A��葽���̒m�b���W�߂đn���������Ăق����Ǝv���B �@3�N�O�ؑ��ݗ��H�@�ł������v�H�������A�v�ɂ������Ă͖{���E�[�����E��k��فE�ɗ��܂Ńo���A�t���[�ɂ��ė~�����Ƃ��Z�E����˗����ꂽ�B�o���A�t���[�A�����ă��j�o�[�T���f�U�C�����܂��ɍL�܂��Ă������ŁA���Ɏ��@�܂ł��̔g���������Ɗ��S�[���������̍��ł���B���ׂĂ̐l�ɑ��āA�l�ԂƂ��Ă̊�����W���Ȃ����j�o�[�T���Y���́A�����܂ōL�����Ă��Ă���̂ł���B |
|
| �⑫�����@�s�n�s�n�ʐM�ʍ�2001�~28�Ńh�L�������g �㓡���d�@�@�����@��(��)�L����`�� |
|
�\�P�@�����J���ȎЉ�E����Ǐ�Q�ی�����������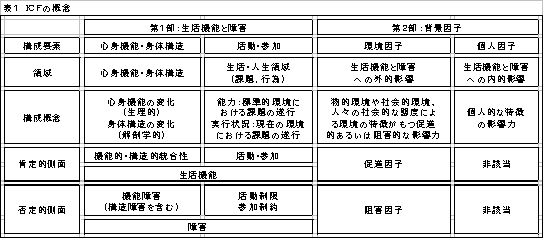 |
![]() �@�����̏Љ��@
�@�����̏Љ��@![]() �@�[���E�E����N�@
�@�[���E�E����N�@![]() �@�J�Ёi�J���ЊQ�j�W
�@�J�Ёi�J���ЊQ�j�W
![]() �@�o�O�����u���@
�@�o�O�����u���@![]() �@�Ԃ����_���X�@
�@�Ԃ����_���X�@![]() �@�o���A�t���[�ނ�N���u
�@�o���A�t���[�ނ�N���u
![]() �@���N���G�[�V�����@
�@���N���G�[�V�����@![]() �@�L�u�킾���v�@�@
�@�L�u�킾���v�@�@