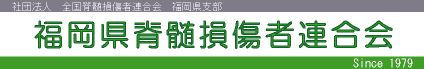
| 憲法施行六〇年と障害者の人権 文化体育部長 久保 親志 |
|
今年の五月三日は、「日本国憲法」施行六〇年で、人間でいえば正に還暦ともいうべき節目に当たります。思えば、戦後の障害者運動は憲法と共に歩み、憲法と共に闘った歴史です。そこで、憲法について少し考えて見たいと思います。 障害者は、戦前・戦中期には軍人になれない為に、「非国民」的な扱いを受け、穀潰しと揶揄されました。また、戦後の混乱期には足手まといと、「厄介者」扱いをされ、更に、高度経済成長期には仕事が出来ない役たたずと、「落伍者」のレッテルを貼られ、地域や職場から排除され続けて来たのです。当然、その人権と暮らしは十分に守られていなかったわけです。 そのような、私たちが「障害者は障害者である前に一人の人間であり、自由かつ平等な存在である」との、大前提に立ち、市民的権利を求める運動を開始したのは、日本国憲法の公布・施行に端を発しています。何故ならば、憲法の究極の目的は「個人の尊厳」を確保することにあるのだからです。 人は、全て生命を与えられて生きており、その一人ひとりは何ものにも変えがたい、かけがいのない存在なのです。そして、一人ひとりはみんな個性を持った独立した人格として尊重されるべきなのです。このように個人を人間として一人ひとりを大切にして行こうという考え方が「個人の尊厳」という考え方であり、日本国憲法のよって立つところであり、基本的な考え方となっているのです。そのことは、第一三条に「すべて国民は、個人として尊重される。」と明定されていることからも分かります。 また、この個人の尊厳から派生して来た原理として、自由主義、民主主義、平等主義、福祉主義そして平和主義があり、この派生原理のことを「憲法原理」と呼んでいます。つまり憲法とは、「個人の尊厳の確保という究極の目的を達成する為に、自由主義、民主主義、平等主義、福祉主義、平和主義の憲法原理を各条文の形で具体化した法である」といえます。これが、憲法の基本構造です。 この基本構造は、大きく二つの体系に分類出来ます。先ず、国民の権利及び義務を定めた「人権体系」。次に、立法・行政・司法の各国家作用を定めた「統治体系」です。この二つの体系は共に、憲法の具体化であり、実定化ですが、もともと憲法は国家権力の濫用による個人への人権侵害を防止し、人権を保障する為に生まれた経緯があります。 従って、「人は人であるというただそのことのみにより、人としての尊厳が守られるべきであり。また、人は自分自身で自己の生き方を決定し、自らの意思に従って幸福を追求することが出来る」という原理と直結する「人権体系」が憲法の中核なのです。 つまり、どんな人にもこの世に「代役」はいないのであり、私たち一人ひとりが独自の個性を持ち、人格を持ち、そして価値を持った「主人公」だという考えが憲法の中心にあるということです。当然に障害の有無、家柄、国籍、老若男女を問いません。そこで、この中核となる人権を保障する為に、「統治機構」のシステムが必要となって来るわけです。要するに、人権保障の規定が「目的」で、統治機構の規定はその為の「手段」であるということが出来ます。 以上が、日本国憲法の基本構造であり、人権規定と統治規定を明文化して、個人の尊厳と自由を守って行くべきことを明確にしました。が、それだけではまだ不十分です。そこで、もし人権侵害が発生した場合、これを事後的に救済する「人権の砦」が必要です。これが、憲法訴訟といわれるものです。 この日本国憲法施行六〇年の機会に、憲法前文に定める「平和のうちに生存する権利」について、今一度考え、その理念が「暮らしの中で実現」出来ることを願っています。 |
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」