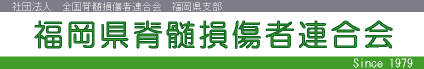
| バリアフリー点検活動 1 2 3 4 5 6 7 ページ | |
| バリアフリーになったJR小竹駅を利用して | |
| 日時 2003年10月11日(土) 場所 JR福北ゆたか線 JR小竹駅~JR博多駅 |
|
 平成12年11月より交通バリアフリー法が施行され、筑豊地区ではおくらばせながら小竹駅が新飯塚駅に続いて2番目のバリアフリー駅になりました。小竹駅は、交通バリアフリー法が定める一定規模の旅客施設(1日の利用者数が5,000人以上であること)に適応されない1日の利用者数が5000人に満たない小さな駅ですが、小竹町町長の公約によりエレベーター2基の総工費約1400万円は、小竹町が負担して完成しました。 平成12年11月より交通バリアフリー法が施行され、筑豊地区ではおくらばせながら小竹駅が新飯塚駅に続いて2番目のバリアフリー駅になりました。小竹駅は、交通バリアフリー法が定める一定規模の旅客施設(1日の利用者数が5,000人以上であること)に適応されない1日の利用者数が5000人に満たない小さな駅ですが、小竹町町長の公約によりエレベーター2基の総工費約1400万円は、小竹町が負担して完成しました。 10月11日(土)に実際に利用してみてどうなのか点検もかねて小竹駅から博多駅まで利用しました。新しい小竹駅は、遠賀川沿い旧200号線の御徳大橋の横に移転されていました。 10月11日(土)に実際に利用してみてどうなのか点検もかねて小竹駅から博多駅まで利用しました。新しい小竹駅は、遠賀川沿い旧200号線の御徳大橋の横に移転されていました。 駅に通じる経路はバリアフリーになっていて、駅構内も完全フラットです。ホームと駐車場へ行く2基のエレベーターは正面から入り反対側のドアから出るエレベーターです。そのままの向きで出られ回転する必要がないためなのかエレベーター内はリクライニング式電動車イスがギリギリ入る位の狭さです。ホームの高さは電車と同じ高さになっていましたが、ホームと電車間で10㌢くらいの隙間があり電動車イスの大きめのキャスターでも前進すると落ち込む可能性があるために介助者に後ろ向きに真っ直ぐに引いてもらい乗り込みました。2両目の前の方に車イス使用者用スペースがあり、そこに乗車して博多駅へ向かい、目的地で用事を済ませ折り返し小竹駅に戻りました。新しい小竹駅は、利用する前に”気が重くなる”バリア(障壁)だらけの駅と違い、車イス使用者が気軽な気持ちで利用できる駅に変わっていたことを報告します。 駅に通じる経路はバリアフリーになっていて、駅構内も完全フラットです。ホームと駐車場へ行く2基のエレベーターは正面から入り反対側のドアから出るエレベーターです。そのままの向きで出られ回転する必要がないためなのかエレベーター内はリクライニング式電動車イスがギリギリ入る位の狭さです。ホームの高さは電車と同じ高さになっていましたが、ホームと電車間で10㌢くらいの隙間があり電動車イスの大きめのキャスターでも前進すると落ち込む可能性があるために介助者に後ろ向きに真っ直ぐに引いてもらい乗り込みました。2両目の前の方に車イス使用者用スペースがあり、そこに乗車して博多駅へ向かい、目的地で用事を済ませ折り返し小竹駅に戻りました。新しい小竹駅は、利用する前に”気が重くなる”バリア(障壁)だらけの駅と違い、車イス使用者が気軽な気持ちで利用できる駅に変わっていたことを報告します。 小竹駅を利用してみて気になる点は、1.小さな駅のために駅員1人体制で窓口から離れられずに乗降の介助は望めないこと、2.車イス使用者用トイレは、男性トイレ入り口付近側しかなく女性の車イス使用者は入りづらいこと、3.ホームと電車間で10㌢くらいの隙間がありキャスターが落ち込む可能性があり簡易携帯スロープが必要なことの3点です。 小竹駅を利用してみて気になる点は、1.小さな駅のために駅員1人体制で窓口から離れられずに乗降の介助は望めないこと、2.車イス使用者用トイレは、男性トイレ入り口付近側しかなく女性の車イス使用者は入りづらいこと、3.ホームと電車間で10㌢くらいの隙間がありキャスターが落ち込む可能性があり簡易携帯スロープが必要なことの3点です。 小竹町では町長の英断でエレベータ2基の設置にかかる費用千数百万円を町で負担して、全ての市民が駅を気軽に安心して利用出来るようになりました。そのことを考慮すると、対費用効果も充分あり、移動の自由の保障の観点から各自治体にある主要駅にはエレベーター設置費用を自治体が負担すべきだと思います。(藤田 忠) 小竹町では町長の英断でエレベータ2基の設置にかかる費用千数百万円を町で負担して、全ての市民が駅を気軽に安心して利用出来るようになりました。そのことを考慮すると、対費用効果も充分あり、移動の自由の保障の観点から各自治体にある主要駅にはエレベーター設置費用を自治体が負担すべきだと思います。(藤田 忠)(広報誌「わだち」No.121より) |
| 大野城市コミニティーバス 「まどか号」について |
|
 2004年2月23日大野城市市会議員瀬戸氏と私達とで私達が常日頃抱えている問題について話をする機会をもってもらいました。そこで、いろいろな問題がでたのですが、大きく取り上げた問題の一つが大野城市のコミニティーバス「まどか号」が車イス使用者が乗るには問題が多いと言うことでした。 2004年2月23日大野城市市会議員瀬戸氏と私達とで私達が常日頃抱えている問題について話をする機会をもってもらいました。そこで、いろいろな問題がでたのですが、大きく取り上げた問題の一つが大野城市のコミニティーバス「まどか号」が車イス使用者が乗るには問題が多いと言うことでした。 早速瀬戸議員より実際委託運営をしている西鉄の子会社「西鉄バス二日市株式会社月の浦支社」にアポイントを取ってもらい、2月26日、月の浦支社で支社長、運行責任者、運転手の方々、瀬戸議員、そして私達車イス使用者4名(大型電動車イス利用者も含む)及びその付き添いの家族の方とで、予備においてある「まどか号」に実際乗ってみて、そして車を敷地内で運行してもらいさまざまな問題を検証いたしました。 早速瀬戸議員より実際委託運営をしている西鉄の子会社「西鉄バス二日市株式会社月の浦支社」にアポイントを取ってもらい、2月26日、月の浦支社で支社長、運行責任者、運転手の方々、瀬戸議員、そして私達車イス使用者4名(大型電動車イス利用者も含む)及びその付き添いの家族の方とで、予備においてある「まどか号」に実際乗ってみて、そして車を敷地内で運行してもらいさまざまな問題を検証いたしました。月の浦支社では、バス約100台、運転手52名(女性2名)体制で、一般車両と、大野城市よりの委託「まどか号」と、春日市の委託「弥生号」の3種類のバスがローテーションを組まれて運行されている。その上「まどか号」の車イス乗り口は横から、「やよい号」の車イス乗り口は後方から。当然、「まどか号」と「弥生号」は車イスの乗せ方も違うし固定方法も違う。当然運転手は固定ではない、毎回違う運転手が乗務。問題がでるのは当たり前である。 検証の結果次のようなことが判明いたしました。  月の浦支社長より回答があり、運転手の再教育を早急に実施する。また、今後定期的に車イスの乗せ方について教育を実施していくとの事。 月の浦支社長より回答があり、運転手の再教育を早急に実施する。また、今後定期的に車イスの乗せ方について教育を実施していくとの事。※瀬戸議員より大野城市の担当責任者に今日の状況を連絡しておくとの回答をもらいました。 今後の取り組みとして (広報誌「わだち」No.123より) |
| 「大野城市コミュニティバス「まどか号」の問題点及びその改善についての要望書 そして、要望書について大野城市からの回答書」 |
|
 先般「わだち」4月号で大野城市コミュニティバス「まどか号」の車イスで乗ったときの諸問題について報告いたしましたが、5月24日大野城市を訪問、書面にて要望書を提出いたしました。その結果、6月22日に大野城市建設部 都市計画課より2名担当の方が福脊連福岡事務所へ来室、書面にて回答書をもらいました。 先般「わだち」4月号で大野城市コミュニティバス「まどか号」の車イスで乗ったときの諸問題について報告いたしましたが、5月24日大野城市を訪問、書面にて要望書を提出いたしました。その結果、6月22日に大野城市建設部 都市計画課より2名担当の方が福脊連福岡事務所へ来室、書面にて回答書をもらいました。内容については、もう少し改善の余地はないのか??と少々不満の個所もありますが、今後の問題として一番大切なことは、このようなバスが運行される前に、あるいはコミュニティバスが出来る前に、私たちの意見をもっと取り入れられるよう各市町村に働きかけを行うことがいかに大切かと痛感いたしました。今後のわれわれの問題として、要望書、そしてその回答書を報告いたします。(中野 拓生)  回答 コミュニティバスの運行事業者に対しては、運転手が車イスの乗降介助、固定を円滑に行うよう指導しております。しかし、時間がかかる場合があるとのご指摘を受け、大変恐縮しております。今後は西鉄に対し、出来るだけ5分以内で乗車と車イスの固定が出来るように、運転手の研修の徹底を指導いたします。 回答 大野城市では、やさしさとふれあいのコミュニティ都市を目指しており、誰もが利用しやすいバスになるような雰囲気づくりが必要であるとの考えから、人権感覚に富んだまちとなるよう啓発活動を行っております。このことから、今後とも地域と協力し、人権感覚に富んだ街づくりの取り組みを進めてまいります。なお、バス車内の音声アナウンスにおいて、次のとおりアナウンスしております。「お客様にお願いします。車イスの方の乗降の際には、数分間バスを停車しますので、ご協力をお願いします。」また、実際に車イスの方の乗降の際には、運転手が乗客の皆さんに同様のアナウンスを行っております。  回答 雇用機会均等の考え方から、女性の運転手も増えております。重量が大きい車イスの移動介助も出来るだけ円滑に出来るよう、研修の徹底を指導いたします。しかし、運転手だけでは移動介助が困難な場合は、乗客の皆さんにご協力をいただくことも考えられます。地域のバスとしてみんなで協力し合うことも大切なことと存じますので、そのような啓発も行っていきたいと存じます。 回答 バス車両販売会社に問い合わせたところ、引き出し式スロープ、電動ワイヤー式固定装置のいずれにつきましても、設置するためにバスを改造する場合は、床下については機材の都合上、困難であるとのことでした。また、床の上部については、固定装置を取り付けた場合、床(乗降口)との段差が生じるため、傾斜を付けて床(乗降口)に擦り付けることとなり、高齢者の皆さんなどの円滑な車内移動に不都合が生じる恐れがあります。このことから、本市では電動ワイヤー式固定装置等の設置は困難と考えております。重ねて申し上げますが、円滑、適切、そして短時間で車イスの乗車及び固定が完了するよう運転手の研修の徹底を指導してまいりたいと存じます。  回答 大野城駅は、大野城市の玄関口の一つであり、市交通バリアフリー基本構想においてもバリアフリー化を推進することとしております。具体的には、平成18年度までに東西の駅前広場と駅改札口を結ぶ自由通路(大野城市道)の東西にエレベーターを各1基設置することとし、現在事業を進めております。なお、改札口からホームにかけてはJRの管轄になりますが、是非ともエレベーターを設置するようJRに対して働きかけを行っております。 (広報誌「わだち」No.126より) |
| 公共交通機関を利用して | |
総会から、一週間後の2004年5月2日(日)、天気予報では午後から雨が降るという薄曇りの朝10時から下川さんと二人で九大病院に入院している友人のお見舞いに出かけました。行きはJR小竹駅から吉塚駅まで行って、帰りは地下鉄を利用して、九大病院前から博多駅まで行って、博多駅からJR小竹駅へと帰って行きました。 考えてみると福北ゆたか線が電化されたときのバリアフリー点検以来、公共交通機関利用は利用していなかったなと思い、久しぶりの各駅停車の旅に少し、ドキドキワクワクするような気持ちでした。 まず、小竹駅からはエレベーターがあるのでホームまで行き、ホームと列車の段差はフラットということもあってか、自分達だけでホームまで行きました。列車が来ると私にとってはそんなに段差を感じることはありませんでしたが、手も少し不自由な下川さんにとっては少し介助していただかないと大変でした。でも、そういうときは結構、他のお客さんが手伝ってくださったので、無事に乗り込むことが出来ました。 吉塚駅では駅員さんが待っててくださいましたが、列車から降りるときは先程と同様にお客さんが手伝ってくださり、駅員さんにはホームから改札までのエレベーターへと案内していただきました。帰りは、一応、来た道を戻る途中で地下鉄の駅を見つけて、では、こちらから博多まで行ってから帰りましょうということで地下鉄の馬出九大病院前から博多駅まで行きました。途中、中洲川端で乗り換えがありましたが、各駅でエレベーターを利用しながら、駅員さんたちが乗り降りのさいに付いててくださり、博多へと無事に着くことが出来ました。 さて、JR博多駅から小竹駅までの道のりですが、エレベーターも出来て、確かバリアフリー点検の時は使用しませんでしたが、エスカルという昇降機があるはずだと思いつつ、小竹駅までの切符を買って、女性の係員の方が駅員さんに説明されているとき、その駅員さんが「ワアッ」とどうしようといった感じの大きな声で叫ばれていましたが、とりあえず改札からエレベーターまで一度上がりホームまで行こうとしたとき、駅員さんが4、5人くらいおられ、「もしかして人海戦術かな?」と思いきや階段の傍らを見ると少し埃をかぶったようなエスカルがちゃんとあり、「これ使えないのですか?」と尋ね、下川さんも「使った方がいいですよ」と言ってから、かけてあった布が取り外され、エスカルを使用することになりました。 これで付いてくださる駅員さんも2人になり、使い方が不慣れのようで下川さんの時は、後ろ側になる落下防止の支え板を乗る方へ倒されており、下川さんが乗ってから気付かされて、乗り直してからホームまで行き、私の時は乗り込むときのスロープ板を降ろされるときに、あの叫び声をあげた駅員さんの足下に当たり痛そうに飛び跳ねられて、もう一人の駅員さんには何やってんだかという感じで見られていました。私も痛い思いまでして一生懸命してくださっているのにと思いつつも、ちょっぴりおかしくて笑ってしまいました。(ごめんなさい…。)そして、そのすごくいいキャラの駅員さんのいる博多駅をあとに小竹駅へと帰路につきました。 総会の折、北九州支部の白川さんがこの時にJRを使ってクローバープラザまで来られていて公共の交通機関も利用しようと言われたのを機に、この日の体験で確かにエレベーター等、乗降のさいには便利になったものの、まだ少し手伝っていただかなくてはいけなくて、ご面倒をかけたりもするけれど、自分達が利用して行かなくてはみんなでしてきた活動が無駄になるし、係りの方の器具の扱い方の不慣れもまねいてしまうのではと感じました。帰りの列車の中で下川さんも「以外と車より疲れないかも…。」と言われたりして、結構、道中は楽しい一日でした。これからも出来るだけ公共交通機関を利用したいなと思っています。 皆さんも多いに利用してみませんか!車では味わえないひとときを得られるかもしれませんよ…! (安部 佳代子) (広報誌「わだち」No.124より) |
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」