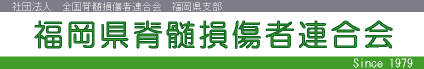

| バリアフリー点検活動 1 2 3 4 5 6 7 ページ | |
| 八女商店街バリアフリー点検に参加して | |
|
去る1999年5月8日、障害者も高齢者も安心して暮らせるまちづくりを目指し、誰もがもっと住み良い街をつくる一つのきっかけになればという事で、住環境の問題を実際に障害者の視点に立って体験し、地球市民全てが安心して暮らしていける環境の整備について考え、街づくりの一環として取り組むことを目的とした八女青年会議所(JC)主催の「住環境フェスタ『共生』の根付いた環境を求めて」が開催され、八女市の共同作業所「ふくし邑(むら)」より依頼を受け、堤氏と私が参加した。 まず朝9時に集合地の八女公園にて開会式の後、障害者・ボランティア・八女JC会員の混成チーム(9名前後でその内車イス5〜6台)が8チーム編成され、八女JC会員にも障害者の視点に立ってもらう為に車イス体験をしてもらい、それぞれ決められたコースに従い八女市商店街へバリアフリー点検に繰り出した。 それぞれのチーム単位で店の入り口や店内の通路・横断歩道などをチェックしながら買い物(昼食時の飲物など)をして帰るというものでしたが、実際には斜面になった歩道や、排水の側溝にキャスターがはまり込んだり、車に進路をふさがれ、やむなく危険な車道を通る等四苦八苦の連続でした。又、商店の通路もせまく入ったもののバックでしか出れないもの・ショーウインドウのガラス戸や棚を割らないように注意が必要等と「ふだん気にも留めていない事が、こんなに障壁になるなんて」と八女JC理事長は驚いていた。 バリアフリーの点検の後、八女市役所前に集まり車イスの介助の仕方について山下恭平氏より説明があり実際に階段の上り下りの体験も行い、ボランティアの方や八女JC会員も熱心に聞き入っていた。 午後からは、八女文化会館に於いてパネルデスカッションが行われ、パネリスト5名が意見交換。八女商店街会長は「これからは地域で何事も済ませる利便性が必要になってくる。今は苦境の中心商店街に再び光が当たる時代は必ずくる。その為にもバリアフリーは進めていかなければならない。」と強調し、又、同JC会員もバリアフリー推進に積極的に取り組む事を確認した。(田中 秀樹) (広報誌「わだち」No.95より) |
| 第2回筑豊支部バリアフリー点検 | |
|
まずはじめに昨年の飯塚市で行ったバリアフリー点検の要望書提出後を報告します。一番問題のコスモスコモン近辺の、歩道を取り囲み車イスの進入を拒むような、お堀状の溝は段差が無くなり、それからバスセンター周辺の視覚障害者用床材(点字ブロック)は弱視の方にも識別しやすいように周囲の床材と明度差の大きい黄色に塗装してもらい、西鉄バスセンターの入口は段差解消してもらう等、八割方改善してもらいました。 そして五月九日(日曜日)に、超高齢化社会を迎える現在、誰もが安心して暮らせる福祉のまちに変えていこうと第二回バリアフリー点検を行いました。十時にJR直方駅待合室に参加者(当事者十一名・ボランティアや家族十四名)が集合して、まず自己紹介を行いました。それから鉄道を利用するうえで最大のバリアは高架橋です。そのバリアを無くし事前連絡などしなくてもいいよう気軽に鉄道を利用出来るように、JR直方駅にエレベーター設置の要望書を提出しました。 |
|
  |
|
ここから点検の開始です。ふるまち商店街を通り直方市役所までのコースです。駅構内の券売機では、手を伸ばさなければ使用率の高い一番上のボタンには手が届きません。直方駅では車イスで入れるスロープが端にしかなく、玄関で降車すると遠回りしなければなりませんし、車イストイレは改札口の中しかありませんでした。 |
|
 |
|
それからふるまち商店街入口の溝蓋(グレーチング)は、キャスターが落ち込まない目の細かい溝蓋になっていて少し安心しました。それで駅周辺すべてに期待しましたが、他の溝蓋は目の大きい溝蓋で、車イスのみならずベビーカーにも危険でした。買い物し易そうな店は甘く見ても3割程度で、店の人によれば店舗の床の高さを通りより上げておかないと集中豪雨の時に浸水するそうです。そのために入口をスロープ状にしても傾斜がきつくなります。これではどうしても、あらゆる意味で買い物がしやすい郊外型の大型店に行ってしまいます。商店街内の三つの銀行は大理石で出来て滑りやすく斜めにのぼっていくきわめて危険なスロープだったり、スロープの角度が急だったり、スロープが全くなかったりのひどい状態でした。 |
|
 |
|
そして市役所付近では施工時期によって、点字ブロックの色が黄色から突然歩道の床材と同色になっていて景観ばかりを重視して、何で点字ブロックが必要なのかという視点が欠けています。唯、作ればよいと言うものではありません。帰りは歩道を通り直方駅まで帰りました。警察署前の横断歩道で歩道に上がるさいに五センチ位の段差でHさんが車イスから転倒して街に潜む危険性を一同実感しました。 |
|
  |
|
残念ながら日常的風景になっている、歩道上に車が駐車していて、点字ブロックをまたいでいるので視覚障害者は激突のおそれがありますし、我々は一度車道に降りなければならず危険を感じました。車イス専用の駐車場に健常者が停めるのと同様に、罰則がなければマナーもへったくれもない常識のなさに憤りを感じます。あらゆる所にバリアが存在し障害者当事者が声を出し「福祉のまちづくり」に参加しないことには安全・快適に外出できないと思い、又「福岡県福祉のまちづくり条例」が、平成十一年四月一日より完全施行され追い風も吹いています。そこでまちづくり条例の「整備基準」に沿った形で要望書を提出する事となりました。 |
|
  |
|
|
五月二十五日に滝口・大里・安部・藤田の四人で直方土木事務所に直方市役所七〇七会議室で五項目の要望書を提出しました。1.溝の蓋を細かいものに交換する。2.点字ブロックを黄色に塗装する。3.歩道の段差を二センチ以下にする。4.福祉のまちづくり条例を守る。5.新規事業には障害者団体に報告する。八月末までに文書で回答を聞きに行く予定です。 最後に要望書提出の件でアポイントを取るために電話したところ、はじめのうちは土木課のカウンターで受け取るからいつでも来て下さい。という感じでしたがマスコミも取材に訪れる可能性を告げると、直ぐに係長に電話を代わり部長も呼ばないといけないからと態度が豹変しました。昨年の飯塚土木事務所・係長の「マスコミの方が取材に来るなら部長も呼んでましたのに。」という発言と同じ結果になりました。自分達だけだと係長で適当にあしらって、マスコミが取材に来ると部長も呼ぶというあまりの対応の違いには疑問符がつきます。そしてお役人に染みついた体質を感じました。(藤田 忠) (広報誌「わだち」No.95より) |
| 交通安全点検 | |
去る2000年10月23日(月)八幡西区による交通安全点検が、学園都市である八幡西区折尾の大浦地区で行われた。 当日は朝から小雨が降り 次第に強く成る様な気配に身障者協会へ電話を入れて確認を取る、十数分後、ボランティア協会より回答の電話が入り、様子を伺いつつ予定通り行いますので参加して欲しいとの事、午後1時過ぎ雨の中家内を伴って集合場所に指定された九州女子大学のキャンパス内にある耕雲館なる建物へ出掛けた。 降りしきる雨の中、数人の役所職員が出迎える耕雲館の玄関に車を横付けして下りると、一人の職員が5階会議室まで案内してくれ、午後1時半 オリエンテーションで八幡西区長の挨拶の後、区役所の担当職員から説明とグループリーダーやスタッフリーダーの紹介が有り、グループ毎に一段と強くなった雨の中スタート地点へ向けて用意されたタクシーに乗り込む。小生は4つの班の内Cルートに配属され、スタート地点の九州産業医科大学直ぐ側の交差点から集合場所だった九州女子大学前の交差点迄の約1キロ(雨天の為に縮小された距離)を10人余りでスタートする。 職員の差し掛ける傘の下雨に濡れながらの点検、小生のチェックシートを家内が手にして気になる箇所や問題点を記入する・・・・。全体的にこのコースは点字ブロックが無く側溝の蓋も無い、所々に設置されたグレーチング(溝蓋)は目が粗くてキャスターがはまり易い、又、バス停では歩道が深く切り込まれ 歩道が狭く成った上にバス停のベンチが邪魔をし後ろ側の側溝には蓋が無い、しかも街灯が無いので夜間は特に危ない。横断歩道から歩道へのアプローチは段差や急なスロープが有り、街路樹の根が張り出しては所々凸凹に歩道の舗装を盛り上げている箇所も。やがてゴール地点に辿り着くと耕雲館へ立ち戻り、各班別に点検資料をまとめると拡大した地図に要点を書き込んだメモを貼り、各ルート別にグループリーダーが発表し要望する。八幡西区役所や建設局 折尾警察署等は、今後予算の関係もあるが 検討しつつ徐々に改善していきたいとの返事・・・・ 午後4時過ぎ、雨もすっかりあがった女子大のキャンパス、助手席の家内に気を使いつつもピチピチの女子大生ギャルに目を奪われながら家路に向かった。(石打 憲治) (広報誌「わだち」No.103より) |
| 「高速道路のSA・PAにおけるバリアフリー調査」 に参加して |
|
 全脊連本部の企画で趣旨は、私達障害者にとって欠かす事が出来ないのが自動車ですが、先般バリアフリー法が制定された事に伴いバリアフリーな社会環境が整備される事によって始めて社会に参加する事が可能になります。 全脊連本部の企画で趣旨は、私達障害者にとって欠かす事が出来ないのが自動車ですが、先般バリアフリー法が制定された事に伴いバリアフリーな社会環境が整備される事によって始めて社会に参加する事が可能になります。今回は、会員9名とボランティア5名、総勢14名で九州自動車道上り線の古賀SAで11時〜14時までの3時間に、高速道路のサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)の障害者専用駐車場、スロープ、障害者優先多目的トイレ、売店、レストラン等の出入り口や通路等のバリアフリー調査及び「マナーをまもって!私たちは困っています・・・・」と書かれた啓発ビラを配る啓発活動やアンケートへの記入のお願いを実行しました。アンケート内容については「障害者専用駐車場を知っていますか」の様な一般的なバリアフリーについての認識アンケートです。そして駐車スペースで車イス利用者が乗り降りに際してのドアの開きがこれだけ必要だと言う写真3枚を貼り付けたポスターパネル1枚を提示しました。  当日は11月初めとは言え日差しが強く、風はなく、気温は27℃と夏を思わせるような天気でドライブにでも行きたくなるような絶好日和でした。 当日は11月初めとは言え日差しが強く、風はなく、気温は27℃と夏を思わせるような天気でドライブにでも行きたくなるような絶好日和でした。会員、ボランティア全員の人が汗だくで自分達が行なっている趣旨の説明をメガホンで叫び、目に付く人にはビラを配りアンケートの趣旨の説明をし、そして記入のお願いをしています。この様な事など初めての経験ではなかっただろうか、最初はギコチ無く感じていたが時間の経過とともにたくましくなり、昼食の時期ともなる頃には駐車場から食事に来る人、休憩に来る人達が多くなりましたが、各人が一生懸命に力強く声を出して出入りする人達に近づき説明をして居る姿は自信に満ちていました。また、老若男女とバランス良く話す事が出来ましたし、相手の人から励ましの言葉などを頂き勇気付けられました。 結果として121名の方々からアンケート用紙に記帳して頂きました。そして「頑張って下さい」と声を掛けてもらう場面もあり心から嬉しく思いました。  私達は「高速道路のSA・PAにおけるバリアフリー調査」の計画書が手元に届いてからは、全脊連本部や福岡支部での打ち合わせ、道路公団に書類の提出や施設の使用許可書の手配、当日使う備品のチェック、折りたたみテーブル、折りたたみいすの借り出し依頼等の打ち合わせや電話連絡などと慌ただしく準備に追われた大変な10日間でしたが「手配は万端結果を御覧じろ」です。当日の事を今振り返ってみますと参加者全員の気持ちが一つになり、特にボランティアの人達の協力が無ければ出来なかった事だと実感しています。私達は一人で行う事には限度があり、1人の力は小さなもので多くの事は出来ないと思いますが、数人の人達の力を出し合えばかなりの事は成し遂げる事が出来る事を身を持って学ぶ事が出来感謝しています。(大山 勇雄) 私達は「高速道路のSA・PAにおけるバリアフリー調査」の計画書が手元に届いてからは、全脊連本部や福岡支部での打ち合わせ、道路公団に書類の提出や施設の使用許可書の手配、当日使う備品のチェック、折りたたみテーブル、折りたたみいすの借り出し依頼等の打ち合わせや電話連絡などと慌ただしく準備に追われた大変な10日間でしたが「手配は万端結果を御覧じろ」です。当日の事を今振り返ってみますと参加者全員の気持ちが一つになり、特にボランティアの人達の協力が無ければ出来なかった事だと実感しています。私達は一人で行う事には限度があり、1人の力は小さなもので多くの事は出来ないと思いますが、数人の人達の力を出し合えばかなりの事は成し遂げる事が出来る事を身を持って学ぶ事が出来感謝しています。(大山 勇雄)(広報誌「わだち」No.104より) |
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」