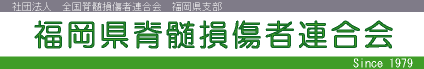
| 出前福祉講座活動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ページ | |
| 平成12年度筑豊高校ボランティア講座 ワークキャンプに参加して |
|
| 日時 2000年7月19日~20日 場所 直方市 直方福祉センター 主催 福岡県立筑豊高校 社会福祉法人 直方市社会福祉協議会 |
|
| 七月十九~二十日の両日、直方福祉センターにて行なわれた筑豊高校ボランティア講座・ワークキャンプに参加させていただきました。 この講座の目的としては、《一泊二日という時間を通して、日常、私たちが知り得ることができない当事者の方々の生活に触れるとともに、これから私たちがともに地域生活を送る上で何かを考える〝きっかけ〟となれば…(プログラムより)》ということで、少しばかり緊張しながらの参加でした。 講座内容として主に一日目は、一時半より、開会式に始まり、ミニ講演①、②と続き、夕食などを済ませて、午後七時半より分散交流会と題して当事者、学生たち(引率の先生、社協の職員さんも交えて)が三つのグループに分かれ、それぞれの課題で話し合いをしました。二日目は、車イス、アイマスクなどの説明を受けて、一日目に分かれた三つのグループで駅前を中心に町を探検ということで車イス、アイマスクなどを使い、実際に学生たちに体験をしてもらいました。  ミニ講演①では、直方市ボランティア連絡協議会・副会長のK・A氏が「ボランティアについて」という演題でご自身や会のこれまでの経緯などを織り交ぜてお話されました。その中では「ボランティアは、何も資格なんて要りません。まず、笑顔からはじめましょう。」そして「笑顔で接することでお互いがお互いを気持ち良く受け入れられる、まず、そういうことが基本としてあるのではないでしょうか。」という感じで話されていました。ボランティアする側はもちろんのことですが、される側もココ一番というくらいの笑顔で接しなくてはいけないなと感じました。また、傾聴するということも言われました。その言葉どおり「耳を傾け聴いてあげると言うことです。型にはまったボランティアではなく、相手の思いを一生懸命にちゃんと聴いてあげられるか、また、そういうふうに聴いてほしいですね。」と言われていました。 ミニ講演①では、直方市ボランティア連絡協議会・副会長のK・A氏が「ボランティアについて」という演題でご自身や会のこれまでの経緯などを織り交ぜてお話されました。その中では「ボランティアは、何も資格なんて要りません。まず、笑顔からはじめましょう。」そして「笑顔で接することでお互いがお互いを気持ち良く受け入れられる、まず、そういうことが基本としてあるのではないでしょうか。」という感じで話されていました。ボランティアする側はもちろんのことですが、される側もココ一番というくらいの笑顔で接しなくてはいけないなと感じました。また、傾聴するということも言われました。その言葉どおり「耳を傾け聴いてあげると言うことです。型にはまったボランティアではなく、相手の思いを一生懸命にちゃんと聴いてあげられるか、また、そういうふうに聴いてほしいですね。」と言われていました。ミニ講演②では、わが筑豊支部・支部長の藤田君が講師として、車イスとなった経緯からその苦しみを乗り越えて今に至るまでの想い、自分自身が今、思っている事などを話されました。今日に至るまでの想いは共感できる部分もあり、また、私よりももっと辛い思いをされてきたんだなと感じさせられました。そんな中でも、「障害者だからかわいそうではなく、ただ、身体が不自由なだけでみんなと同じなんですよ。普通に接してほしい。」と話されたときには思わず、うなずいていました。 後の交流会が終わったあとに学生さんが「最初はどういうふうに接していいのか分からなくて戸惑ったけど、話をしてみると普通なんだと感じました。」というような感想を言ってくれていました。今は以前に比べるとこういうような交流を持つ機会が少しずつでも多くなってきているとは思いますが、お互いにどういうふうに声を掛けたらいいのか分からずじまいにそのまま素通りしてしまうということがあるようです。どちらからかというでもなく自然と挨拶を交わすように声かけができればいいなと感じました。 講演が終わり、夕食までの間に自由時間があり、入浴を済ませたり、おしゃべりしたりと時が過ぎて、緊張の中、交流会が始まりました。まず、講師三人(藤田君、障害者の住みよい風土づくりをすすめる会代表の大久保裕子さん、私・安部)の自己紹介と課題提起(藤田君はバリアフリー、大久保さんは自立生活、私もバリアフリー)をして、それぞれ三つのグループに分かれて話し合いをしていきました。  私のグループは学生四人と社協の職員二人に私と計七人で交流会が始まりました。ドキドキしながら、私はまず、車イスとなった経緯、今までの自分の体験談を話して、質問をどうぞと言ったとき、しばらくは誰ともなく考え込んでいる様子でしたが、職員さんのフォローで少しずつ質問がありました。その中でも車イスでの移動手段は?と聞かれた時にはほとんどが車で電車・バスなどの公共交通機関はあまり利用していません。バスは全く利用していませんが、以前、電車・汽車は何度か利用しました。電車は比較的ホームとの差があまりなく乗りやすかったけれど、汽車はその駅々で段差があったり、なかったりしています。また、エレベーターや昇降機が設置してあるところはホームまで行きやすいんですが、無いところは階段を何人もの手を借りて手伝ってもらわないといけません。また、駅にはエレベーターなどの設置を義務付けするなどの条例もできていますが結局、大きな駅にしか設置できないような内容の条例なのでどの駅にもということではありません。と数少ない体験ですが話させていただきました。そうすると、車イスだったら、一人で移動することができないじゃないか、行きたくても行きたいところに行けないなどの意見が交わされました。 私のグループは学生四人と社協の職員二人に私と計七人で交流会が始まりました。ドキドキしながら、私はまず、車イスとなった経緯、今までの自分の体験談を話して、質問をどうぞと言ったとき、しばらくは誰ともなく考え込んでいる様子でしたが、職員さんのフォローで少しずつ質問がありました。その中でも車イスでの移動手段は?と聞かれた時にはほとんどが車で電車・バスなどの公共交通機関はあまり利用していません。バスは全く利用していませんが、以前、電車・汽車は何度か利用しました。電車は比較的ホームとの差があまりなく乗りやすかったけれど、汽車はその駅々で段差があったり、なかったりしています。また、エレベーターや昇降機が設置してあるところはホームまで行きやすいんですが、無いところは階段を何人もの手を借りて手伝ってもらわないといけません。また、駅にはエレベーターなどの設置を義務付けするなどの条例もできていますが結局、大きな駅にしか設置できないような内容の条例なのでどの駅にもということではありません。と数少ない体験ですが話させていただきました。そうすると、車イスだったら、一人で移動することができないじゃないか、行きたくても行きたいところに行けないなどの意見が交わされました。それから、私は手伝っていただいたら、ありがとうと言うのが当然だと思うのですが、中には手伝うことが仕事だから当たり前で礼を言う必要は無いと言う考えを持つ人もいます。と話したときには物理的なバリアフリーも考えていかなければいけませんが、心のバリアフリーも考えなくてはと白熱した(?)意見も交わされました。 それぞれのグループで意見が交わされ、あっという間に時間が過ぎて、一日目が終わりました。 起きられるかなという心配をよそに起床時間(七時)の二時間前ぐらいから目が覚めて二日目の朝を迎えました。まず、車イス・アイマスクの説明を受けて、昨日分かれた三つのグループで直方駅周辺、商店街などのコースを実際に車イス・アイマスクを使って学生さんたちに体験してもらいました。晴天に恵まれ、福祉センターを出発し、御舘橋を渡り、商店街から直方駅周辺までを往復してセンターへと戻っていきました。戻ってからは反省会とまとめで、アイマスクを使用しながらの体験では、日頃、通っているところだから、頭の中にはどこに何があるのかはおおよそ見当はつくけれど、実際にアイマスクを使用してみると怖くて前に進めない、車イスの体験では、まず、思うように動かせない、スロープでも造り方の違いで動きやすいところと動きにくいところがあり、急なところでは怖いと感じるなどの意見がでました。便利なように見えても、まだまだ、不便なことが多くあり、バリアフリーと言われながらも改善すべき点がたくさんあるということ、そして、この体験を通して、今まで見えていなかったことが見えてきて、自分ではまあ、こんな感じかなということが実体験ではこんなにも大変なんだという意見などが交わされて、ほぼ、時間どおりに事が運び、無事に閉会へとなりました。 自分自身もこの二日間は貴重な体験をさせていただいたなと思います。改善すべき点がたくさんあると言っても、自分で進んでこういった事に参加したり、意見交換などもしたりしていかなければならない、また、そうしていかなければ次へと進めない、つなげないなと感じました。 お疲れさまでした、そして、ありがとうございました。(安部 佳代子) |
|
| 感想 筑豊高校3年 Sさん |
|
| この2日間を通して、今まで知ることの出来なかったこと、自分が知ったつもりでいたことなど、沢山のことを学ぶことが出来た。実際に介助してみて、要領よくいかないと、逆に迷惑になってしまうこと。アイマスクをして街中を歩いてみて…すごく怖かった。私はまだある程度その道が頭の中にあるので予想して歩けたけど、全く見えない中で白杖1つで歩くのはどれだけ怖いだろうか。又車イスに乗って、自分の行きたいところへ行くことがどれ程大変か、経験してみて初めてわかったことが沢山あった。本当は何も知らなかったのだなぁと改めて考えさせられた。出来るかわからないけど、もし困っているふうな人を見かけたときは、この経験を生かせてゆけたらと思う。 | |
| 3年 Fさん |
|
| この2日間ワークキャンプに参加して、3班の大久保さんとふれ合えて、とても楽しかったです。 1日目は初めてだから、”大丈夫かな?”とか”うまく話が出来るかな?”と思ったけど、仲良くなれたし、話も少しずつだけど出来たのでよかったと思いました。トイレの世話も着替えも大変だったけどいい経験だったし、分散交流会で大久保さんが1人暮らしをしていて、困っていることや良いことなど沢山聞けて良かったです。 2日目の車イスで町を探検も、アイマスクをして歩いていたら、どこを歩いているかわからないし、1人じゃすごく不安なんで大変だったし、車イスでも道がちょっと斜めになっているだけでも、結構苦労しました。あと自動販売機はお金を入れられても上の方の(ボタンが押せず)ジュースが買えなかったり、スロープがあっても障害者の事を考えてなく、坂がきつくて上るのが大変だったりしたけど、本当この2日間いい経験が出来てよかったと思いました。 (広報誌「わだち」No.102より) |
| 小学校での車いす体験学習 | |
| 日時 2001年7月12日(木) 場所 飯塚市 飯塚東小学校 6年生 |
|
 2001年7月12日(木)飯塚東小学校6年生の、車イスとアイマスク体験のお手伝いに行って来ました。(ゲストティーチャーというのだそうです。) 2001年7月12日(木)飯塚東小学校6年生の、車イスとアイマスク体験のお手伝いに行って来ました。(ゲストティーチャーというのだそうです。)車イス体験は、車イス利用者がかかわり教える(伝える)事が大切ではないかと思います。実際に車イス利用者に会う、話す事から始まり、車イスに乗ってみる、車イスを押してみる、という体験の中で「どこかが、何かが違っていても、互いを認め合い、共にいきる」社会の大切な事を感じ取ってほしいなと思います。  今回、事務局長の大里さんとご一緒したのですが、その事が大変良い勉強となりました。 今回、事務局長の大里さんとご一緒したのですが、その事が大変良い勉強となりました。私は地元の若宮町の小中学校に呼ばれる事がありますが、いつもどういうふうに教え(伝え)たらよいのかと考えていました。大里さんはひと通りの車イス体験のあとに自作の紙芝居を使い、生徒さんたちに「障害をもっている人たちも、ほんのちょっとしたまわりの気遣いで生きて行きやすい社会が生まれる」と分かりやすくお話されました。おもわず、うーん・・・これだ!(紙芝居の絵と文が絶妙)と思いました。 最近、総合的な福祉の時間という授業が導入された事で学校関係に障害当事者として呼ばれる機会が多くなりましたので、私たちもどう教えるか(伝えるか)を考えていかなければならないのではないかと思います。そして、そのための勉強する場も必要ではないかと思いました。(下川 厚子) (広報誌「わだち」No.108より) |
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」