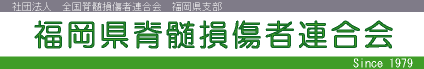
| 出前福祉講座活動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ページ | |
| 篠栗町立篠栗中学校車イス学習出前講座 | |
| 第1回 講話 「車イスを使って生活をしている人の実情に学ぶ」 平成16年6月22日 篠栗町立篠栗中学校 1年生(38名) 講話者 正岡 功 ・ 西山利明 |
|
 福岡県脊髄損傷者のホームページを見て出前講座の依頼ありましたと、編集局長の藤田さんより福岡支部へお電話を頂き、早速、篠栗中学担当のT先生と連絡をとり、福脊連春日クローバープラザ事務所にて、織田顧問・正岡・西山4人で打合せをし、講座をお引き受けいたしました。 福岡県脊髄損傷者のホームページを見て出前講座の依頼ありましたと、編集局長の藤田さんより福岡支部へお電話を頂き、早速、篠栗中学担当のT先生と連絡をとり、福脊連春日クローバープラザ事務所にて、織田顧問・正岡・西山4人で打合せをし、講座をお引き受けいたしました。篠栗中学は、八木山の麓に位置し山と緑の自然環境に恵まれた仏の里、恵まれた環境の中にあり、生徒も非常に礼儀正しく福祉の勉強をしようと言う強い熱意が見られました。 車イスに関しては、生徒38名の参加で、「車イスを使って生活をしている人の実情に学ぶ」と言うテーマで、正岡さんと、西山2人で参加しました。会場は、2階の音楽教室、エレベータがないので、男子生徒が協力し、私たち2人を抱え会場まで案内してくれました。いきなりの実体験、汗だくになり良くがんばってくれました。私も正岡さんも、何か生徒たちの熱意と誠意にほだされ心なごむ思いで会場へ入りました。  テーマに沿い、障害者の生活事態・障害との戦いと自立・社会のハード面の環境整備その重要性等、障害者にとって「悲しい事」障害者は、「かわいそう」哀れみの目で見られる「特別視」される障害者に対する差別です。「嬉しい事」は社会の一員として認められ自立して生きていくことです。 テーマに沿い、障害者の生活事態・障害との戦いと自立・社会のハード面の環境整備その重要性等、障害者にとって「悲しい事」障害者は、「かわいそう」哀れみの目で見られる「特別視」される障害者に対する差別です。「嬉しい事」は社会の一員として認められ自立して生きていくことです。 正岡さんと二人で1時間20分お話をしました。特に正岡さんのお話の中に、この篠栗は以前公務でこの地に勤務したことがあるので特に親しみを感じます。これから皆様も人生いろいろな難問に遭遇すると思いますが決して負けないで下さい。不幸にして障害を持つような事があっても諦めてはいけません。私を思い出してください。障害をもっても、負けずに、色々なことにチャレンジして、障害者活動、ダンス、海外旅行等人生をエンジョイしています。「障害者は不便ではあるが不幸ではないのです」皆様も元気でがんばって下さいなどの話をして1回目を終了しました。 正岡さんと二人で1時間20分お話をしました。特に正岡さんのお話の中に、この篠栗は以前公務でこの地に勤務したことがあるので特に親しみを感じます。これから皆様も人生いろいろな難問に遭遇すると思いますが決して負けないで下さい。不幸にして障害を持つような事があっても諦めてはいけません。私を思い出してください。障害をもっても、負けずに、色々なことにチャレンジして、障害者活動、ダンス、海外旅行等人生をエンジョイしています。「障害者は不便ではあるが不幸ではないのです」皆様も元気でがんばって下さいなどの話をして1回目を終了しました。 |
|
| 第2回 車イス体験講座 平成16年7月01日 篠栗町立篠栗中学校 1年生(38名) 体験指導者 中野拓生・正岡 功・西山利明 |
|
 今回は、猛暑の中3人で車イスの体験講座に参加しました。篠栗中学の体育館で車イスの基本操作法、介助の仕方等を実施指導後、学校内を4人グループで段差、教室、体育館及び校舎間の移動、トイレが利用できるか、階段の抱え上げ等、実技体験後は質疑応答を体育館で行いました。なかなか前向きな意見行動が、体育館の蒸し暑さを爽やかな雰囲気にしてくれました。 今回は、猛暑の中3人で車イスの体験講座に参加しました。篠栗中学の体育館で車イスの基本操作法、介助の仕方等を実施指導後、学校内を4人グループで段差、教室、体育館及び校舎間の移動、トイレが利用できるか、階段の抱え上げ等、実技体験後は質疑応答を体育館で行いました。なかなか前向きな意見行動が、体育館の蒸し暑さを爽やかな雰囲気にしてくれました。 終了後、生徒たちは次回の篠栗町の町内を車イスの体験行動に向け実施計画を、今日の体験をもとに自主計画をするそうです。 終了後、生徒たちは次回の篠栗町の町内を車イスの体験行動に向け実施計画を、今日の体験をもとに自主計画をするそうです。篠栗中学の校舎入り口にはスロープが設置され、障害者用トイレもあり、トイレが綺麗に清掃されていたのが好印象でした。 (西山 利明) (広報誌「わだち」No.126より) |
|
| 安徳北小学校 車イス体験学習出前講座 | |
| 車イス体験講座 心のバリアフリーと交流 平成16年7月14日 4年生(52名) 体験指導者 中野拓生・正岡 功・坂本一憲・西山利明 |
|
 福岡県脊髄損傷者連合会クローバー事務所へ車イス体験講座の依頼があり、クローバーにて、安徳北小学校の先生方4名と織田顧問・中野・西山とで体験プログラムについて打合せをし、「心のバリアフリーと交流」をテーマにお引き受けいたしました。 福岡県脊髄損傷者連合会クローバー事務所へ車イス体験講座の依頼があり、クローバーにて、安徳北小学校の先生方4名と織田顧問・中野・西山とで体験プログラムについて打合せをし、「心のバリアフリーと交流」をテーマにお引き受けいたしました。安徳北小学校は、筑紫郡那珂川町の新幹線JR福岡駅の近くで、新興住宅街の中にありました。当日は連日の猛暑、学校の校門を入りましたが、玄関にはスロープが有りません。先生方に介助をお願いし校舎へ、会場の体育館へ入ると高熱で蒸し風呂状態、一時はどうなるものかと思いました。  生徒たちの元気で素直な笑顔で「お願いします」と挨拶されると、私達も気を取りなおし、車イスの生活の実態、障害者問題等、体験指導者4人でお話をしました。車イス体験は、車イスの基本操作及び介助者の心構え等を説明後、会場にスラローム、段差、障害物等のコースを4人1組12台の車イスで体験活動を行いました。生徒たちは真剣に童顔に汗しながらがんばる姿を見ていると、福祉教育は子どものころからと言うことが良く解ります。 生徒たちの元気で素直な笑顔で「お願いします」と挨拶されると、私達も気を取りなおし、車イスの生活の実態、障害者問題等、体験指導者4人でお話をしました。車イス体験は、車イスの基本操作及び介助者の心構え等を説明後、会場にスラローム、段差、障害物等のコースを4人1組12台の車イスで体験活動を行いました。生徒たちは真剣に童顔に汗しながらがんばる姿を見ていると、福祉教育は子どものころからと言うことが良く解ります。 質疑応答の時間に、正岡さんが(さすが、元ミスターポリスマン)、海外旅行の折購入した外国の車のナンバープレート数枚を見せると、子どもたちは興味津々の眼差しで説明を聞いていました、子どもたちには何か目新しいものも必要のようです。 質疑応答の時間に、正岡さんが(さすが、元ミスターポリスマン)、海外旅行の折購入した外国の車のナンバープレート数枚を見せると、子どもたちは興味津々の眼差しで説明を聞いていました、子どもたちには何か目新しいものも必要のようです。終了後校庭で、私たちの車を取り巻き、車の乗り降り及び操作の仕方を見学、障害者駐車場の3.5メートル駐車スペースの必要性を見てもらい終了。 帰り際に、「僕たちもこれから障害者の方に、こちらから声をかけお手伝いをしたいと思います。元気でがんばってください」の言葉が印象的でした。(西山利明) |
|
| 生徒さんから感想文が届きました | |
安徳北小学校 4年生 車いすの人は、ふつうの人よりも生かつしにくいと思っていたけど車いすをじょうずに使えば世かいりょこうもできるなんてびっくりしました。だんさでもかるがるのぼっていたのですごいと思いました。車いす用の車があんなにくふうしているなんて思いもしませんでした。車いすのことをいろいろおしえてくれてありがとうございました。 TSくん 車いすののりかたやたたみかたや会場の仕方を教えてくれてありがとうございました。 いろんな所で足の不自由な人で車いすをのっていた人を見かけたら、「わたしになにかてつだいはありませんか?」と聞こうと思いました。足の不自由な人でもどこでも行けるんだなぁと思いました。 NRさん ぼくは車いすをおしえてもらったおかげでふべんだなとおもっていたけどあまりふべんじゃないことがわかりました。ターンとかむずかしいとおもったけどけっこうかんたんそうとおもいました。おしえてくれたことをいかしたいとおもいます。車いすのことをおしえてくれたひとたちありがとうございます。 NRさん 車いすのひろげ方や、おりたたみ方、車いすから車に乗るときなどを教えてくれてありがとうございました。私は、足の不自由な人は、じこや、びょう気で足がまひをしても車いすがあれば、足のかわりの役目をはたしてくれて、とっても大切なもとのいうことがよくわかりました。ありがとうございました。 NYさん 車いすに乗って、だんの所とか、さい初の所とかで、両手を強くするのとか、声かけをするのとかは、はじめてわかりました。おす時の声かけはぜんぜん知らなくて、話の時に教えてもらって、おす時にわすれていて、だんの所で言ってもらって、その時に思い出しました。車いすのたたんであける時、指を内がわにしないと、指が切れると言われた時こわかったです。でも、足がふ自由になった時とかできるので、教えてもらってよかったです。ありがとうございました。 FMさん わたしがはじめてしったことまなんだこと思ったことがいっぱいあります。わたしは車いすに乗っていた人は、どこにもいけないのかなと思ったらそうでもありません。車いすに乗っている人も、りょこうやさん歩とかもいけるから車いすに乗っている人も、かなしくもありません。そして、わたしがまなんだことは、車いすの人でも、坂道がたいへんです。下り坂では、急な坂道のときは、車いすを反対にして、うしろをもってもらって、おります。これがたいへんだなと思いました。 WMさん わたしは、キャスターを上げるステッピングバーをおしてキャスターを上げることがわかりました。 車いすの人を、おす時は坂道だったらうしろむきでおして上が道だったら、いつもどおりてどいいけど足をふんばってやらなくちゃあぶないと言うことがわかりました。 それとシートをひろげるとき、手は外がわに出すのではなくうちがわに出すことがわかりました。 わたしのおばーちゃんは、足がふじゆうで車いすです。今ならったことをおじいちゃんにおしえて、おばーちゃんにやってあげようと思います。 YMさん 今日は車いすの事を、いろいろ教えてくださってありがとうございました。わたしが、今日初めて知ったことは坂を下りる時は、後ろ向きになって下りるという事でした。 あと、「ふつうに歩いていても、見えなかった物が、車いすに乗っていると見えることがある。」という言葉にかんげきしました。 あと一つ車いすをおしている人は、つねに前を向いてしょうがい物に気をつけないということも分かりました。今日はありがとうございました。 OCさん (広報誌「わだち」No.126より) |
| 平成16年度 福岡県高等学校家庭クラブ連盟指導者養成講座 “「障害」者の福祉とは何だろう” |
|
| 日時/平成16年8月18日 (260名) 場所/クローバーホール 講演者/織田 晋平 |
|
| 去る、8月18日に県内の高校生の指導者養成講座で織田顧問が“「障害」者の福祉とは何だろう”という表題で講演しました。 <講演の内容> 1.障害者は市民として認められ(保障)ているか? 2.一般的な観方とはどういったものか? 3.障害レベル(機能)とは、何を意味するのか? 4.眼鏡と車イスは、どのような道具か? 5.「障害」者の「害」という字をどうのように読み取るのか? 等の視点から「障害」を持つ人々の置かれている存在と、社会一般の見方について、その「区別から差別」の発生の根拠について、問い返す内容の提起をされた。 (織田 晋平) |
|
| よせられた生徒さんの感想です (すべて原文のまま) |
|
(広報誌「わだち」No.127より) |
|
| 安徳小学校 車イス体験学習出前講座 | |
| 平成16年11月10日(水) 4年生(60名) 体験指導者 西山利明・正岡 功 |
|
今日、那珂川町「安徳小学校」4年生に私と西山氏が「ゲストティーチャー」として福祉授業をしました。全盲の方が一クラス持ち、車イス使用者で一クラス持ちました。 |
|
  |
|
|
私と西山氏で、前半は2人で交代に話をしました。後半は学校の周りを車イス10台くらいを使って体験学習をしました。 |
|
  |
|
| (正岡 功) (広報誌「わだち」No.127より) |
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」