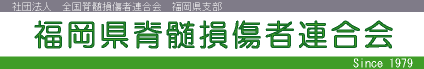
| 出前福祉講座活動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ページ | |||
| 総合的な学習 「共に生きる・車イスを使ったスポーツに挑戦しようー」 |
|||
| 日時 2002年10月22日(火) 場所 北九州市 上津役小学校 5年生 |
|||
| 下記の要望で2回目の出前福祉講座に行きました、今回も車から降りるところを見てもらい、何故広くスペースが必要なのかを理解してもらい、そこから生徒さんに体育館内に抱えてもらう、体育館にはかわいいクス玉が用意されていて、家内と一緒に開けたり、5年生全員で校歌を演奏してくれる華やかなお出迎えでした。 | |||
|
|||
| Ⅰ.自己紹介、Ⅱ.車イスで生活するようになって、Ⅲ.困っていること | |||
 感激しながら自己紹介から始めて、昭和53年5月、43歳の時に屋根から落ちて車イス生活になってから、今日までの体験談を簡単に話して、③の困っている事では、やはり段差、特に階段があって利用出来ない(JRの駅)事、又車イスマークの事と、新しく出来た4ツ葉マークの事にも触れ、最近スーパーや公共の建物のなどに、車イスマークの付いた駐車場が増えて来て私たちは喜んでいますが、中には一般の車が駐車している(マナー無視)ケースが見られます。入り口に近いから、空いているからの理由ですが、車イスの人は他に停める所が無く非常に困っています。車イストイレも同じような事が言えます。 感激しながら自己紹介から始めて、昭和53年5月、43歳の時に屋根から落ちて車イス生活になってから、今日までの体験談を簡単に話して、③の困っている事では、やはり段差、特に階段があって利用出来ない(JRの駅)事、又車イスマークの事と、新しく出来た4ツ葉マークの事にも触れ、最近スーパーや公共の建物のなどに、車イスマークの付いた駐車場が増えて来て私たちは喜んでいますが、中には一般の車が駐車している(マナー無視)ケースが見られます。入り口に近いから、空いているからの理由ですが、車イスの人は他に停める所が無く非常に困っています。車イストイレも同じような事が言えます。今私たちの会(福岡県脊髄損傷者連合会)でマナーを守って下さいと、チラシなど配って運動を続けています。 |
|||
| Ⅳ.車イスでのスポーツについて | |||
今回は前回と少し学習が異なり、車イスを使ったスポーツに挑戦しよう!と言うことで、車イススポーツの事に関して話しをします。車イススポーツと言っても色々有り、車イスバスケット、車イスマラソン、車イステニス、車イスゲートボール、グランドゴルフ、アーチェリー、風船バレー、これはスポーツに入るかどうか分かりませんが車イスダンスもあります、又ルールも夫々車イスでも出来るように変更されて、私たちの会員の中にも自分達に残された、機能や体力に合ったスポーツを選び頑張っています。 そこで8月末に行なわれた世界車イスバスケット大会の選手に中で、九州から唯一人選ばれた北九州市八幡東区の山見誠治さんについて知っていることが有ったら話して下さいとの事でしたので、ここに平成3年4月に今から11年前ですね、皆さんが生まれる前かな?北九州車イスレーシングクラブの名簿があります。監督、コーチ、マネージャーの次に主将・山見誠治23歳、副将・熊谷敏彦57歳(私)、選手MS33歳、O・T32歳、I・K28歳、Y・H25歳、U・N20歳のメンバーで、平成4年2月に京都車イス駅伝に参加しました。その当時の写真もあります。勿論、山見さんはアンカーでしたが、私は3キロの上り坂で大変苦しかった思い出があります。  他にも大分国際マラソン大会にも何回も出られ何時も上位でした、福岡シティーマラソンなどにも一緒に参加したこともありましたが山見さんはいつもトップクラスで、走るたびにどうしてあんなに速く走れるのだろうかと感心していました。その頃バスケットも同時に練習していたのでしょう。同じ車イス使用者でも私たちとは機敏さが違います。子供の頃に山笠の上から落ちて車イス使用者になってから苦労の連続だったと思いますが、バスケットの日本選手に選ばれるまでの努力は、並大抵ではなかったと思います。山見さんは本当に頑張り屋さんですね。皆さんも頑張っていると良い事がありますよ。私も山見さんとは親子ほど違う歳で、一時ではあれ一緒に頑張れた事を今でも誇りにしています。現在は歳相応の車イスゲートボールを楽しんでいます。来月11月15日には第18回九州身体障害者ゲートボール大会が、福岡市の百道公園球技場で開催されますが、32チームの中に私達の車イスチームも入り頑張ってきます。 他にも大分国際マラソン大会にも何回も出られ何時も上位でした、福岡シティーマラソンなどにも一緒に参加したこともありましたが山見さんはいつもトップクラスで、走るたびにどうしてあんなに速く走れるのだろうかと感心していました。その頃バスケットも同時に練習していたのでしょう。同じ車イス使用者でも私たちとは機敏さが違います。子供の頃に山笠の上から落ちて車イス使用者になってから苦労の連続だったと思いますが、バスケットの日本選手に選ばれるまでの努力は、並大抵ではなかったと思います。山見さんは本当に頑張り屋さんですね。皆さんも頑張っていると良い事がありますよ。私も山見さんとは親子ほど違う歳で、一時ではあれ一緒に頑張れた事を今でも誇りにしています。現在は歳相応の車イスゲートボールを楽しんでいます。来月11月15日には第18回九州身体障害者ゲートボール大会が、福岡市の百道公園球技場で開催されますが、32チームの中に私達の車イスチームも入り頑張ってきます。今日はこれでお話しは終わりますが、これから車イスの体験乗車や介助の勉強をします。車イスが8台用意されていて、全員が一通り室内で試乗して、その後運動場に出ました。 先ず、最初に「介助者の心がまえ」当会の車イス介助入門書を参考にして説明。
以上の説明の後10センチほどの段差の上がり方、降ろし方の介助の方法を、家内がお手本を示してその後、全生徒が車イスに乗る人と介助する人になり、両方の体験をしましたが、始めのうちはうまく行かなかったが、家内の指導のおかげでだんだん慣れてきて、皆が終わる頃には上手に出来る様になり練習は終わる。 |
|||
| 質問・応答 | |||
|
続いて生徒からの主な質問 質問1、お爺ちゃんは、お風呂は如何していますか? 答え、前の家のお風呂は狭くて段が有って、一人では入れませんでしたが、今の家のお風呂は広く、一人でも入れる様に作っています。 質問2、お婆ちゃんは、介助の方法は何処で習いましたか? 答え、長い間お爺ちゃんの介助をしている内に、自然と覚えましたので特別には習いませんでした。 以上で予定の講演を無事に終わりました。最後に全生徒から、お礼を言われ握手を求められそれに応えてその後、再び段差を抱えてもらって校長室まで行き、そこで改めて校長先生からお礼を述べられ謝礼を頂いて、前回の講演の載っている「わだち」を差し上げて帰りました。(熊谷 敏彦) (広報誌「わだち」No.115より) |
|||
| 出前福祉講座体験 宮田東小にて |
|
| 日時 2003年1月31日(金) 場所 鞍手郡宮田町 宮田東小学校 5年1組 |
|
 平成15年1月31日(金)晴れですが、まだまだ寒いこの日、鞍手郡宮田町の宮田東小学校へと出かけました。 平成15年1月31日(金)晴れですが、まだまだ寒いこの日、鞍手郡宮田町の宮田東小学校へと出かけました。ことの始まりは一本の電話からでした。宮田東小学校の五年一組の生徒さんからで「僕たちは、おじいちゃんおばあちゃんのために住みやすい町づくりにしたいのですが、身体が不自由で車イスを使っているお年寄りのためにも車イスのことを勉強したいので協力してください」という内容の電話がありました。5年生というと姪のクラスなので、よくよく、姪にも話を聞いてみると5年生でH園という老人施設へ慰問へ行った後に、おじいちゃん、おばあちゃんのために何かしてあげたいと三つのグループに分かれて、それぞれに活動すると云うことでした。 その中のひとつのグループが「施設改善要求隊」という名前の班で宮田町内で車イスなどで不便なところの改善を町に求めるということで、一緒に行ってもらえませんかとの協力依頼でした。 今、出前福祉講座でそれぞれの福脊連会員の方が活動されています。私自身も中・高生対象で二回ほどですが行かせてもらいましたが、小学生とは初めてのことでしたので、一人では少し不安もあり、大里さんに協力していただいて、その日、宮田東小へと出かけていきました。 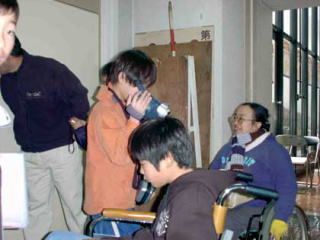 学校に着いて、改善要求隊との対面で男の子ばかり九名でしたので、ちょっとビックリしましたが、お互いに自己紹介をしてから話をしていきました。車イスなどに関してのことや自己の体験談を話していく中で、みんな、熱心に話を聞いてくれたり、「ノーマライゼーション」「ADA(障害を持ったアメリカ人法)」などの言葉が出てきたときはしっかりメモを取ったりしていました。乗り物の話が出たときには、結構詳しく話を知っている子もいたほどでした。 学校に着いて、改善要求隊との対面で男の子ばかり九名でしたので、ちょっとビックリしましたが、お互いに自己紹介をしてから話をしていきました。車イスなどに関してのことや自己の体験談を話していく中で、みんな、熱心に話を聞いてくれたり、「ノーマライゼーション」「ADA(障害を持ったアメリカ人法)」などの言葉が出てきたときはしっかりメモを取ったりしていました。乗り物の話が出たときには、結構詳しく話を知っている子もいたほどでした。小一時間ほど話をしてから、担任の先生や教頭先生の協力を得て、いよいよ宮田町役場と隣接している各施設へと出向いて行ってみると、まず、駐車場で四、五台分はある車イス使用者用駐車場が、丁度、一台分しか空いていなくて、一応、駐車は出来ましたが、まだまだ認識不足だなと感じさせられました。車を降りてから、溝蓋(グレーチング)やスロープなどの点検をしました。そのときは学校側で社会福祉協議会より車イスを借りておられて、子ども達も車イスに乗っての体験も同時にしていきました。グレーチングの目幅は車イスの前輪(キャスター)がはまり込む幅で、はまり込む体験もありました。マリーホール宮田の玄関横のスロープと宮田町中央公民館の短いスロープは、少し急で、案外ときつかったりしました。宮田町中央公民館の中へ入ってからは、宮田文化センターとの境目の三段位の階段のところに木材で作ってある簡易スロープがありましたが、円を描いたような形でしたので介助なしでは上がり下がりは無理でした。 それから同じフロア内で宮田文化センターのところに身障者トイレが設けてあり、そこでも車イスでの体験をしました。他にもエレベーターは無いので階段しか二階へと移動できないので、こんな時はどうしたらいいのかとの問いに、こういう時はみんなで手助けしてくださいとの心のバリアフリーに関してのことも勉強をしました。  そして、外へ出て、マリーホール宮田側から横断歩道を渡って向こう側の歩道へと移動していきました。しかしここでは横断歩道を渡ると直ぐの歩道には十cm以上はある段差があり、渡ってそのままには行けずに少し左か右へと行かないと歩道へと上がれません。歩道自体の幅も狭く、斜めに盛り上がったような形なので、上肢の安定している人でも、注意しながら行かないと危ないところでした。そうやって一時間少しの体験をして、駐車場でお昼のサイレンを聞きながら体験してどうだったのかを意見を交換して、この体験を終えました。このあと学校へ戻り五年生のみんなと給食をいただいて帰りました。 そして、外へ出て、マリーホール宮田側から横断歩道を渡って向こう側の歩道へと移動していきました。しかしここでは横断歩道を渡ると直ぐの歩道には十cm以上はある段差があり、渡ってそのままには行けずに少し左か右へと行かないと歩道へと上がれません。歩道自体の幅も狭く、斜めに盛り上がったような形なので、上肢の安定している人でも、注意しながら行かないと危ないところでした。そうやって一時間少しの体験をして、駐車場でお昼のサイレンを聞きながら体験してどうだったのかを意見を交換して、この体験を終えました。このあと学校へ戻り五年生のみんなと給食をいただいて帰りました。この日の体験は、改善要求隊のみんなの熱心な姿に改めて、私自身もまだまだしっかりと勉強していかなくてはと感じさせられました。また、給食の時は二階の教室までの上がり下がりを担任の先生、教頭先生と一緒に子ども達も一生懸命に手伝ってくれたおかげで二十数年ぶりに美味しい給食をいただくことが出来ました。 紙面上ではありますが、改善要求隊のみんな、五年生のみんな、そして担任のM先生、教頭先生、どうもありがとうございました。校長先生にはご都合で帰る頃にお会いしてご挨拶させていただきました。校長先生にもこういう機会を作っていただき本当にありがとうございました。また、大里さんにも助けていただいて本当にありがとうございました。お疲れまでした。 その日の夜にM先生よりお礼の電話があり、その中で子ども達があの後、メモした言葉についてもっともっっと調べたいとパソコンで検索して勉強していましたと聞いて、この体験が良い印象を与えたのかなと嬉しく思いました。また、これからもこういう活動がお互い様に役立っていき良い方向へと導いてくれたらと願ってやみません。(安部 佳代子) (広報誌「わだち」No.117より) |
| 総合学習 車いすツインバスケットボール体験学習 |
|
| 日時 2003年6月11日(水) 場所 嘉穂郡筑穂町 上穂波小学校 5年生 |
|
|
去る6月11日嘉穂郡筑穂町上穂波小学校の「総合学習」の一環として「車いすツインバスケットボール体験学習」(以下、体験学習)を「博多パトラッシュ」の方々の協力を得て行いました。この体験学習は事務局長の大里さんから声がかかり二年前から各小学校で行っています。 上穂波小学校は、駐車場から校舎、体育館へとたどり着くまでに段差、階段があり、またトイレも車イスでは利用しにくく各先生方にとっても良き体験学習となったのではないでしょうか。 当日は、5年生(以下、生徒)の約一時間半の授業で、最初は実際に博多パトラッシュの方々にゲーム形式でやってもらい、その後生徒達を数班に分けて博多パトラッシュの方々と一緒にパス、ドリブル、シュートを行ってもらいました。最後の質疑応答では生徒達の素直で率直な質問が出て応答に戸惑う場面もありましたが、何よりも生徒達と打ち解けて無事体験学習を終えることが出来ました。予定では、生徒達や先生方も交えてチームを作り実際に「車いすツインバスケットボール」を体験してもらう予定でしたが、時間の都合で出来なかったのが残念でした。 授業も終わり給食の時間となり私達も小学校時代を思い出しながら学校給食を美味しく頂き帰路へと向かいました。 今後も身障スポーツを通じての車いす体験を広めて行きたいと私なりに思っています。 |
|
| 【感想文】 | |
以上が今回お邪魔した上穂波小学校5年生の総合学習「車いすツインバスケットボール」体験学習を終えての感想文です。また、担任のA先生より「一緒にパスやシュートをしたことは、忘れられない思い出になると思います」という暖かい言葉も頂きました。 最後になりましたが紙面をお借りして、上穂波小学校の校長先生はじめ教職員の方々、博多パトラッシュの方々本当にお世話になりました。また機会があれば共に学習して行きたいと思っていますので今後とも宜しくお願い致します。(堤 伸吾) (広報誌「わだち」No.119より) |
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」