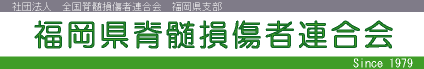
| 出前福祉講座活動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ページ | |
| 大和青藍高校 平成17年度 難病患者等ホームヘルパー養成研修 レポート |
|
| 日時/2005年8月8日(月) 場所/大和青藍高校 講演室 |
|
大和青藍高校(直方市)・介護科3年生45名が夏休みを利用して「難病患者等ホームヘルパー養成研修」の資格を得るため2日間の講座が行われました。 外部からの講義の第一日目は、当事者。二日目は、医学・専門医療病院の先生となっていました。 その講演依頼の話が直方市社会福祉協議会のY氏よりありまして、“学校に紹介させてもらえないでしょうか?”とのお電話をいただきました。 難病と言われたときは、私は難病ではないので・・・?と思いました。確かに発病の原因は不明ですし、広い分野で考えれば、難病に入るかもしれません。私は、他の方にお願いできないでしょうかと言ったのですが、障がいと介護の両面から話してもらえればと言われ、学校へ紹介されました。 それから、学校に伺い介護科のK先生とお会いしてお話をさせて頂き、生徒さんに “ホームヘルパーとしてどう関わればよいか”などの体験を通じて話してもらえないだろうか?と言われ、引き受けることにしました。 翌日が7月5日の障害者自立支援法を考える“福岡県民集会”で、安部支部長さんや、下川さん達と、ご一緒させてもらった時、大和青藍高校から講演の話がきているのだけど、一時間も話すには・・・どうしたらよいか相談しました。その時、行き当たりバッタリでは難しいので、原稿を書くことを教えていただきました。 早速、原稿作りに取りかかり、過去を振り返らないように生活していた私ですが、自分の過去を思い出し、記憶を蘇らせなくてはなりませんでした。 |
|
  |
|
|
ある日突然、病気で動けなくなったことは、あまりにも忙しかった介護の仕事の休養のつもりで、少しの休みがあってもいいのかな・・・!と思って病院生活をしていました。立場が逆になってしまい障がい者の痛みや苦しみを私の身体を通して感じることができました。職場からの退職通知と県リハ入所が重なり、仕事を失った虚しさは言い知れないものを感じ、“自分の障がいを受け入れ、認知する場でもあります”と県リハの先生に言われた、その言葉の重みを実感させられた思い出も、今回の原稿を書いていく過程で再び蘇ってきました。 障がいって!なんだろう?と二年間の間に受容し、受け入れる期間を・・・与えられました。 そんな自分の気持ちや体験、仕事の事を自分なりに原稿を作り、何度も書き直し、不安になったりしたりして、講演の当日を迎えました。 学校の講演室に入り、表題を目にした時は、この場から帰りたい気分になりました。 ええ!ヘルパー養成研修の専門講師・・・。もう開き直おるしかありませんでした。朝、9時から「難病患者等ホームヘルパー養成研修」の開校式が行われ、校長先生のあいさつ、カリキュラムの説明などあり、次に、専門講話と題して私の紹介を受けました。難病患者の専門的な話はできませんでしたが、これから生徒さんたちが福祉に従事されるにあたって、私の体験を通じて、障がいの立場、介護職の立場の両面から話をさせてもらい、その中から感じ取っていただければと話をしました。 “障がい者はみんな何にも出来ない・・・!”と誤解されているといけませんので、たとえADLができなくても、残された機能で、医療・福祉・他の機関と連携をされることで、素晴らしい人生を送られておられる障がい者がいっぱいおられることも話しました。 |
|
 |
|
| 最後に、みんなと一緒に私の掛け声と共に笑顔のプレゼントを教え、あくびをしていた子も、皆、すてきな笑顔になりました。 私のリハビリで始めた“ちぎり絵”3点ほど持って行き、ライフワークになっていることを伝えました。 また、生徒さんたちが、社会に出ると、嫌な事などに遭遇するかもしれませんが、“みなさんを必要とする人が待っている”ことも忘れないで、福祉の勉強にがんばって欲しいと思いました。 今回は、難病患者等のヘルパー資格の研修で、私のような障がい者が、福祉の勉強をされ、多くの知識を学んでおられる生徒さん達に、たまたま、元、介護職だったと言うだけで、福祉の動向は刻々と変化していますし、知らないことばかりの私です。年を重ね・・・見当識障がいを起こしそうな私に若い学生のみなさんと、共有の場が持てたことに、大変うれしく感謝いたしております。講演を終え自分の無知や愚かさに深く反省しています。学校のみなさまに大変ご迷惑をおかけしました。 大和青藍高校の生徒のみなさんのご活躍をお祈りしております。大和青藍高校の先生はじめ生徒さん方にはお世話になりました。ありがとうございました。(東房 晶子) (広報誌「わだち」No.132より) |
| 篠栗中学校車イス出前講座 車イスで町に出かけよう! |
|
篠栗中学校より、昨年に続いて今年も、中学1年生の出前講座の依頼があり、1学期に2度の出前講座で基本的な車イスの介助方法を習得(「わだち」No.131・8月号掲載)、今度は公共交通機関・JRを利用して車イスで町へ出て実体験をしようと10月17日(月)に福岡の街へと体験講習に出かけました。1年生37名、3台の車イスで3班に分けて行い、福岡支部・中野さんと西山が同行しました。 幸い好天にめぐまれ、学校よりJR篠栗駅へと歩道で車イスを押し介助しながら駅へと移動、篠栗駅はバリアフリーになっていました。先ずそこでトラブル、中野さんがトイレ行くとトイレに鍵がかかり開かない、駅員に尋ねると、トイレのある場所は駅の管轄ではないとのこと、篠栗町の管理で連携の問題が起きました。 |
|
  |
|
|
JR篠栗駅は、バリアフリーになっていてスムーズに乗車できました。博多駅に着くと駅員さんが待機していて、「エスカル」(車イス用エスカレータ)にてホームより誘導された。エスカルが車イス使用者1人乗りでいかに不便で時間がかかるか、計5台の車イスの移動で大変でした。 駅員さんを囲みお話を聞き、そして、地下鉄へ移動し中洲・川端駅まで乗車、地下鉄も混雑がなくスムーズに中洲・川端駅へ着き、博多リバレインのエレベータで地上へ、川端商店街を介助しながらキャナルシティ博多へ到着、キャナルシティは自由観察で、各班で見学をし、問題点を探す。中野・西山は久恒先生と同行し、キャナルで食事をしながらご苦労のお話を聞き、障がい者の話などをしました。 |
|
  |
|
予定の時間になり集合地点に全員集り、キャナルシティを出て、博多駅へ歩いて交代で車イスを介助しながら駅へ、私たちもこんなに長い道を押してもらったのは初めてで、生徒さん達が真剣な気持ちで介助してくれる真心を、背中に感じながら博多駅へ到着、篠栗線に乗車し無事篠栗駅へ到着しました。 |
|
  |
|
|
ここで大きな問題がある。篠栗駅のホームは、上りは改札口から直ぐにホームがありバリアフリーだが、下りは線路をまたいで高架橋の急な階段を渡らなくてはならない。中野さんと私は抱えて渡るしかないのでお願いすると、生徒さんのなかで私がと申し出でがあり、4人で抱えることになり、ミスは大きな事故につながりかねないので、先生と駅員さんの監視しのもと、無事渡ることが出来ました。生徒さんは顔を真っ赤に手が痛かったと、手をなでているのが印象的でした。ありがとう。感謝でいっぱいです。 学校まで帰り着き、生徒さんからありがとうございましたと感謝の言葉をいただき終了しました。(西山 利明) (広報誌「わだち」No.133より) |
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」