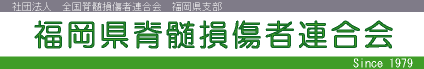
| 出前福祉講座活動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ページ | |
| 宮若市の小学生のためのボランティアスクールに参加して 筑豊支部 安部 佳代子 |
|
| 日時/2007年8月7日(火)、20日(月) 場所/宮若市社会福祉センター |
|
平成19年8月7日、20日の両日に宮若市社会福祉センター(本所)において恒例の小学生を対象としたボランティアスクール(3日間)が開催され、同じ筑豊支部の早原さんと一緒に3日間のうちの1日目にある車イス体験の講師として参加させていただきました。今年度は参加希望者があまりにも多くて、5.6年生だけにしぼって、2回に分けてのスクール開催でした。第1回(8/7)は6年生、第2回(8/20)は5年生で両日合わせて60数名の参加がありました。 両日は10時から始まり、開校式が終わって車イスの扱い方などを説明してから福祉センター付近を車イス、アイマスクで体験するコースへと、いざ、出発していきました。両方の体験が終わって、福祉センターへと戻り、「障害」についてと題して1回目が私(安部)が、2回目を早原さんがそれぞれに30分程度話をさせていただきました。 体験のときは、ほんとに今年は冷夏? と、いいながらも、とても暑い猛暑の中、1回目はまさしく快晴で、2回目はアイマスク体験の折に途中から曇ってきて極微量の雨が数分ほど降り、幾分かは涼しく? 体験できたのかなとは思いますが…。 |
|
  |
|
|
「障害」についての話が終わってから、子どもたちからの質疑応答が20~30分程度あり、途中で自己紹介をしながらの昼食タイムで私たちも一緒にお弁当をいただいて、私はそこで終わりでしたが、早原さんは日頃より点訳サークルでも活躍されており、次の点字体験にも参加されました。 会場は福祉センターといいつつも建物が古いということもあり、バリアフリーとまではいかず、1回目は1階でしたが和室の広間で段差があり、畳の上まであげていただき、2回目は2階(しゃれではないのであしからず…)で、エレベーターは設置してあるのですが…全く使えないという状況なので階段を抱えていただくこととなりました。かえってバリアがあるという点では子どもたちにとって、いい体験となったのかもしれませんし、また、エレベーターなど、あるものが使えないとこんなにも大変だということを福祉センター側にも理解していただくことにもなったのではないかと思います。 こういう体験などは4年生から学校で学習されるので、ほとんどの子どもが扱い方などは大体わかっているところもあるようです。でも、やはり、1~2回だけでなく、何回も繰り返し体験してもらうことで〝障がい者〟に対しての理解をしてもらうことにつながっていくと思いますし、障がい当事者側も繰り返し経験することで伝えることの勉強にもなり、自信にもつながります。 そして、その場の状況などによって違いもありますが、回数を重ねることにより「このことを伝えるにはどうしたらいいのだろう?」ということを考えたり、「あっ、こういう言い方もあるのか!」と気づかされ、話し方の工夫ができるようになっていくと思います。 |
|
  |
|
私自身、伝えることの難しさを味わいながらさせていただいている状況なので、まだまだ、伝え足りないこともあり、「ああ、これも伝えたかったのに…」とか、そのときによってこういうふうに言おうと思っていたことと違うことを言ってしまったりすることやこう思っているのに言えないままで終わってしまうこともしばしばあります。本当に〝伝える〟というのは言葉の使い方や話の仕方をとっても容易なことではありません。 〝障がい者〟となり今日までの生活の中で私自身、タクシーの乗車拒否にあったり、かわいそうにと哀れみの同情を受けたりと苦い思いもしてきましたが、それでもただ、ごく普通に生活していきたいと思っているだけで、その中でどうしてもできないこともあり、そのときの状況によっても違い、また、人の手を借りなければ~という状況もないとはいえません。けれども、たとえ時間がかかっても、周りから見たときに大変そうであっても、自分で最後までやりたいときはすぐに手を出さないで見守っていてほしいと…手伝う前に当事者自身の想いを深く聴いてほしいと強く思うのです。多かれ、少なかれ〝障がい者〟といわれる立場の人はそう思っているのではないのでしょうか…。それとも私だけの意固地な想いなのでしょうか…。そういう想いを理解していただくということと、その想いを伝えることの難しさを気づかされた体験となりました。 |
|
  |
|
まだまだ、勉強不足の私ですが、体験を通しながら、理解を深めていただくように自分自身も成長していきたいと思っています。 今回、ボランティアスクールで出会った子どもたち、お世話いただいたみなさん本当にありがとうございました。そして、また、これからもよろしくお願いいたします。 ~いつの日か、〝障がい者〟という〝ことば〟がなくなることを願いながら~ (広報誌「わだち」No.144より) |
| 「であい夢広場」の車イス体験コーナーの報告 北九州支部 佐藤 カヨ子 |
|
07年11月4日(日)八幡西区にある北九州市立西部障害者福祉会館記念行事「であい・ゆめ広場」において、「思いやりとともに歩こう 車いす体験」と銘打って車イス体験・介護体験を行いました。これは私たち北九州支部の日頃の活動拠点でもある同会館の記念行事に、アトラクション部門として毎年参加しているものです。 今年は開館15周年となりボランティアや地元町内会の人達に支えられて、餅つき・模擬店・バザー・発表・展示などにぎやかに行われました。 |
|
    |
|
この日は天候にも恵まれて、朝早くから会員5名、介護者3名が駆けつけ準備に掛かり先ず、熊谷支部長お手製の段差やスロープで、バリア体験コーナーを会館の駐車場に設け、お祭りの参加者に「車イスの試乗」と「車イスの人を介助する」両方の体験をしてもらおうと言うものです。 |
|
  |
|
あいにく、地元八幡の最大の祭りである起業祭の最終日、風船バレー全国大会とも重なり体験者は34人と例年に比べ少なめでしたが、その分一人一人に丁寧に対応することが出来たのではないかと思います。特に子ども達は興味津々のようで、実際に車イスに乗って見ると3センチの段差を超えるのも難しい、段差やスロープを降ろされる時は車イスが傾いて怖い、などの感想を語ってくれましたが、やはり見ているだけと実際に乗ったり押したりしてみるとは大きな違いがあるようです。また、参加者同士でも色々と話が弾み、こう言うささやかな体験やふれ合いが「障害」や「福祉」を理解するキッカケになってくれたら良いなと思います。 (広報誌「わだち」No.145より) |
| 出前福祉講座 篠栗中学校での体験学習に参加して 福岡支部長 菅原 義和 |
|
| 日時/2007年10月18日(木) 会場/南蔵院(篠栗町) |
|
篠栗中学校には昨年も「出前福祉」に参加しましたが、今年も出前福祉の依頼があり、大山・坂本・菅原の3人で長時間の出前福祉に参加しました。 1回目・2回目は校内にての講演・体育館及び校舎内での車イス体験学習を指導してきましたが、最後は10月18日(木)に「南蔵院」体験学習があり、坂本・菅原で参加してきました。 長時間かけて福祉講座をやってきましたが、実際に外に出て車イス体験をすることが、生徒さん達にとっては身をもっての「バリアフリーに関するいい体験」になった様です。生徒さん達は電車で南蔵院駅まできて、そこから車イス体験となったのですが、一人の生徒さんの作文の中に、電車とホームの間に隙間があったことに気がつき、車イスが隙間に落ち込むのではないかなあという感想を書いています。この一点でも長時間福祉講座をして来たことが生かされていると思います。南蔵院に行くには坂道がきつく、降りる時は後ろ向きに降りる、歩道橋を利用しての階段を下りる際の車イスの取り扱い方も講座での勉強が役にたった様です。 生徒さんから感想文をいただきました。しっかりした内容の文だと思います。1~2名の感想文を載せたいと思います。 最後に1回きりの出前福祉講座ではなく、長時間かけての出前福祉が大事なことだと思います。 (広報誌「わだち」No.146より) |
|
  |
|
| 感 想 文 | |
拝啓 秋空高く、さわやかな頃となりました。いかがお過ごしでしょうか。 さて、先日はお忙しい中、体験学習に来て下さって、ありがとうございました。私達にとって、とても貴重なものとなりました。車イスで行動することは、とても難しいことだということが分かりました。この体験学習が無かったら、私は車イスや福祉とは関係が無かったけど、この体験学習があったことによって、福祉とはどんなことなのか、福祉活動の意味は、何なのかを少しだけ分かった気がします。 南蔵院では、でこぼこした道や坂道が多くて、車イスの方1人では、とてもじゃないけど登れないということが分かり、先生の話によると、坂本さんと菅原さんが「いつもは登れない上のほうまで登れてうれしかった。ありがとう。」といった話を聞き、とてもうれしく思いました。 そして、坂本さんと菅原さんと大山さんのおかげで、たくさんのことを知ることができました。これからの私たちの学習に、よく生かしていきたいと思います。 これから寒くなって参りますが、お体にお気を付けてください。 敬具 |
|
 |
|
拝啓 秋の風がやっと涼しさを運んでまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 さて、先日の「体験学習」では、お忙しい中いろいろと教えてくださり本当にありがとうございました。ぼくにとって貴重な体験になりました。 先日の体験でぼくはいろいろ学びました。とくに溝のある細い道では、前に1人いて、手伝えば楽に通れたことが心に残っています。そして南蔵院を登るときの坂は1人だけではとてもきついけど2人だと楽に登れるということも学びました。 ぼくは電車に乗って電車から降りるときに車いすに乗っている人はきついだろうなと思いました。それは降りるときにある電車と駅の間の溝です。もしかするとタイヤが落ちるかもしれない溝があって、やっぱりいろいろきついこともあるだろうなと思いました。ぼくはもし、電車でそういう人を見かけたら手伝えることをしていこうと思いました。 これから寒くなって参りますので、お体には気をつけてお過ごし下さい。本当にありがとうございました。 敬具 |
|
 |
|
拝啓 秋の風がやっと涼しさを運んでまいりました。皆様は、いかがお過ごしでしょうか。 さて、先日の「体験学習」では、お忙しい中、いろいろと私達のために教えていただき、本当にありがとうございました。車いすをあまり使ったことがない私達にとって、とても貴重な体験となりました。私は、いままでに一度も車いすに乗ったり、おしたりした経験がなく、車いすなんて簡単なものだと思いこんでいました。 一番初めに、体育館で車いすに初めて乗った時、自分自身で動かしてみると、思った以上にきつかったし重く感じました。実際に外で車いすを動かしてみると、体育館よりずっと重かったです。それに外では、まっすぐに行かずにすぐ斜めに行ったりして、車いすを自由に動かすことが難しく、南蔵院の一日体験学習で、一番「きつい」と思った所は階段をおりる所でした。 車いすで毎日生活するのは、とても大変なんだなぁと思いました。だから、これからはボランティアをしていきたいです。 皆様のご健康をお祈り申し上げます。 敬具 |
| 篠栗中学校出前福祉講座(1) 福岡支部長 菅原 義和 |
|
| 日時/2008年6月25日(水) 会場/篠栗中学校(篠栗町) |
|
6月9日篠栗中学校の高橋先生より、バリアフリーについて学習するコースを今年も施したいとの事で講師派遣の依頼があった。今年の計画としては、6月25日(水)「車いすで生活する方のお話を聞く」、7月2日(水)「車いすの基本操作(校内で)」、7月9日(水)「車いすの応用操作(校外で)」、10月15日(水)「体験活動(バリアフリー博多探訪)」、12月17日(水)「発表会」と予定が組まれている。第1回目として6月25日(水) 久保、坂本、菅原の3人が講演をした。1番目の講師として、久保さん(↓)が講演にはいった。 前半、自分が障がい者になった生い立ちなどを話された。 6歳時に脊椎カリエスに罹り4年間自宅療養の後、10歳で小学校に入学したこと、高校入試のときに障害があることを理由に県立高校入学を拒否されたこと。就職試験の面接で、一人の人間として見られず「障害」のみを見て劣等者と判断されたことなどを、噛んでふくめるように話していかれた。紆余曲折の後、自分のことを理解する人と出会い、障害のある人もない人も「共に生きる」という重要性を学んだことを伝えられた。 |
|
  |
|
後半では、障害の有無に関係なく人間を人間としてみる「ノーマライゼ―ション」と、人間らしい生活の回復を目指す「リハビリテーション」に関しては、人としての思いやりなどを中心に話していただいた。熱心に聴いており、なかにはメモを取っていた生徒もいた。ちょっと難しいところもあり、中学1年生になってまだ3ヶ月の生徒さん達には理解できなかったかもしれないが、最低の線、これだけは伝えておかなければならない「障がい者福祉」の2本柱を踏まえ、わかりやすく「共に生きる」ことの大切さについて、教え育むような講演であった。2番目は菅原(↓)が何故、障がい者になったかの過程を話し、障害を持つことになっても自分が卑屈にならずに、前向きに物事を考え行動していけば、ある程度のことはかなえられると思う。又、私達障がい者が後々の代の人々に伝えていくことにより、少しではあるが着実に変わっていくことを生徒さん達に伝えた。 |
|
  |
|
3番目に坂本さんが簡単な自己紹介をして、障がい者になった事故の話をしました。 次に車いすの基本的な操作の仕方を説明し、リハビリで操作を覚えたことを話しました。家での生活の様子など身振り手振りを交えて紹介し、段差で困ることや、バリアフリーの現状を身近なところの例を挙げて説明されました。 生徒さんの質問に答えて、講義を終了しました。 |
|
| 篠栗中学校出前福祉講座(2) 福岡支部長 菅原 義和 |
|
| 日時/2008年7月2日(水) 会場/篠栗中学校(篠栗町) |
|
7月2日(水)午後2時10分より2回目の出前福祉講座にゲストティーチャーとして指導。31度を越す真夏日で体育館内は熱気がむんむんしていた。 今回は「車いすの基本操作について」のテーマで大山、菅原2人で実技体験に参加して指導した。 大山さんより介助者としての心構えの講話、車いすの構造、取り扱い方の説明後、体育館内において実技指導に入った。スラロームで車いす操作を学んでもらい、次に薄いマットでティッピングレバーを踏んで段差をクリヤーする 事の説明をしながら実技に入った。 |
|
  |
|
全く車いすに触ったことも無い生徒さん達だったので、うまく指導できるかと少し心配しましたが、意外にも男女ともに車いす操作にも慣れ体育館内の講座はスムーズに終了した。因みに生徒さん達に、「町で車いすを見かけますか」と聞くと、ほとんどの人達は「見かけた事がない」との返事が返ってきた。 体育館内での実技終了後、校舎を出ての実体験、最初に障害者用トイレが常設されているので、車いすをどのようにアプローチして対応するかの実技を体験してもらった。 トイレは専用ではあるが中で回転するのがやっとの広さだ。次に階段を上げるという実技に入った。中学生とはいえ、まだ力は無く4人1組での対応だが、車いすを持つ位置を確認させ、声をかけ合って力が一つに成るように抱え上げることを確認させる。 |
|
 |
|
階段上りの実技も幾分斜めになったり、前輪の担当者が横に行ってしまったりと、危ない所があったが事故も無く終了した。今日の体験が2学期に入り、博多探訪(10月2日)という体験活動を予定しているが、必ず外での体験に役立つものと思う。 毎年、篠栗中学校は総合的な学習の中で、福祉の勉強をしていることは、生徒さん達が成人した時に、役に立つものだと思う。 |
![]() 活動の紹介
活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起
啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係
労災(労働災害)関係
![]() 出前福祉講座
出前福祉講座 ![]() 車いすダンス
車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ
バリアフリー釣りクラブ
![]() レクリエーション
レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」
広報誌「わだち」